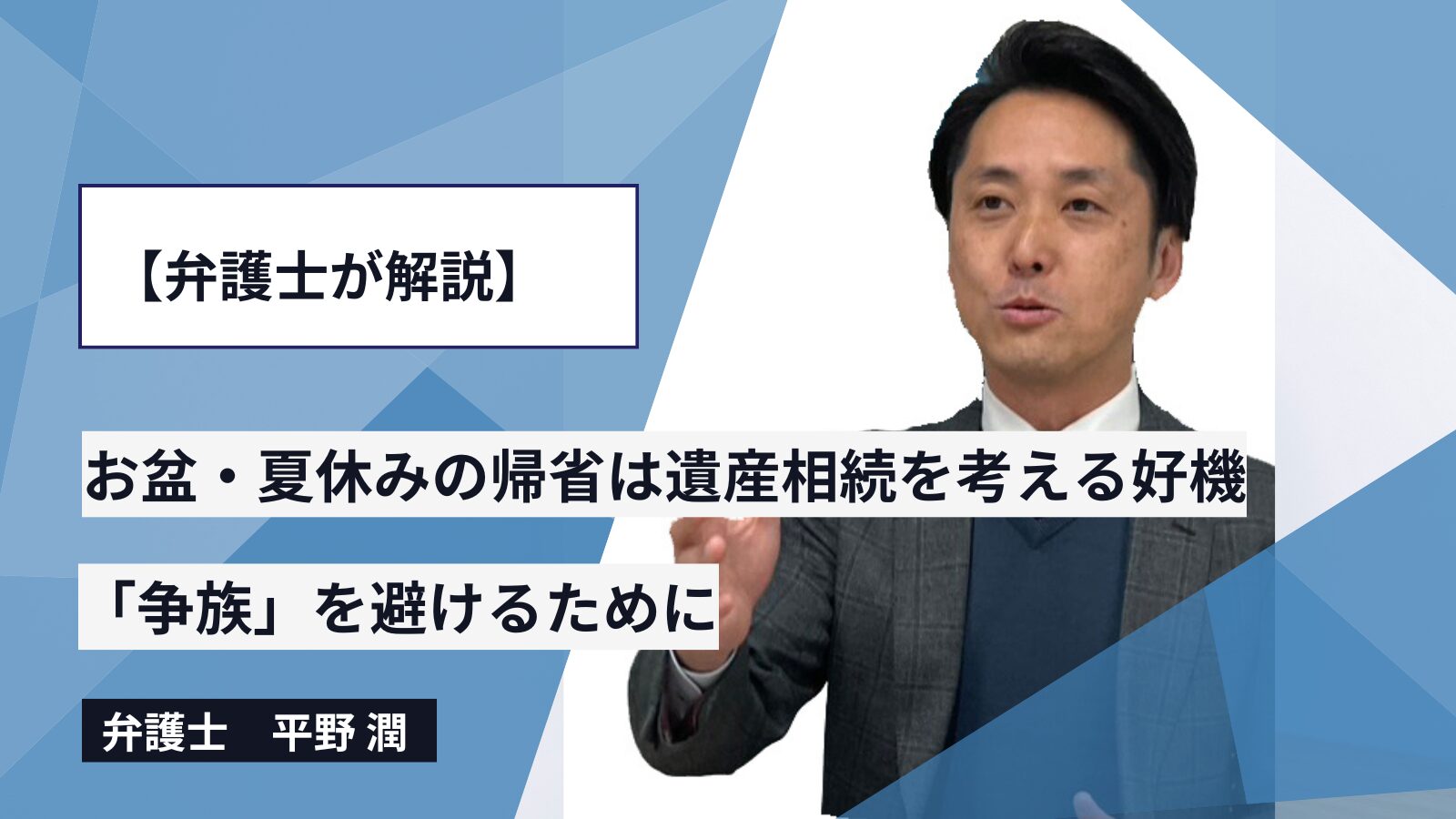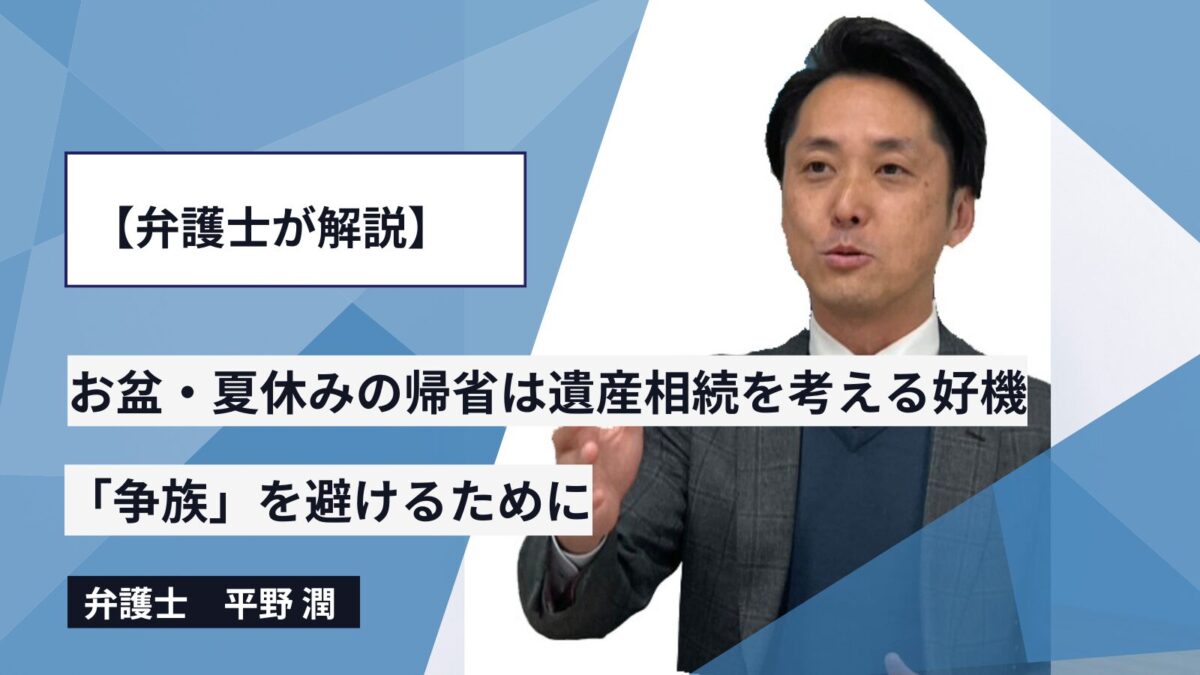
お盆や夏休み。故郷へ帰省し、家族や親戚と顔を合わせ、亡くなったご家族を偲ぶ、かけがえのない時間です。懐かしい思い出話に花が咲く一方で、将来のこと、特に「遺産相続」の話が持ち上がることも少なくありません。
親族が一堂に会するこの時期は、相続について話し合う良い機会です。しかし、この話し合いがきっかけとなり、これまで良好だった関係に思わぬ亀裂が生じてしまう「争族」へと発展してしまうケースが後を絶ちません。
「うちは財産なんてないから大丈夫」 「兄弟仲が良いから揉めるはずがない」
そう思っていても、いざ相続が始まると、些細な認識の違いや感情的なもつれから、深刻なトラブルに発展することがあります。
大切な家族との絆を守るためにも、相続について正しい知識を持ち、いざという時に頼れる専門家の存在を知っておくことが重要です。この記事では、遺産相続の基本的な流れから、弁護士に相談するメリットまで、詳しく解説していきます。
相続はいつから始まる?-四十九日や法要が話し合いのタイミングに

人が亡くなられた瞬間から、法律上、相続は自動的に開始されます。そして、相続人は様々な手続きを決められた期間内に行わなければなりません。
遺産相続の主な手続きと期限
遺産相続の手続きは複雑で、期限が定められているものも多くあります。
| 遺言書の有無の確認 | まず、故人が遺言書を残していないかを確認します。自筆証書遺言は家庭裁判所での「検認」という手続きが必要です。公正証書遺言は公証役場で検索することができます。 |
|---|---|
| 相続人の調査・確定 | 故人の出生から死亡までの戸籍謄本等を取り寄せ、誰が法的な相続人になるのかを確定させます。兄弟姉妹が多い場合や養子縁組があった場合など、相続人の調査に時間がかかることもあります。 |
| 相続財産の調査・確定 | 預貯金、不動産、有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もすべて調査します。相続人が把握していない財産や借金が見つかることも少なくありません。 |
| 相続放棄・限定承認の申述 (期限:相続の開始を知った時から3ヶ月以内) |
マイナスの財産(借金など)が多い場合などに、家庭裁判所で相続を放棄したり、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する手続きです。この3ヶ月という期間は非常に短いため、注意が必要です。 |
| 所得税の準確定申告 (期限:相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内) |
故人のその年1月1日から死亡日までの所得について、相続人が代わって確定申告を行います。 |
| 遺産分割協議 | 相続人全員で、誰がどの財産をどれだけ相続するのかを話し合います。相続財産の大小にかかわらず、相続人間で意見が食い違うことも少なくありません。 |
| 遺産分割協議書の作成 | 協議がまとまったら、その内容を書面にし、相続人全員が署名・押印します。これは不動産の名義変更や預貯金の解約手続きに必要となります。各手続に使用できるよう、正確に記載することが重要です。 |
| 相続税の申告・納付 (期限:相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内) |
相続財産の総額が基礎控除額を超える場合に必要です。それまでに、相続財産を正確に把握しておくことが重要です。 |
四十九日や一周忌などの法要は、親族が集まりやすいため、遺産分割の話し合いを行う良い機会と捉えられがちです。しかし、上記のように相続放棄の期限は3ヶ月と短く、相続財産の調査が難航している間に期限を過ぎてしまい、多額の借金を背負うことになってしまった、というケースも少なくありません。
相続が開始されたら、法要を待つのではなく、なるべく早く専門家も交えて手続きの全体像を把握し、計画的に進めることが肝心です。
なぜ遺産分割は揉めるのか?-「争族」の火種

裁判所の司法統計によると、遺産分割をめぐる争いは、決して富裕層などの特別な家庭だけで起こるわけではありません。
遺産分割事件のうち認容・調停成立件数(令和4年)を見ると、遺産の総額が「5000万円以下」のケースが全体の約76%、「1000万円以下」のケースだけでも約33%を占めています。
(出典:裁判所 司法統計「令和4年 司法統計年報(家事編)」第52表 遺産分割事件のうち認容・調停成立件数ー遺産の価額別ー全家庭裁判所)
このデータが示すように、「遺産が大きいからこそ揉める」「財産が少ないなら揉めない」とは一概に言えません。むしろ、分けにくい不動産が財産の大部分を占めるようなケースで、トラブルは起こりやすいのです。
よくあるトラブルのパターン
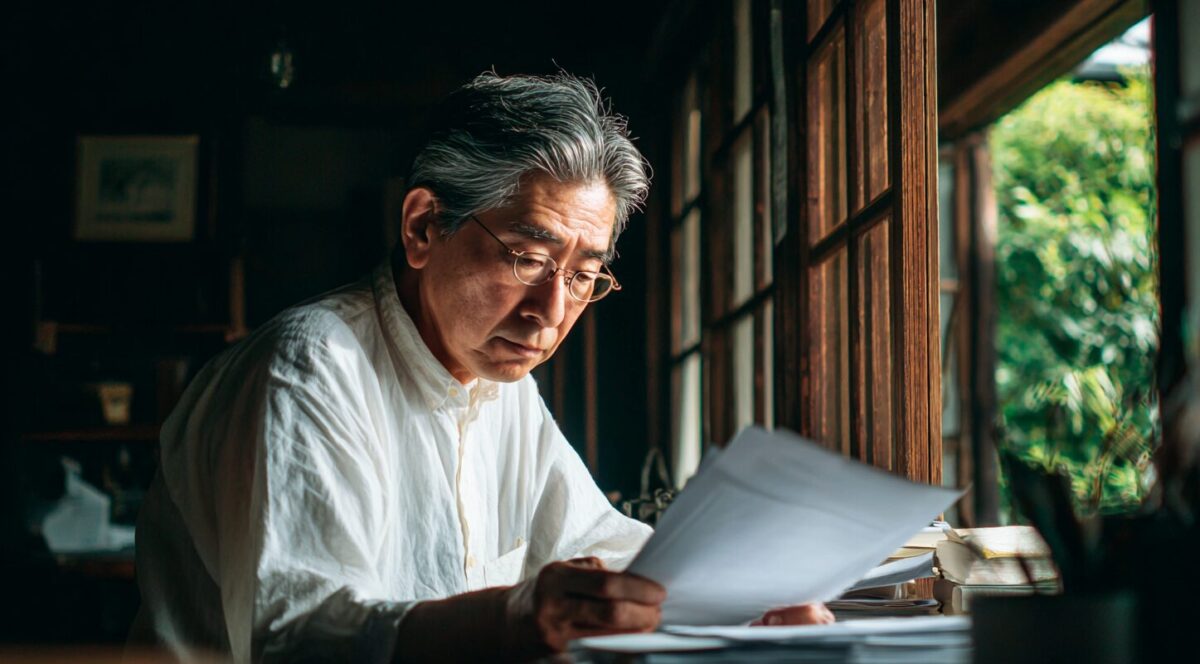
1.不動産の分け方
実家など、簡単に分割できない不動産の評価額や、誰が相続するかで意見が対立します。
2.寄与分(きよぶん)の主張
長年の介護や家業への貢献をどう評価するかで対立します。
3.特別受益(とくべつじゅえき)の主張
生前贈与の有無・公平性を巡る争いです。
4.預金使い込み疑惑
故人の預金の引き出しを巡り疑念が生じます。
こうした問題は、当事者同士の話し合いだけでは、感情的なしこりを残すばかりで、解決が困難になることが少なくありません。
感情的な対立を避けるために-弁護士に依頼する5つのメリット

親族間の話し合いが行き詰まってしまった場合、あるいはそうなる前に、相続の専門家である弁護士に相談・依頼することをお勧めします。弁護士は、あなたの代理人として、法律に基づき、あなたの正当な権利を守るために活動します。
メリット1:正確な法的アドバイスと見通しが得られる
相続に関する法律や判例は非常に複雑です。ご自身の状況で、法的にどのような主張が可能なのか、どの程度の権利が見込めるのかを正確に把握することができます。「寄与分」や「特別受益」の主張が認められる可能性、不動産の適正な評価方法など、専門的な知識に基づいた的確なアドバイスを提供します。
メリット2:精神的・時間的な負担から解放される
親族と直接お金の話をすることは、精神的に大きな負担を伴います。弁護士が代理人として交渉の窓口となることで、相手方と直接顔を合わせるストレスから解放されます。また、相続人の調査に必要な戸籍謄本の収集や、煩雑な相続財産の調査、遺産分割協議書の作成といった手続きをすべて任せることができ、ご自身の時間と労力を大幅に節約できます。
メリット3:冷静かつ対等な交渉が実現できる
当事者同士では感情的になりがちな話し合いも、弁護士が間に入ることで、法的な論点に絞った冷静な交渉が可能になります。相手方が無理な主張をしてきた場合でも、法律の専門家として、毅然とした態度で論理的に反論し、交渉を有利に進めることができます。相手方に弁護士がついている場合は、こちらも弁護士を立てなければ、知識や交渉力の差から、不利な条件を飲まざるを得ない状況になりかねません。
メリット4:調停や審判になっても安心
話し合いで解決しない場合は、家庭裁判所での「遺産分割調停」や「審判」という手続きに移行します。弁護士に依頼していれば、これらの裁判手続きもすべて代理人として対応します。裁判所に提出する書面の作成から、調停期日への同席まで、一貫してサポートを受けられるため、安心して手続きに臨むことができます。
メリット5:円満な解決を目指せる
弁護士の役割は、必ずしも争うことだけではありません。法律に基づいた公平な解決案を提示し、お互いの妥協点を探ることで、親族関係に配慮した円満な解決を目指すことも重要な役割です。第三者である専門家が加わることで、感情的な対立を避け、お互いが納得できる落としどころを見つけやすくなります。
まとめ:問題が深刻化する前に、まずはお気軽にご相談ください

お盆や夏休みは、ご家族の将来を考える絶好の機会です。遺産相続は、誰にでも起こりうる身近な問題であり、準備が早すぎるということはありません。
「何から手をつけていいか分からない」 「他の兄弟の考えが分からず、不安だ」 「遺言書の内容に納得がいかない」
少しでもこのような不安や疑問を感じたら、問題がこじれて「争族」となってしまう前に、ぜひ一度、私たち蒼生法律事務所にご相談ください。法律の専門家として、あなたの権利を守り、大切なご家族との絆を未来へつなぐお手伝いをさせていただきます。
初回のご相談は無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。

2004年の弁護士登録以降、個人・法人問わず幅広い事件を担当し、クライアントにとっての重大事には誠実かつ丁寧に寄り添う。命運に配慮し、最善策を模索。豊富な実績と十分なコミュニケーションで、敷居の高さを感じさせない弁護士像を追求してきた。1978年大阪府出身、京都大学法学部卒業。2011年に独立。不動産・労務・商事・民事・破産・家事など多様な分野を扱い、2024年6月に蒼生法律事務所へ合流。相続・遺言