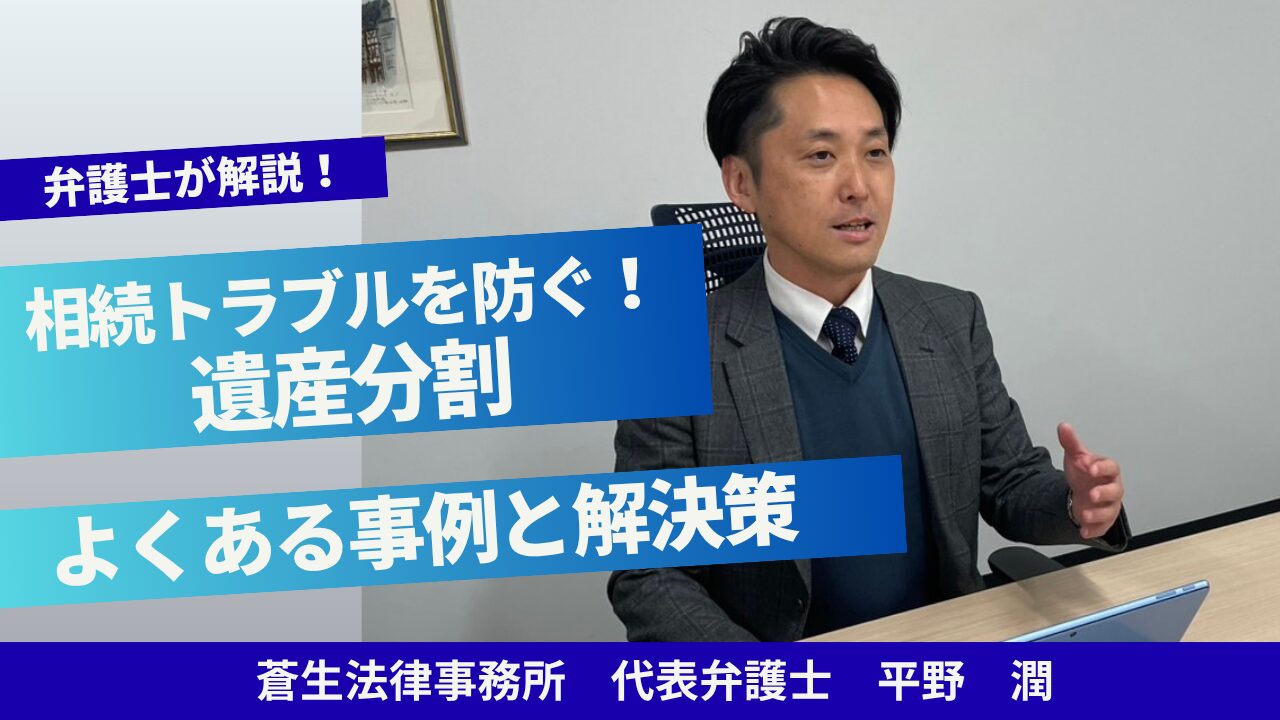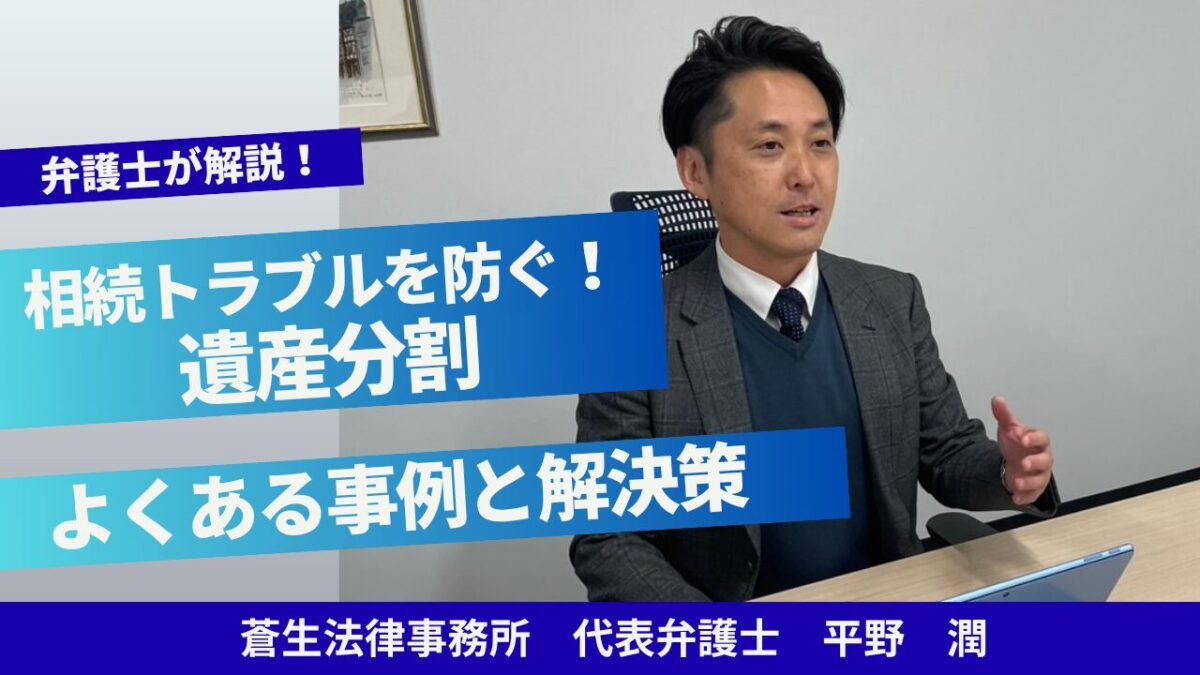
皆様、こんにちは。
蒼生(そうせい)法律事務所、代表弁護士の平野 潤(ひらの じゅん)です。
この度は、当事務所のブログをご覧いただき、誠にありがとうございます。
相続手続きの中でも、ご家族が最も頭を悩ませ、時には深刻な対立にまで発展してしまうのが、相続財産の「分け方」、すなわち「遺産分割」のステップです。
「相続財産の調査も終わり、あとは分けるだけ。そう思っていたのに、兄弟の意見が全く合わない…」
「父が亡くなり、会ったこともない親戚が相続人だと言われて、どうすればいいか分からない…」
「親の介護をずっと私だけがしてきたのに、他の兄弟と同じ分け方なんて納得できない!」
遺産分割は、単なる「お金の計算」ではありません。そこには、ご家族それぞれの故人への想い、これまでの歴史、そして将来への希望や不安といった、様々な「感情」が複雑に絡み合います。だからこそ、相続における最大の難関と言われるのです。
しかし、どうかご安心ください。法律には、こうした複雑でデリケートな問題を、客観的なルールに則って公平に解決するための知恵と仕組みが備わっています。
今回の記事では、遺産分割でよくある「困った!」というケースを取り上げ、法律の専門家である弁護士がどのように問題を解決していくのか、具体的な事例を交えながら、分かりやすく解説してまいります。もし今、あなたが遺産分割の暗いトンネルの中にいると感じているなら、この記事が希望の光を見つける一助となれば幸いです。
【ケース1】相続人が多すぎる!連絡も取れない!どうすれば?

遺産分割の話し合いである「遺産分割協議」は、相続人全員の参加と合意がなければ成立しません。一人でも欠けていれば、その協議は法的に無効になってしまいます。しかし、時には相続人が多数にのぼり、話し合いのテーブルに着くことすら困難な場合があります。
複雑化する相続関係
例えば、祖父が亡くなった際の遺産分割が終わらないうちに、相続人である父が亡くなってしまうと、父の相続人(母や子)が、祖父の遺産分割協議にも参加しなければならなくなります(これを二次相続といいます)。相続が何度も重なると、権利関係はネズミ算式に増え、誰が相続人なのかを把握するだけでも一苦労です。
お子さんがいらっしゃらないご夫婦の一方(例えば夫)が亡くなった場合、相続人は妻だけでなく、夫の兄弟姉妹も含まれます。もし、その兄弟姉妹の中にすでに亡くなっている方がいれば、そのお子さん(故人から見て甥や姪)が代わりに相続人となります(これを代襲相続といいます)。
何十年も会っていない、あるいは全く面識のない親戚と、いきなり財産の分け方を話し合わなければならないのですから、その難しさは想像に難くありません。
連絡が取れない相続人がいる場合の対処法
さらに困難なのが、相続人の中に行方不明の方や海外に移住して連絡先が分からない方がいるケースです。
ご自身で探そうにも限界があります。しかし、法律にはこのような事態に対応するための制度があります。
・不在者財産管理人: 行方不明の相続人がいる場合、家庭裁判所に申し立てることで、その行方不明者の財産を管理する「不在者財産管理人」を選任してもらうことができます。この不在者財産管理人が行方不明者に代わって遺産分割協議に参加することで、協議を進めることが可能になります。
出典: 遺産分割Q&A>1. 相続人>Q2 共同相続人の中に,行方不明者がいる場合はどうすれば良いですか?(裁判所)
・公示送達: 裁判手続き(後述する調停や審判)において、相手方の住所がどうしても分からない場合に、裁判所の掲示板に書類を掲示することなどで、法的に「送達された(相手に届いた)」とみなす手続きです。これにより、相手方が現れなくても手続きを進めることができます。
弁護士に依頼するメリット
私たちは、戸籍や住民票の附票などを辿り、粘り強く相続人の所在調査を行います。その上で、連絡が取れない相続人がいる場合には、不在者財産管理人の選任申立てといった法的な手続きを代理人として進めます。会ったことのない親戚との間にも、弁護士が中立的な立場で入ることで、感情的な対立を避け、冷静な話し合いの場を設定することが可能です。
【ケース2】財産の価値、意見がバラバラ!どうやって決める?

遺産分割で揉める大きな原因の一つが、「財産の評価」です。特に、預貯金のように金額が明確なものと違い、不動産や株式、美術品などは、その価値をいくらと見るかで相続人間の意見が対立しがちです。
「兄は、自分がこの家をもらうから、固定資産税評価額で計算すると言う。でも、実際に売ったらもっと高く売れるはずだ!不公平だ!」
不動産の評価額には、相続税申告で使う「路線価」、固定資産税の基準となる「固定資産税評価額」、そして実際に市場で取引される価格である「時価(実勢価格)」など、複数の指標があります。どの指標を使うかで、各相続人が受け取る金額が大きく変わるため、争いの火種になりやすいのです。
故人が経営していた会社の株式は、上場していないため客観的な市場価格がありません。会社の経営を引き継ぐ相続人は「会社は負債も多くて大変だから、株の価値はゼロに近い」と主張し、会社に関わっていない相続人は「純資産はたくさんあるのだから、もっと価値があるはずだ」と主張するなど、立場によって見方が全く異なります。
故人が大切にしていた絵画や壺。「これは高価なものだ」と聞いていたけれど、本当の価値は誰にも分からない…。このようなケースも少なくありません。
解決策は、客観的な「専門家の鑑定」です
このような対立を解決する唯一の方法は、第三者である専門家による客観的な鑑定評価です。
鑑定費用は決して安くはありませんが、相続人間で何年も争い、最終的に裁判になって弁護士費用が膨らむことを考えれば、結果的に安く、そして早く解決できる最善の方法と言える場合が多いです。
弁護士に依頼するメリット
私たちは、各分野の信頼できる専門家(不動産鑑定士、税理士、美術品鑑定士など)と緊密に連携しています。どの専門家に依頼すべきかを見極め、鑑定手続きをスムーズに進めます。そして、その客観的な評価額を基に、全ての相続人が納得できる分割案を作成し、交渉をまとめる「調整役」としての役割を果たします。
【ケース3】どうしても話し合いがつかない!最終手段は?

当事者同士での話し合い(遺産分割協議)が、どうしてもまとまらない。感情的な対立が深まり、もはや冷静な会話ができない…。そんな場合は、家庭裁判所を利用した法的な手続きに移行することになります。
ステップ1:遺産分割調停
いきなり裁判で白黒つけるのではなく、まずは「調停」という話し合いの場が設けられます。調停では、裁判官と、一般市民から選ばれた中立的な「調停委員」が間に入り、双方の言い分をじっくりと聞きながら、合意に向けた助言やあっせんを行います。第三者が入ることで、当事者同士ではできなかった冷静な話し合いが可能になり、お互いが譲歩できる落としどころを見つけやすくなります。
出典: 遺産分割調停(裁判所)
ステップ2:遺産分割審判
調停でも合意に至らなかった場合、手続きは自動的に「審判」に移行します。審判では、裁判官が、これまでの経緯や双方の主張、提出された資料など、一切の事情を考慮して、最終的に「このように遺産を分割しなさい」という決定を下します。これは判決と同じ効力を持ち、法的な強制力を伴います。
弁護士に依頼するメリット
調停や審判の場では、単に「納得いかない」という感情をぶつけるだけでは、自分の望む結果は得られません。自分の主張が、法律上いかに正当なものであるかを、証拠に基づいて論理的に説明する必要があります。
私たちは、皆様の「代理人」として、法廷に立ちます。皆様の想いを法的な主張に整理し直し、有利な証拠を収集・整理して提出し、相手方の主張の矛盾点を指摘するなど、専門家としての技術を駆使して、皆様の正当な権利を守るために戦います。
【ケース4】「あの人だけズルい!」不公平感を解消する法律のルール
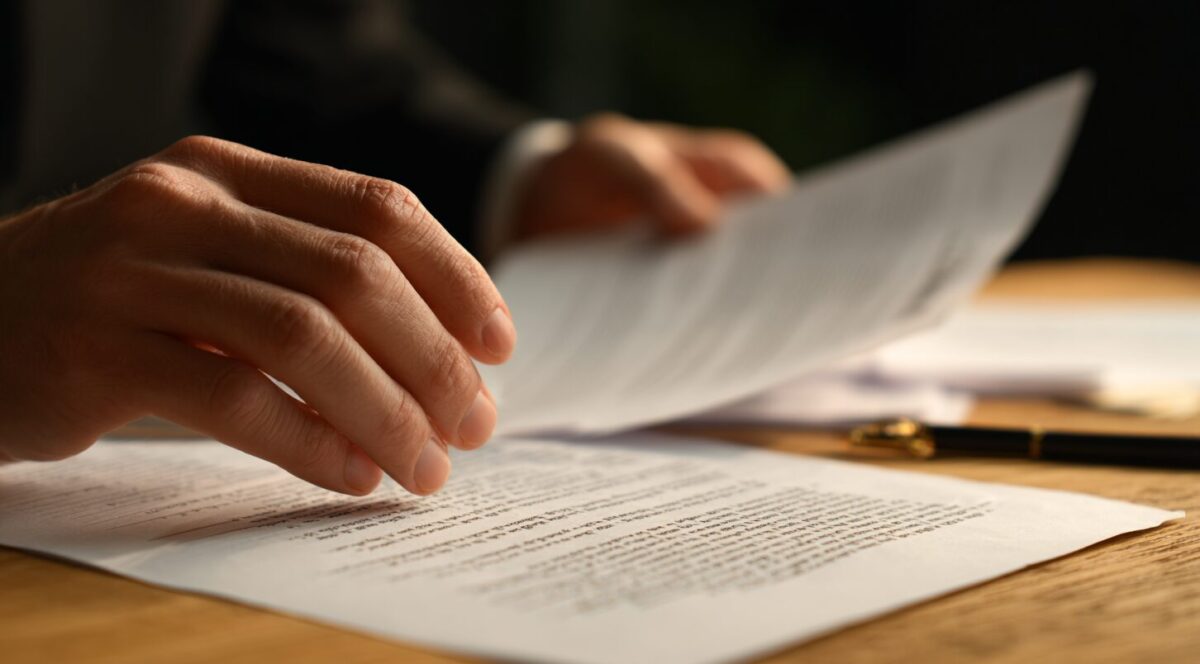
法定相続分通りに分けるのが基本ですが、それではかえって不公平になってしまうケースがあります。法律はそうした不公平感を調整するための、「特別受益」と「寄与分」という二つの重要な制度を設けています。
「あの人だけ生前にもらっていた」→ 特別受益
「兄は大学の費用だけでなく、結婚するときに家を買う頭金まで親に出してもらっていた。それなのに、相続分が同じなのは不公平だ!」
このように、一部の相続人だけが、故人から生前に特別な利益(住宅資金、事業資金、高額な学費など)を受けていた場合、その利益を「特別受益」として扱います。具体的には、その生前贈与の額を、一旦相続財産に足し戻した上で(これを「みなし相続財産」といいます)、各人の相続分を計算し、特別受益を受けた人は、自分の相続分からその額を差し引く、という形で調整します。これにより、実質的な公平を図ることができます。
出典: No.4161 相続財産に加算される贈与財産(国税庁) (※税法上の考え方ですが、民法上の特別受益の概念を理解する参考になります)
「私がずっと親の面倒を見てきた」→ 寄与分
「私が仕事を辞めて、10年間寝たきりの母の介護を続けてきた。だからこそ、父の財産が減らずに済んだはず。他の兄弟と同じ分け方では到底納得できない」
このように、特定の相続人が、故人の財産の維持または増加について、通常期待される程度を超える特別な貢献をした場合に、その貢献度を金銭的に評価し、相続財産からその分を先に取得できる制度が「寄与分」です。介護や看護、家業への無給での従事などが典型例です。
ただし、寄与分が認められるためのハードルは決して低くありません。「親族として当たり前の範囲」を超えた「特別な」貢献であったことを、日記や領収書、第三者の証言といった客観的な証拠で証明する必要があります。
弁護士に依頼するメリット
「特別受益」や「寄与分」の主張は、遺産分割の中でも最も感情的な対立を生みやすい論点です。私たちは、皆様から丁寧にお話をお伺いし、それが法的に「特別受益」や「寄与分」として主張できるものなのかを的確に判断します。そして、その主張を裏付けるための証拠集めをサポートし、相手方や裁判所に対して、説得力のある形で主張を構成します。感情論に陥りがちな議論を、法的な土俵での冷静な交渉へと導くのが、私たちの役割です。
まとめ:諦める前に、あなたの想いを専門家にお聞かせください

遺産分割は、ご家族にとって非常に辛く、エネルギーのいる作業です。対立が長引けば、これまで築いてきた家族の絆に、取り返しのつかない亀裂が入ってしまうことさえあります。
しかし、どうか諦めないでください。
こじれてしまった糸も、専門家が介入し、法律という客観的なものさしを当てることで、一つひとつ丁寧に解きほぐしていくことが可能です。弁護士は、あなたの権利を守る法律の専門家であると同時に、複雑な人間関係を調整する「交渉のプロフェッショナル」でもあります。
「もう当事者同士では話にならない」
「自分のこの気持ちは、法的に主張できるのだろうか」
そう感じたら、それは専門家に相談するタイミングです。問題が深刻化し、お互いの不信感が頂点に達してしまう前に、ぜひ一度、私たちにご相談ください。
蒼生法律事務所では、相続に関する初回のご相談を無料で承っております。まずは、あなたの胸の内にある想い、お悩み、そして不安を、ありのままにお聞かせください。私たちが、必ずや解決への道筋を見つけ出します。
ご家族が、再び笑顔で向き合える未来のために。
あなたからの一歩を、心よりお待ちしております。

2004年の弁護士登録以降、個人・法人問わず幅広い事件を担当し、クライアントにとっての重大事には誠実かつ丁寧に寄り添う。命運に配慮し、最善策を模索。豊富な実績と十分なコミュニケーションで、敷居の高さを感じさせない弁護士像を追求してきた。1978年大阪府出身、京都大学法学部卒業。2011年に独立。不動産・労務・商事・民事・破産・家事など多様な分野を扱い、2024年6月に蒼生法律事務所へ合流。相続・遺言