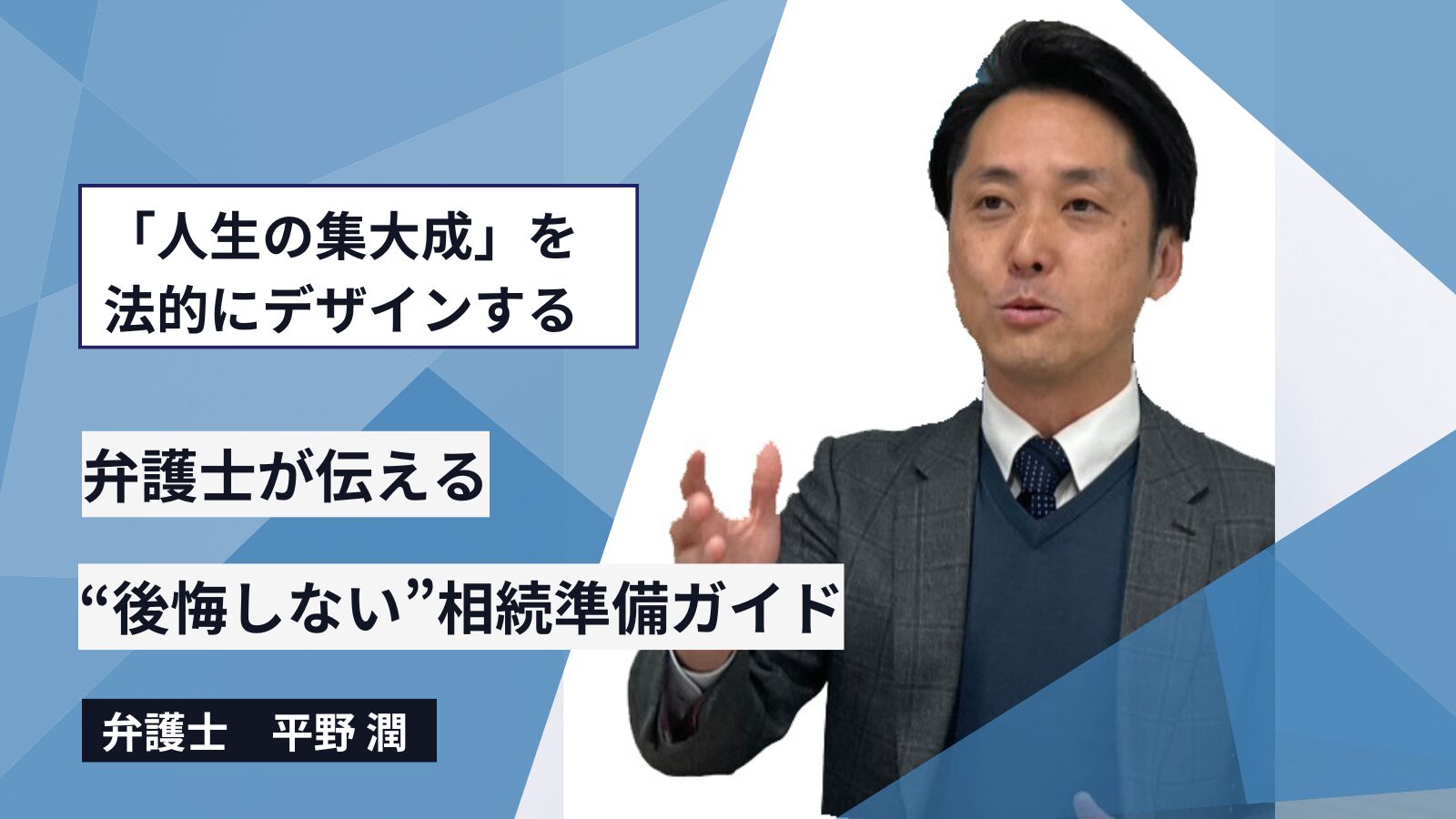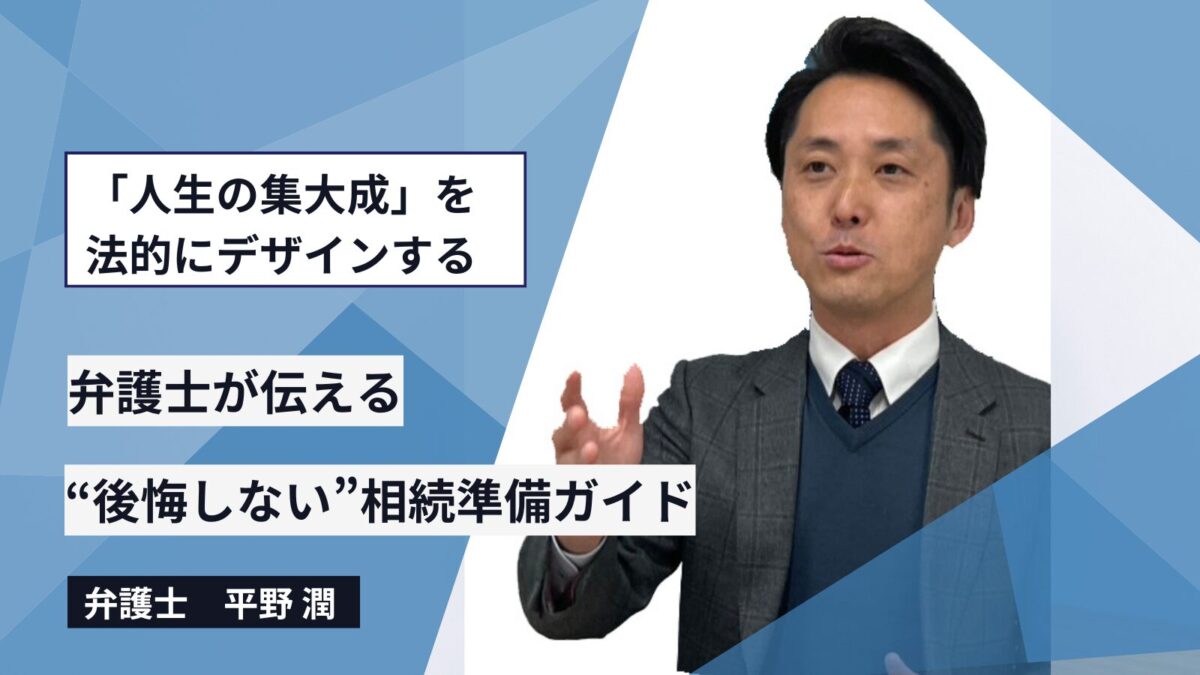
皆様、こんにちは。
蒼生(そうせい)法律事務所、代表弁護士の平野 潤(ひらの じゅん)です。
この度は、当事務所のブログに足をお運びいただき、誠にありがとうございます。
「人生100年時代」と言われる現代、私たちはかつてないほど長い時間を生きるようになりました。それは素晴らしいことであると同時に、私たちに新たな課題を投げかけています。それは、「元気なうちに、自分の人生の終い方をどうデザインし、愛する家族に何を残せるか」という、深く、そして大切な問いです。最近では「終活」という言われ方もしますが、相続について考えておく必要があります(相続対策)。
「相続対策」と聞くと、多くの方は「節税」や「財産の分け方」といった、お金にまつわるテクニックを想像されるかもしれません。しかし、私たちが考える相続対策は、それだけではありません。
それは、あなたの人生の哲学や愛情を、法的に確実な形に翻訳し、未来の家族を無用な争いや困難から守り抜くための、壮大で、そして愛情に満ちた「人生設計」そのものなのです。
その設計を実現するため、法律は私たちに様々な「道具」を用意してくれています。「遺言書」はもちろん、「家族信託」「生前贈与」「後見制度」…。この記事は、いわばあなたの想いを実現するための「最高の道具箱」です。
今回は、相続が発生する「前」だからこそできる、究極の対策について、網羅的に、そして分かりやすく解説してまいります。あなたの人生の集大成を、最高の形で未来へ繋ぐための一助となれば幸いです。
第1章:全ての基本となる設計図「遺言書」

生前対策を考える上で、全ての基本となり、土台となるのが「遺言書」です。遺言書がないばかりに、仲の良かった家族が財産を巡って憎しみ合う「争族」に発展するケースを、私たちは嫌というほど見てきました。
遺言書は、あなたの意思を明確に示すことで、残された家族が迷わないようにするための「道しるべ」です。特に、
という選択肢があることは、ぜひ覚えておいてください。
しかし、遺言書は万能ではありません。例えば、「私が死んだ後、財産は妻に。その妻が死んだら、長男に」といった、数世代にわたる願いを叶えることはできません。また、認知症になってからでは、有効な遺言書を作成することは困難です。
そこで登場するのが、遺言書を補完し、さらに高度な想いを実現するための、他の「道具」たちなのです。
第2章:遺言書を超える魔法の道具「家族信託」

近年、富裕層や事業オーナーの方々から絶大な注目を集めているのが「家族信託」という制度です。これは、あなたの財産管理を、元気なうちから信頼できるご家族に託す、オーダーメイドの契約です。
家族信託の仕組み
登場人物は3人です。
ポイントは、財産の「名義」だけを受託者に移し、管理・運用を任せるという点です。これにより、遺言書では実現できない、様々なメリットが生まれます。
メリット1:認知症による「資産凍結」を防ぐ
最大のメリットが、認知症対策です。
もしあなたが認知症になり、判断能力が低下すると、たとえあなた名義の預金であっても、家族はそれを引き出すことができません。不動産を売却したり、アパート経営の修繕契約を結んだりすることもできなくなります。これが「資産凍結」の恐怖です。
しかし、元気なうちに家族信託契約を結んでおけば、万が一あなたが認知症になっても、受託者であるご家族が、契約内容に従って、引き続き財産の管理や活用をスムーズに行うことができます。これにより、高額な介護費用や施設入所費用の支払いにも、滞りなく対応できるのです。
メリット2:二次相続、三次相続…世代を超えた想いを実現

家族信託であれば、遺言書では指定できない「次の次の相続」まで、あなたの意思を反映させることができます。
例えば、「私が死んだら、まずは妻に利益を。妻が死んだら、長男に。長男が死んだら、障害のある孫の生活のために使う」といった、何世代にもわたる財産承継のストーリーを設計することが可能です。これは特に、事業承継や、障害を持つお子様(福祉型信託)の将来に備えたい方にとって、非常に有効な手段となります。
第3章:未来への贈り物「生前贈与」と相続税対策

相続税は、財産が多ければ多いほど、高い税率が課せられます。そこで有効になるのが、元気なうちに財産を少しずつ次世代に移転していく「生前贈与」です。
2つの贈与制度と最新の税制改正
生前贈与には、主に2つの制度があります。
ここで注意が必要なのが、近年の税制改正です。
これまで、亡くなる前3年以内の生前贈与は相続財産に加算されていましたが、この期間が段階的に7年に延長されることになりました。また、2024年からは、相続時精算課税制度にも年間110万円の基礎控除が創設され、使い勝手が向上しています。
これらの制度をどう使い分けるか、最新の税制をどう活用するかは、まさに専門家の腕の見せ所です。安易な判断は、かえって納税額を増やしてしまう危険性もあります。私たちは、相続に強い税理士と緊密に連携し、皆様にとって最適なタックスプランニングをご提案します。
第4章:あなたの尊厳を守る最後の砦「後見制度」

認知症などで判断能力が不十分になった方を、法的に保護し、支援するための制度が「成年後見制度」です。これには、大きく分けて2つの種類があります。
法定後見では、必ずしもあなたの望むご家族が後見人に選ばれるとは限らず、弁護士や司法書士などの専門家が選任されることも少なくありません。
一方、任意後見であれば、あなたの意思で、信頼するご家族に、あなたの財産管理や身上監護(介護や医療に関する契約など)を託すことができます。自分の人生の舵を、最後まで自分の意思で握り続けるための、非常に重要な備えと言えるでしょう。
出典: 任意後見契約(日本公証人連合会)
第5章:家族に迷惑をかけない美学「死後事務委任契約」

遺言書や信託が主に財産のことを定めるのに対し、あなたが亡くなった「直後」の、細々とした事務手続きを託すのが「死後事務委任契約」です。
これらの手続きは、残された家族にとって、精神的にも時間的にも大きな負担となります。特におひとりさまの方や、ご家族が遠方に住んでいる方、家族に迷惑をかけたくないと考えている方にとって、生前に信頼できる人にこれらの事務を託しておくこの契約は、まさに「立つ鳥跡を濁さず」の美学を実践するものと言えるでしょう。
まとめ:あなたの人生の集大成を、最高の形でデザインしましょう

ここまで、生前にできる様々な相続対策についてお話ししてきました。
これらの「道具」は、一つひとつが非常に強力ですが、その真価は、あなたの人生観やご家族の状況に合わせて、オーダーメイドで組み合わせることで発揮されます。
それは、まるで複雑なパズルのようです。どのピースを、どこに、どうやってはめるのか。その設計図を描き、法的に有効かつ、誰もが納得できる形で完成させるのが、私たち法律の専門家の役割です。
「そろそろ真剣に考えないとな…」
そう思い立った「今」が、対策を始める最高のタイミングです。先延ばしにすればするほど、選択肢は狭まっていきます。
私たち蒼生法律事務所は、単に法律手続きを代行するだけではありません。あなたの人生の物語に耳を傾け、あなたの想いに寄り添い、それを未来へ繋ぐための「人生の設計士」です。
あなたの人生の集大成を、最高の形で未来に残すお手伝いをさせてください。
まずはお気軽に、あなたの想いや夢、そしてご不安をお聞かせください。ご連絡を心よりお待ちしております。

2004年の弁護士登録以降、個人・法人問わず幅広い事件を担当し、クライアントにとっての重大事には誠実かつ丁寧に寄り添う。命運に配慮し、最善策を模索。豊富な実績と十分なコミュニケーションで、敷居の高さを感じさせない弁護士像を追求してきた。1978年大阪府出身、京都大学法学部卒業。2011年に独立。不動産・労務・商事・民事・破産・家事など多様な分野を扱い、2024年6月に蒼生法律事務所へ合流。相続・遺言