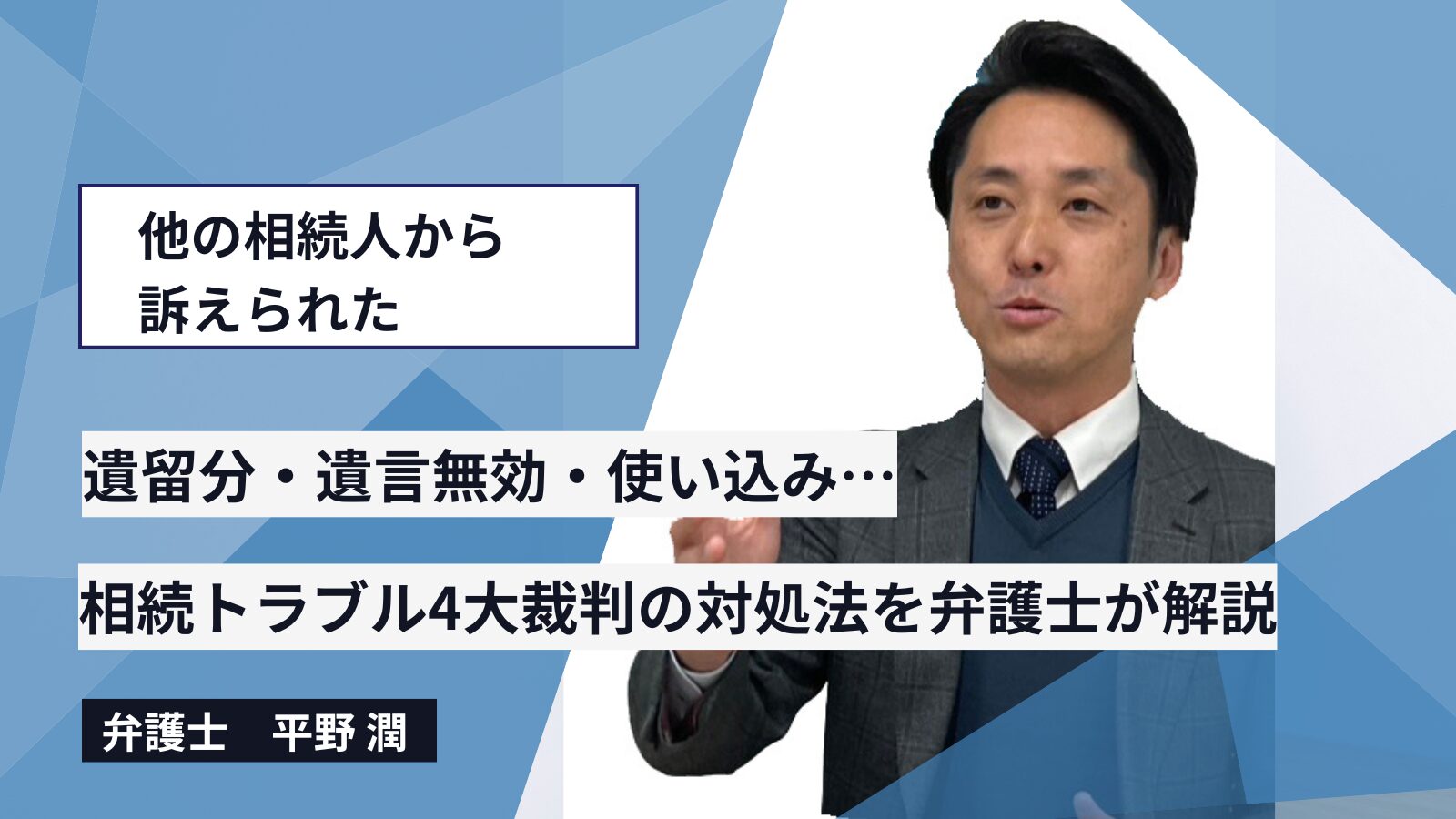
「ある日突然、自宅の郵便受けに、裁判所から分厚い封筒が届いた…」
「『遺産分割調停申立書』『訴状』…見慣れない、そしてあまりにも重い言葉の響きに、血の気が引くような思いをされたのではないでしょうか」
「まさか、自分の家族が、自分の兄弟が、私を訴えるなんて…」
「これから一体どうなってしまうのか、夜も眠れない…」
もし今、あなたがそんな筆舌に尽くしがたいショックと不安の渦中にいらっしゃるのだとしたら、どうか一人で抱え込まないでください。裁判所からの通知は、決して「人生の終わり」を告げるものではありません。それは、泥沼化した感情的な対立を、法律という客観的なルールに基づいて最終的に解決するための「スタートの合図」なのです。
今回の記事では、相続を巡って他の相続人から訴えられてしまった場合に、あなたが受け取った「通知」の種類ごとに、その意味と、これからあなたが何をすべきかを具体的に解説していきます。この記事が、暗闇の中で一筋の光を見出すための、そして、あなたの正当な権利を守るための「反撃の狼煙」となることを願っています。
大原則:裁判所からの通知は「絶対に無視しない」こと!
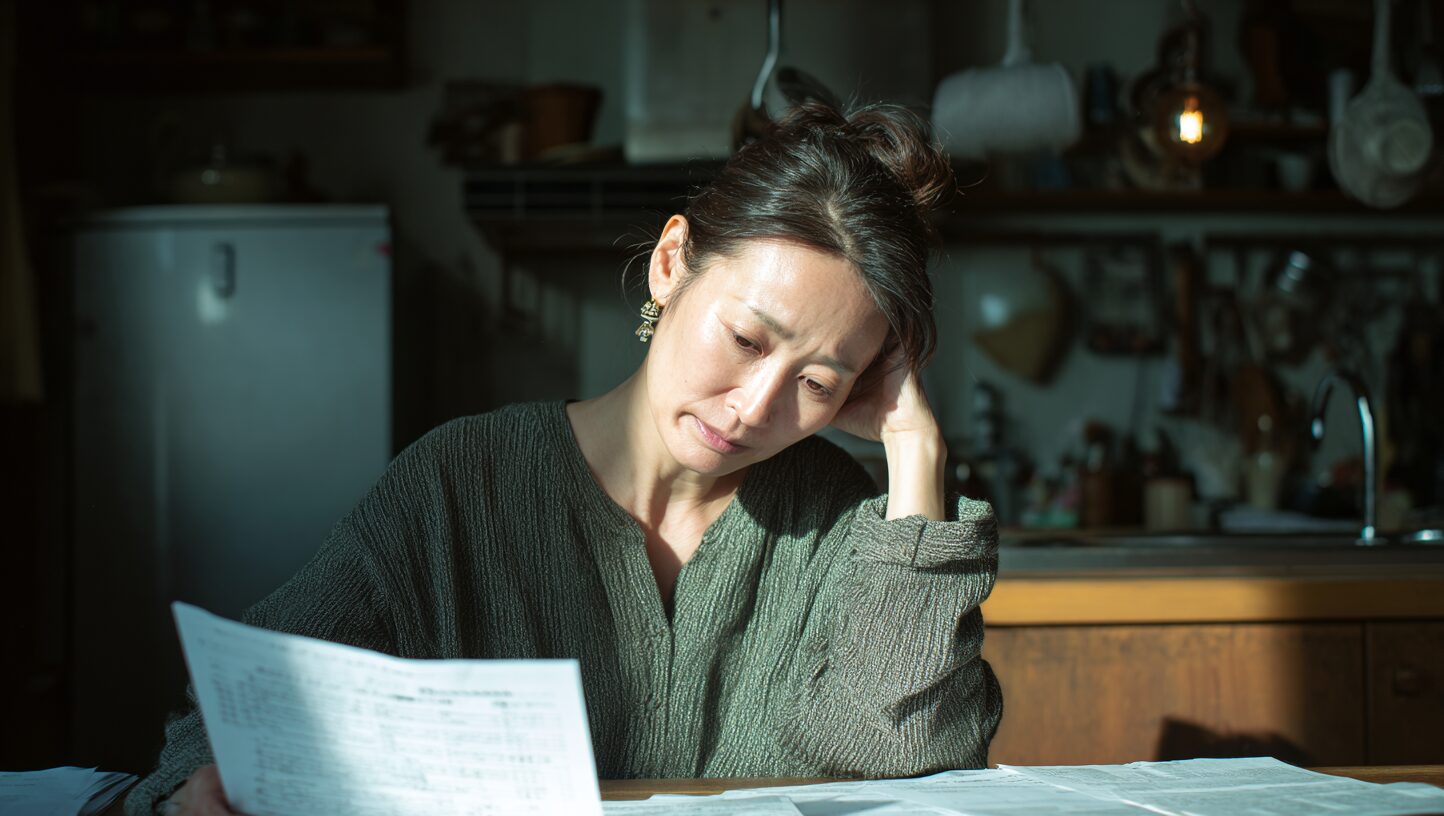
まず、何よりも先にお伝えしなければならない、たった一つの、そして最も重要な大原則があります。それは、「裁判所からの通知は、絶対に無視してはならない」ということです。
「見なかったことにしたい」「関わりたくない」というお気持ちは痛いほど分かります。しかし、通知を無視して、指定された期日に裁判所に出頭しなかったり、答弁書などの書類を提出しなかったりした場合、法律はあなたに最大の不利益を与えます。
それは、「相手方の主張をすべて認めた」とみなされ、相手の言い分通りの判決(欠席判決)が下されてしまう、というものです。一度この判決が出てしまうと、後から覆すことは極めて困難です。あなたは、反論する機会を永遠に失ってしまうのです。
ですから、まずは深呼吸をしてください。そして、その分厚い封筒を勇気をもって開封し、「誰が」「誰を」「何を求めて」訴えているのか、そして何より「いつまでに行動しなければならないのか(期日・期限)」を確認してください。そして、できるだけ早く、私たちのような専門家にご相談ください。
【ケース別】あなたが訴えられた「裁判」の種類と賢い対処法

裁判所から届く書類には、様々な種類があります。それぞれ意味合いも、対処法も異なります。代表的なケースを見ていきましょう。
ケース1:「遺産分割調停の申立書」が届いた場合
これは、相続人間の話し合い(遺産分割協議)が決裂したため、家庭裁判所の「調停委員」という中立的な第三者を交えて、改めて話し合いましょう、という手続きの呼び出し状です。まだ「訴訟」や「審判」という対決の場ではなく、あくまで「話し合い」の延長です。過度に恐れる必要はありません。
しかし、単なる世間話の場ではないことも事実です。調停の場で、あなたは自分の正当な取り分を主張しなければなりません。
「私は、親の介護に尽くしてきたのだから、その分多く財産をもらう権利(寄与分)があるはずだ」
「兄は、生前に親から住宅資金の援助(特別受益)を受けているのだから、その分、相続財産は少なくなるべきだ」
「弟が主張する、父の土地の評価額は不当に低い。専門家にきちんと査定してもらうべきだ」
これらの主張は、感情的に訴えるだけでは意味がありません。調停の段階から、客観的な証拠(介護記録、送金履歴、不動産鑑定書など)を準備し、法的な根拠に基づいて冷静に主張することが、有利な結果に繋がります。ここで合意できなければ、自動的に「審判」という、裁判官が最終的な分け方を決定する手続きに移行してしまいます。
ケース2:「遺留分侵害額請求の通知(調停申立書)」が届いた場合

「故人の遺言書によって、私が多くの財産を受け取ることになった」という場合に、他の相続人から「法律で保障された最低限の取り分(遺留分)を侵害されたので、その分のお金を払え!」と請求されるのがこれです。
遺言書があるからと安心はできません。遺留分は、遺言よりも優先されうる強力な権利です。
遺留分侵害額請求を行うには、原則として、すぐに訴訟提起するのではなく、まずは家庭裁判所に調停を申立てる必要があります。これを「調停前置主義」といいます。
調停で協議がまとまらず、合意に至る見込みがないと判断された場合は、「調停不成立」となり、調停は終了します。ただ、相手方が納得しなければ、今度は「訴訟」を提起されることになるでしょう。
他の相続人から遺留分侵害額請求を受けた場合、あなたは以下のような反論を検討することになります。
- 相手の計算は正しいか?:遺産の評価額は妥当か?(例えば、相手は不動産を高く評価しすぎているのではないか)。相手が主張する生前贈与は、本当に遺留分の計算に含めるべきものか?
- こちらの権利を主張する:こちらも、故人への貢献(寄与分)があれば、それを主張して支払うべき金額を減額できる可能性があります。
- 支払い能力の問題:遺産が不動産ばかりで、すぐに支払う現金がない場合、分割払いや、不動産の売却を待ってもらうなどの交渉も必要になります。
遺留分の請求は、最終的には金銭の支払いに行き着きます。いかにして支払う金額を正当な範囲に抑えるか、そして支払い方法をどう交渉するかが、弁護士の腕の見せ所となります。
出典: 遺留分侵害額の請求調停(裁判所)
ケース3:「遺言無効確認請求の訴状」が届いた場合
これは、遺言によって財産を受け取ったあなたに対して、「あの遺言書は、父が認知症で正常な判断ができない時に書かれたものだから無効だ!」と、遺言の効力そのものを根本から争ってくる訴訟です。
もし遺言が無効になれば、あなたは遺言によって得られるはずだった財産を失い、法定相続に戻ってしまいます。まさに、天国と地獄です。
この訴訟の最大の争点は、故人が遺言を作成した当時に「遺言能力」(遺言の内容を理解し、その結果を認識できる能力)があったかどうか、の一点に尽きます。あなた(訴えられた側)は、「故人には、遺言能力が確かにあった」ことを証明しなければなりません。
- 公正証書遺言の場合:作成に立ち会った公証人や証人の証言が、極めて強力な証拠となります。
- 自筆証書遺言の場合:遺言作成当時の医療記録(カルテ)、介護記録、故人の日記や手紙、周囲の人々の証言などをかき集め、「遺言を書ける状態にあった」ことを立証していく必要があります。
「認知症だった=即、無効」という単純な話ではありません。医学的な知見も踏まえた、高度で専門的な主張・立証活動が求められます。
ケース4:「不当利得返還請求(使い込み)」の訴状が届いた場合
故人の生前、その預貯金を管理していた方が、他の相続人から「あなたは、親の預金を自分のために勝手に使い込んだだろう!その分を遺産に戻せ!」と訴えられるケースです。近年、非常に増えているトラブルです。
良かれと思って親の生活費や医療費を立て替えて引き出していた場合でも、他の相続人から見れば、それは「使途不明金」であり、「使い込み」に見えてしまうのです。
この場合、あなたは預金の出金履歴について、「いつ、いくら、何のために引き出したのか」を、領収書などの客観的な証拠に基づいて、一つひとつ丁寧に説明していく責任があります。「親に頼まれてやったことだ」というだけでは、裁判所は認めてくれない可能性があります。
「争族」という嵐を乗り切るための、たった一つの方法

ここまで、様々な調停や訴訟のケースを見てきました。いずれのケースにも共通しているのは、「もはや感情論では解決しない」ということです。法廷は、あなたの悔しさや悲しさを聞いてくれる場所ではありません。そこは、「法的な主張」と「客観的な証拠」だけがものを言う、冷静な戦いの場なのです。
では、この厳しい戦いを、どうすれば乗り切れるのか。
答えは一つです。相続トラブルの専門家である弁護士を、あなたの「パートナー」として選ぶことです。
弁護士にご依頼いただくことには、3つの大きなメリットがあります。
冷静な「分析官」として、あなたに進むべき道を示す
私たちは、あなたの置かれた状況を法的に分析し、「何が有利な点で、何が不利な点か」「どのような証拠が必要か」「最終的な落としどころはどこか」という、戦いの全体像と見通しを、冷静に、そして明確にお示しします。
屈強な「代理人」として、あなたに代わって戦う
あなたご自身が、相手方と直接言葉を交わす必要はもうありません。私たちはあなたの代理人として、交渉の窓口となり、法廷に立ちます。感情的な応酬に巻きされることなく、あなたの正当な権利を、法的なロジックに基づいて主張・立証します。
あなたの「精神的な盾」として、日常を守る
調停や訴訟という非日常的な出来事は、あなたの心身をすり減らし、平穏な日常を奪います。私たちは、そのストレスや不安を肩代わりし、皆様が安心して日常生活を送れるようにするための、精神的な防波堤、そして「盾」となります。
まとめ:その封筒は、反撃の始まりを告げる合図です

裁判所から突然届いた、冷たく、重い封筒。
それは、確かにあなたの平穏を脅かす、ショッキングな出来事です。しかし、見方を変えれば、それは泥沼化した関係を清算し、問題を法的なルールに則って最終的に解決するための、またとない「チャンス」でもあるのです。
この複雑な戦いを、どうか一人で戦おうとしないでください。
どんなに絶望的な状況に見えても、法律の専門家である私たちの目から見れば、必ずや反撃の糸口、そして解決への活路は見いだせます。
その分厚い封筒を握りしめて、まずは私たち蒼生法律事務所の扉を叩いてください。
お話をお伺いし、分厚い書類を紐解いたその瞬間から、あなたの反撃の第一歩が始まります。
蒼生法律事務所は、あなたの正当な権利と平穏な日常を取り戻すため、全力で戦います。
あなたからのご連絡を、心よりお待ちしております。

2004年の弁護士登録以降、個人・法人問わず幅広い事件を担当し、クライアントにとっての重大事には誠実かつ丁寧に寄り添う。命運に配慮し、最善策を模索。豊富な実績と十分なコミュニケーションで、敷居の高さを感じさせない弁護士像を追求してきた。1978年大阪府出身、京都大学法学部卒業。2011年に独立。不動産・労務・商事・民事・破産・家事など多様な分野を扱い、2024年6月に蒼生法律事務所へ合流。相続・遺言




