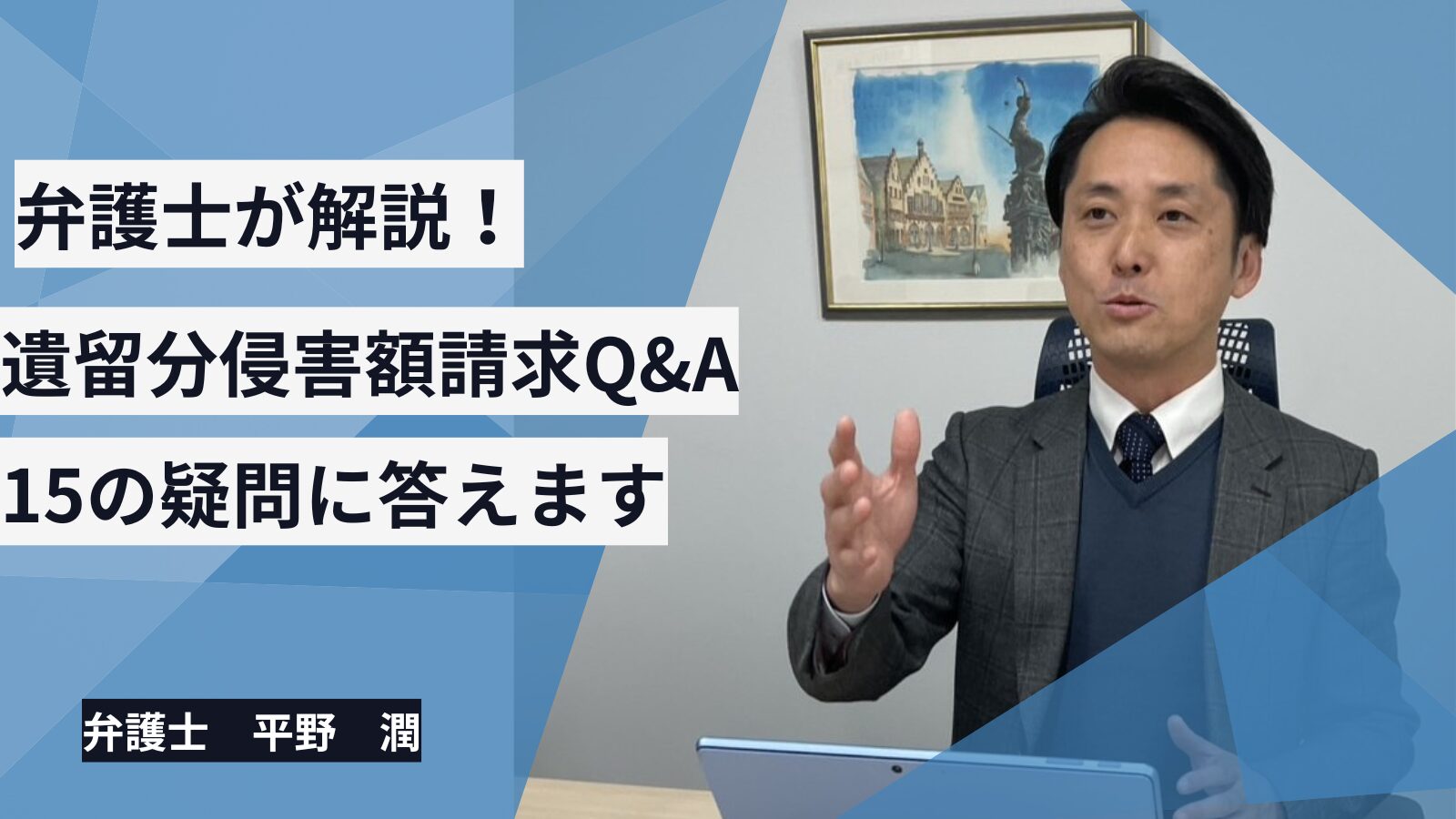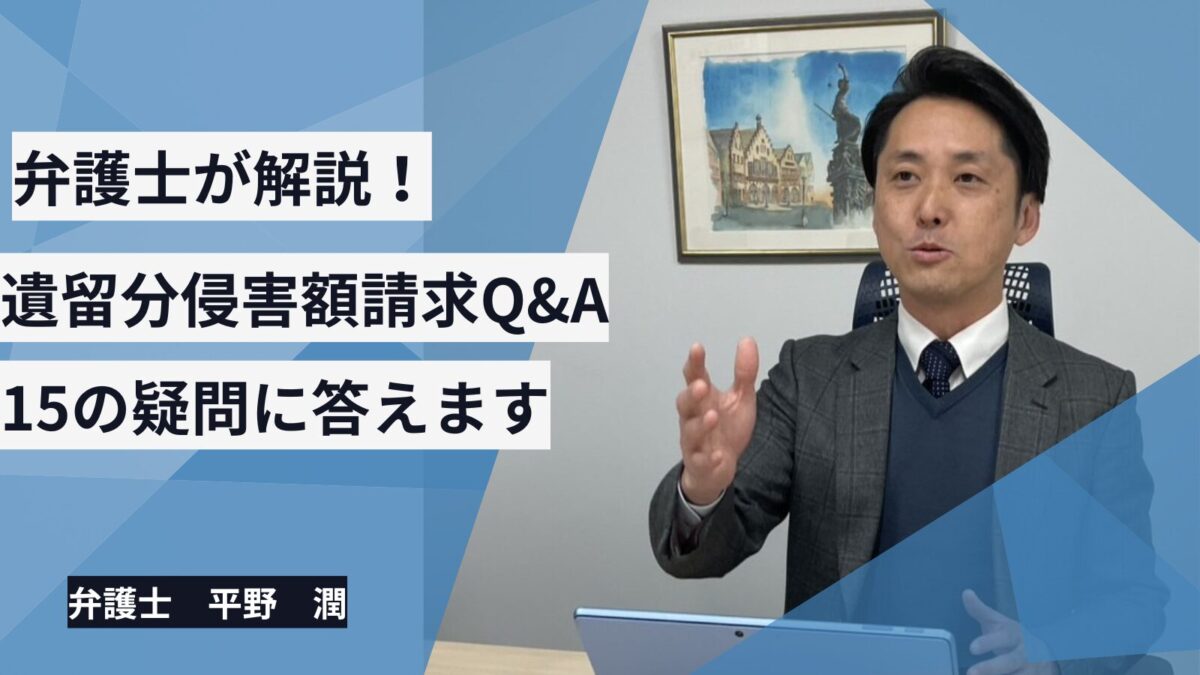
「『愛人に全財産を譲る』という父の遺言書が見つかった…」 「兄だけが事業と財産の全てを相続することになっていて、私には何もない」 「生前に親の財産のほとんどが弟に贈与されていたらしい」
ご自身の相続について、このような理不尽な状況に直面し、途方に暮れている方はいらっしゃらないでしょうか。
「遺言書は絶対だから、もう諦めるしかないのか…」と思われるかもしれませんが、そんなことはありません。法律は、遺された家族の生活を守るため、最低限の遺産の取り分を保障しています。それが**「遺留分(いりゅうぶん)」**という制度です。
今回は、この「遺留分」について、皆様からよく寄せられる質問にQ&A形式で分かりやすくお答えしていきます。ご自身の権利を正しく理解し、納得のいく相続を実現するための一助となれば幸いです。
遺留分Q&A:基本編
遺留分とは、一定の範囲の法定相続人に法律上保障されている、最低限の遺産の取り分のことです。
亡くなった方(被相続人)は、原則として遺言によって自分の財産を誰にどのように遺すか自由に決めることができます(遺言自由の原則)。しかし、その自由を無制限に認めてしまうと、例えば「全財産を愛人に遺す」といった遺言が作成され、残された家族が生活に困ってしまう事態も起こりえます。
そこで法律は、遺された家族の生活保障や、相続人間の公平を図る観点から、この遺言の自由を一部制限し、一定の相続人には最低限の権利を保障しているのです。それが「遺留分」です。
これは非常に重要なポイントです。2019年7月1日の民法改正により、制度が大きく変わりました。
•旧制度:遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)
改正前の制度です。遺留分を侵害された相続人は、遺贈や贈与された財産そのものを取り戻す(現物返還)のが原則でした。例えば、不動産が贈与された場合、その不動産の共有持分を取り戻すことになり、後の管理や売却がかえって複雑になるという問題がありました。
•現行制度:遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう)
現在の制度です。遺留分を侵害された場合、侵害された額に相当する「金銭」の支払いを請求することになりました。これにより、財産そのものではなく金銭で解決することになり、より柔軟で迅速な解決が図れるようになりました。
この記事では、現在の「遺留分侵害額請求」に基づいて解説を進めていきます。
出典:法務省: 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)
遺留分が認められている相続人(遺留分権利者)は、兄弟姉妹を除く法定相続人です。具体的には以下の人々です。
-
配偶者
-
子(子が既に亡くなっている場合は、孫などの代襲相続人)
-
直系尊属(親や祖父母など。子がいない場合に相続人になります)
ポイントは、被相続人の兄弟姉妹には遺留分がないという点です。「全財産を妻に遺す」という遺言があった場合、被相続人の弟や妹は遺留分を請求することができません。
遺留分の割合は、相続人の構成によって決まります。
まず、相続財産全体に対する遺留分の割合(総体的遺留分)は以下の通りです。
-
相続人が直系尊属(親や祖父母)のみの場合:相続財産の3分の1
-
上記以外(配偶者や子が含まれる)の場合:相続財産の2分の1
次に、この総体的遺留分に、各相続人の法定相続分を掛けることで、個別の遺留分が計算できます。
【例】相続人が配偶者と子2人、相続財産が6,000万円の場合
o配偶者:3,000万円 × 1/2 = 1,500万円
o子A:3,000万円 × 1/4 = 750万円
o子B:3,000万円 × 1/4 = 750万円
遺留分Q&A:請求手続き編
自身の遺留分が侵害されている、つまり「遺言や生前贈与によって、自分がもらえるはずの最低限の取り分よりも少ない財産しか受け取れなかった場合」に請求できます。
具体的には、以下のようなケースが典型例です。
-
「長男に全財産を相続させる」という遺言がある
-
「愛人や特定の団体に全財産を遺贈する」と書かれている
-
生前に特定の相続人や第三者に、財産のほとんどが贈与されていた
ここが遺留分請求で最も注意すべき点です。遺留分侵害額請求権には、時効(期間制限)があり、非常に短く設定されています。
この期間を過ぎてしまうと、権利が時効によって消滅し、請求できなくなってしまいます。「知ってから1年」というのはあっという間です。遺留分が侵害されている可能性があると分かったら、すぐに専門家へ相談することをお勧めします。
まずは、相手方(遺贈や贈与を受けた人)に対して、遺留分を侵害されているので金銭を支払ってほしいという意思表示をすることから始まります。
この意思表示は口頭でも可能ですが、「言った・言わない」の争いを防ぎ、時効の進行を止めた証拠を残すために、「内容証明郵便」を送付するのが一般的です。
その後、以下の流れで進むのが通常です。
遺留分Q&A:計算・応用編
遺留分を計算する際の基礎となる財産は、単に亡くなった時に残っていた財産だけではありません。
(相続開始時のプラスの財産)-(債務)+(遺留分計算のための特別な生前贈与)
この「特別な生前贈与」を財産に加算して計算するところが重要なポイントです。
上記質問の「特別な生前贈与」の代表例が「特別受益」です。
【専門用語解説:特別受益(とくべつじゅえき)】
これは、一部の相続人が被相続人から生前に受けた特別な利益のことです。例えば、住宅購入資金の援助、事業資金の提供、高額な学費などが該当します。これは実質的な「遺産の前渡し」と考えられます。
相続人に対する特別受益は、原則として相続開始前10年以内に行われたものが、遺留分計算の基礎財産に加算されます。
はい、なります。相続人以外(愛人、お世話になった人、団体など)への贈与については、原則として相続開始前1年以内に行われたものが遺留分計算の基礎財産に加算されます。
ただし、贈与した側と受け取った側の双方が「この贈与は遺留分権利者の権利を侵害する」と知っていた場合は、1年以上前の贈与であっても対象に含まれます。
被相続人Aには妻Bと子Cがいましたが、「全財産(6,000万円)を愛人Xに遺贈する」という遺言がありました。この場合、遺言に従っては、妻Bと子Cは何ももらえません。しかし、二人は愛人Xに対して遺留分侵害額を請求できます。
-
遺留分の合計額:6,000万円 × 1/2 = 3,000万円
-
妻Bの遺留分:3,000万円 × 1/2(法定相続分)= 1,500万円
-
子Cの遺留分:3,000万円 × 1/2(法定相続分)= 1,500万円
BとCは、それぞれXに対して1,500万円の金銭支払いを請求することができます。
会社経営者のDには、長男Eと次男Fがいました。Dは事業承継のため「会社の株式と関連不動産を含む全財産(1億円)を長男Eに相続させる」という遺言を遺しました。遺言に従っては、次男Fの取り分はゼロです。しかし、次男は長男に対して遺留分侵害額を請求できます。
-
遺留分の合計額:1億円 × 1/2 = 5,000万円
-
次男Fの遺留分:5,000万円 × 1/2(法定相続分)= 2,500万円
次男Fは、長男Eに対して2,500万円の金銭支払いを請求できます。事業承継では、後継者以外の相続人の遺留分に配慮した生前対策が非常に重要になります。
Gには長女Hと次女Iがいました。Gは生前、次女Iの家族に住宅購入資金として3,000万円を贈与(特別受益)していました。Gが亡くなった時、遺産はわずか1,000万円しか残っていませんでした。遺言はなかったため、法定相続分に従うと長女Hは500万円しか相続できません。しかし、長女は次女に対して遺留分侵害額を請求できます。
-
遺留分計算の基礎財産:1,000万円(遺産)+ 3,000万円(特別受益)= 4,000万円
-
遺留分の合計額:4,000万円 × 1/2 = 2,000万円
-
長女Hの遺留分:2,000万円 × 1/2(法定相続分)= 1,000万円
長女Hは本来1,000万円の遺留分がありますが、実際に相続できるのは500万円なので、差額の500万円を遺留分侵害額として次女Iに請求できます。
はい、できます。ただし、手続きが異なります。
-
相続開始前(生前)の放棄:相続人間の不公平や、被相続人からの不当な圧力を防ぐため、家庭裁判所の許可が必要です。単に「遺留分を放棄します」という念書を書いても法的な効力はありません。
-
相続開始後(死後)の放棄:相続が開始した後は、ご自身の自由な意思で放棄することができます。特別な手続きは不要で、相手方にその意思を伝えれば足ります。
遺留分Q&A:弁護士への相談
遺留分侵害額請求は、ご自身で行うことも不可能ではありません。しかし、ここまでお読みいただいて分かる通り、その計算や手続きは非常に複雑で、専門的な知識が不可欠です。弁護士にご依頼いただくことで、以下のような大きなメリットがあります。
まとめ:あなたの正当な権利を諦めないでください
理不尽な遺言や生前贈与によって、ご自身の権利が侵害されていると感じたとき、「どうせ無駄だ」と諦めてしまう必要は全くありません。「遺留分」は、法律があなたに認めた正当な権利です。
しかし、その権利を行使するには、短い時効や複雑な計算、そして感情的な対立といった多くのハードルが存在します。
もし少しでもご自身の相続に疑問や不安を感じたら、まずは私たち専門家にご相談ください。あなたの状況を丁寧にお伺いし、権利を実現するための最善の方法を一緒に考えます。
蒼生法律事務所は、これまで数多くの遺留分に関するご相談を解決に導いてまいりました。
まずは気軽にお問い合わせください。あなたの新たな一歩を、私たちが全力でサポートします。

2004年の弁護士登録以降、個人・法人問わず幅広い事件を担当し、クライアントにとっての重大事には誠実かつ丁寧に寄り添う。命運に配慮し、最善策を模索。豊富な実績と十分なコミュニケーションで、敷居の高さを感じさせない弁護士像を追求してきた。1978年大阪府出身、京都大学法学部卒業。2011年に独立。不動産・労務・商事・民事・破産・家事など多様な分野を扱い、2024年6月に蒼生法律事務所へ合流。相続・遺言