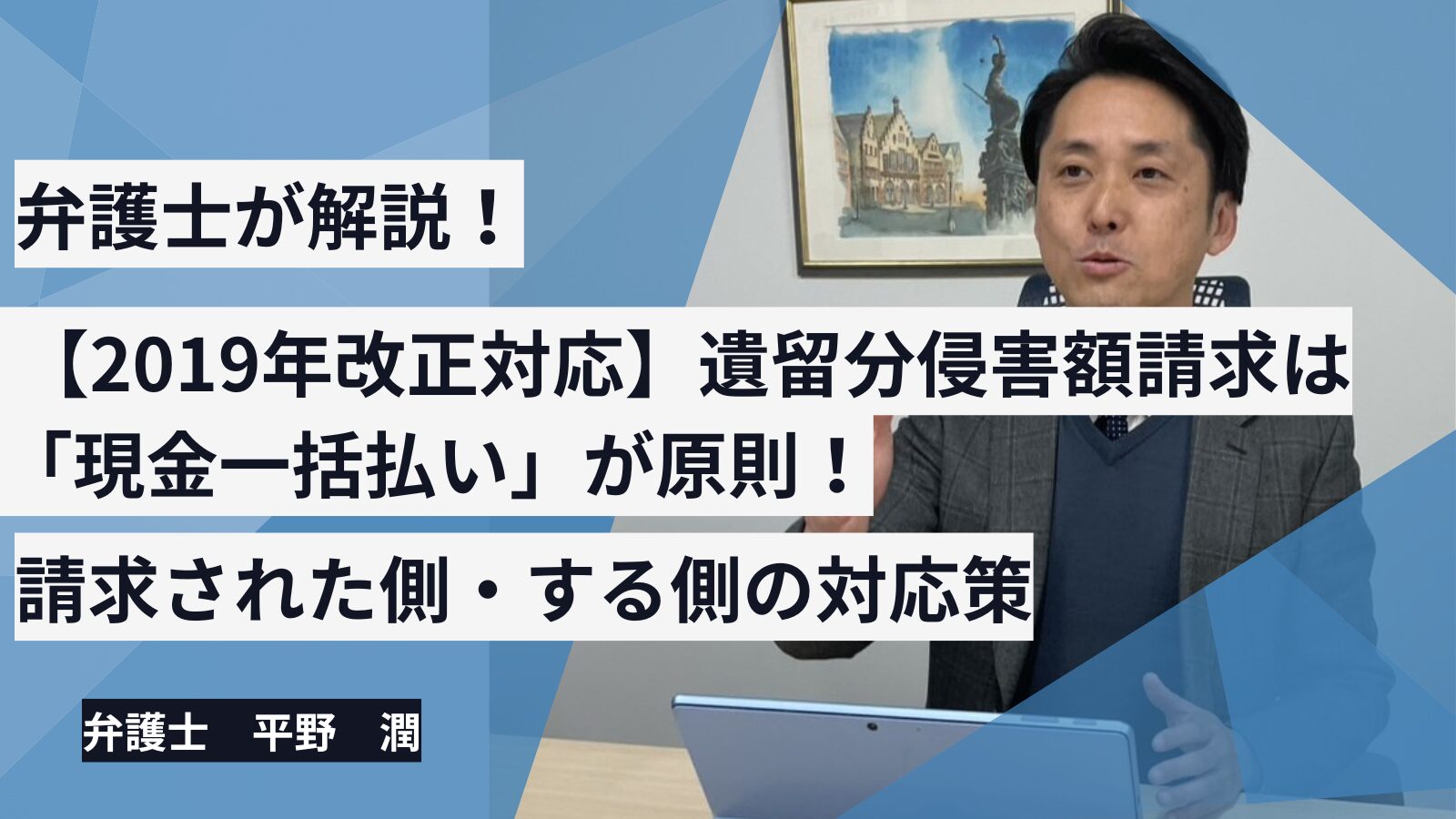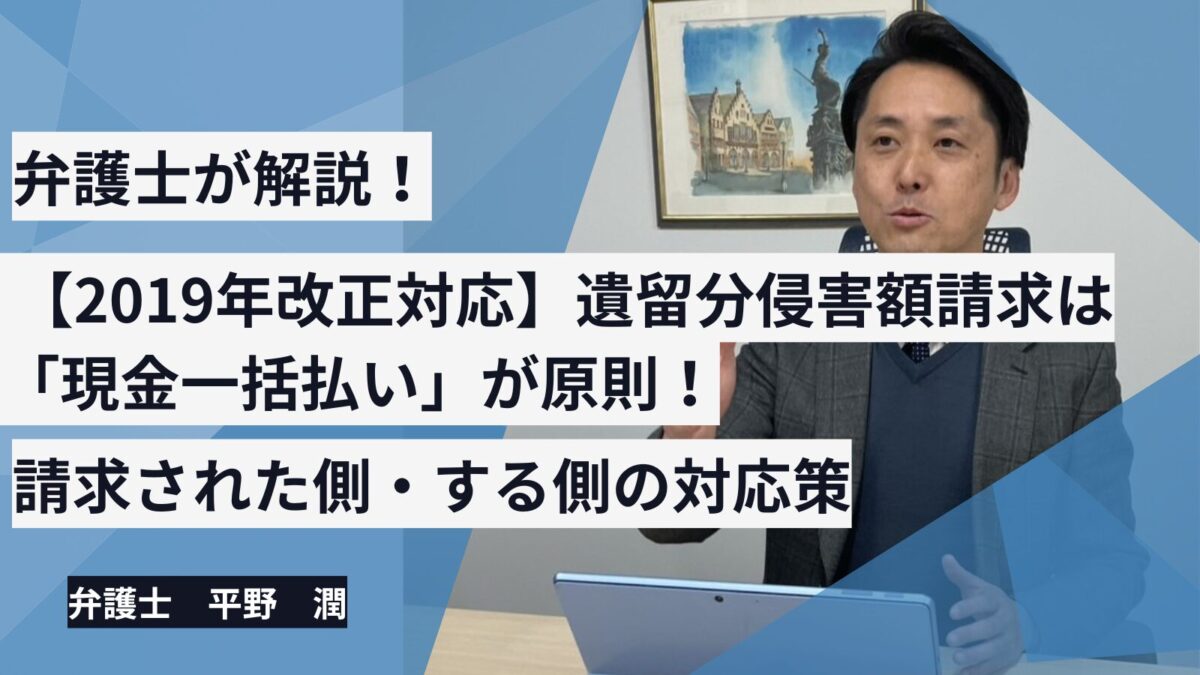
皆さん、こんにちは。 蒼生(そうせい)法律事務所、代表弁護士の平野潤です。
「遺言書を見たら、兄にすべての財産を譲ると書かれていた…」
「父の介護を一身に担ってきたのに、私の取り分が全くないなんて納得できない!」
「亡くなった夫の遺言で、愛人にほとんどの財産が渡ってしまい、今後の生活が不安…」
相続問題に直面する中で、このような理不尽とも思える状況に、悔しさや不安を感じている方はいらっしゃらないでしょうか。
実は、法律はそうした方々のために「遺留分(いりゅうぶん)」という、いわば「相続のセーフティーネット」を用意しています。そして、この遺留分に関するルールが2019年7月の民法改正で大きく変わり、より現実的で使いやすいものになりました。
今回の記事では、この「遺留分」について、特に重要な法改正のポイントから、実際に権利を主張する側・主張された側の具体的な対応策まで、弁護士の視点から分かりやすく解説していきます。
相続トラブルの渦中にいる方も、将来に備えたい方も、ぜひ最後までお付き合いください。
【最重要ポイント】法改正で何が変わった?「モノで返す」から「お金で返す」へ

今回の民法改正で最も大きく変わった点、それは遺留分を侵害されたときの返還方法です。
旧制度の問題点:「遺留分減殺(げんさい)請求」
以前は、遺留分を侵害された場合、「遺留分減殺請求」という権利を行使していました。これは、遺贈や贈与された「財産そのもの」を取り戻す権利です。
例えば、お父様が「長男に全財産である自宅不動産を相続させる」という遺言を残した場合、次男は遺留分として、その不動産の持分(所有権の一部)を取り戻すことになりました。
一見、公平に見えますが、これには大きな問題がありました。
-
不動産が共有状態になる: 兄弟で不動産を共有することになり、売却するにも貸すにも、いちいち相手の同意が必要になり、かえって新たなトラブルの火種になる。
-
事業承継の障害になる: 会社の株式が遺留分の対象になると、後継者以外の兄弟に株式が分散してしまい、会社の経営が不安定になる。
このように、旧制度は問題を解決するどころか、新たな紛争を生み出す原因にもなっていたのです。
新制度のメリット:「遺留分侵害額請求」
そこで、2019年7月1日の改正で、この仕組みが大きく変わりました。新しい制度では、侵害された遺留分を「お金(金銭)」で支払ってもらう権利、その名も「遺留分侵害額請求」に生まれ変わったのです。
先ほどの例で言えば、次男は長男に対して、不動産の持分ではなく「遺留分に相当するお金」を請求することになります。これにより、不動産は長男が単独で所有し続け、次男はお金を受け取る、というスッキリした形で解決できるようになりました。これは、請求する側にとっても、された側にとっても、非常に大きなメリットと言えるでしょう。
【用語解説】
【請求する側のあなたへ】遺留分を取り戻すための具体的なアクションプラン

「自分の遺留分が侵害されている!」と気づいたら、どう行動すればよいのでしょうか。感情的にならず、冷静に、しかし迅速に行動することが重要です。
ステップ1:まずは冷静に話し合い(協議)
いきなり法的な手続きに踏み切るのではなく、まずは財産を多く受け取った相手方と話し合いの場を持つことから始めましょう。
相手方も法律をよく知らず、故人の遺言によって、悪気なく遺留分を侵害してしまっているケースも少なくありません。冷静にこちらの権利を伝えれば、話し合いで円満に解決できる可能性もあります。
ステップ2:【最重要】内容証明郵便で「請求の意思」を伝える
話し合いがまとまらない、あるいは相手が応じない場合は、内容証明郵便で「遺留分侵害額請求書」を送付します。
これは、遺留分を取り戻す上で絶対に欠かせない手続きです。
なぜなら、遺留分侵害額請求には「遺留分を侵害されたことを知った時から1年」という非常に短い時効があるからです(民法1048条)。
この1年という期間は、あっという間に過ぎてしまいます。
内容証明郵便を送ることで、 「いつ、誰が、誰に対して、遺留分を請求する意思表示をしたか」 を郵便局が公的に証明してくれます。
これにより、「言った、言わない」の水掛け論を防ぎ、時効の進行をストップさせることができるのです。
<内容証明郵便の書き方ポイント>
特定の書式はありませんが、以下の点を明確に記載しましょう。
-
いつ亡くなった誰の相続に関するものか。
-
どの遺言書や贈与によって、あなたの遺留分が侵害されているか。
-
民法に基づき、遺留分侵害額を請求する意思があること。
-
(可能であれば)具体的な請求金額。
-
支払い方法や期限についての協議を求める旨。
この段階で具体的な金額が確定していなくても、「請求する」という意思を明確に示すことが何よりも重要です。
ステップ3:家庭裁判所での「調停」
内容証明を送っても相手が支払いに応じない場合、次のステージは家庭裁判所での「遺留分侵害額の請求調停」です。
調停は、裁判官や民間の有識者である調停委員が間に入り、あくまで「話し合い」による解決を目指す手続きです。
いきなり裁判(訴訟)を起こすことはできず、まずはこの調停を経る必要があります(調停前置主義)。
ステップ4:地方裁判所での「訴訟」
調停でも話し合いがまとまらなかった場合の最終手段が「訴訟」です。
訴訟では、お互いの主張と証拠に基づき、裁判官が法的な判断(判決)を下すことになります。
【請求された側のあなたへ】突然の請求…どう対応する?

ある日突然、内容証明郵便で「遺留分侵害額請求」を受けたら、誰でも驚き、動揺すると思います。
しかし、ここでの対応が非常に重要になります。
1.無視は絶対ダメ!
まず、請求を無視することだけは絶対にやめましょう。
無視を続けると、相手は調停や訴訟といった法的手続きに進みます。
その際、あなたが話し合いに応じなかったという事実が、心証を悪くする可能性もゼロではありません。
2.時効をチェック!
相手の請求権が時効にかかっていないかを確認しましょう。
もし時効が成立している可能性がある場合、安易に「支払います」と認めるような発言をしてはいけません。
時効の利益を主張できなくなる恐れがありますので、すぐに弁護士に相談してください。
3.請求額は本当に正しい?
相手が提示してきた金額を鵜呑みにしてはいけません。
遺留分の計算の基礎となる遺産の評価、特に不動産や非上場株式の評価額は、評価方法によって大きく変わることがあります。
相手に有利な高い評価額で計算されている可能性も十分にあります。
4.【重要】支払いが難しい場合は「支払猶予」の申立てを!
「遺産は不動産だけで、請求された現金をすぐに用意できない…」 こんなケースは少なくありません。
ご安心ください。
今回の法改正では、請求された側の救済措置として、裁判所に申し立てることで、支払期限を延ばしてもらう(猶予してもらう)制度が新設されました(民法1047条5項)。
これは非常に重要なポイントですので、ぜひ覚えておいてください。
遺留分トラブルの「よくある失敗」と「落とし穴」

遺留分トラブルでは、知識がないために損をしてしまうケースが後を絶ちません。
【請求する側の失敗】
【請求された側の失敗】
これらの失敗は、早い段階で専門家に相談していれば防げた可能性が高いものばかりです。
なぜ弁護士に依頼すべき?双方にとっての大きなメリット

遺留分トラブルは、請求する側にとっても、される側にとっても、弁護士に依頼することで大きなメリットがあります。
-
正確な遺留分侵害額を計算できる:弁護士は、提携する不動産鑑定士や税理士と連携し、相続財産を正確に調査・評価します。これにより、請求する側は正当な権利に相当する額を把握することができ、請求される側は不当な支払いを防ぐことができます。
-
面倒な手続きや交渉をすべて任せられる:内容証明郵便の作成・送付、相手方との交渉、調停・訴訟の準備と対応など、複雑で精神的にも負担の大きい作業をすべて一任できます。
-
感情的な対立を避け、冷静な解決を目指せる:親族間の金銭トラブルは、どうしても感情的になりがちです。弁護士が代理人として間に入ることで、お互いが冷静になり、法的な論点に集中して話し合いを進めることができます。これは、精神的なストレスを軽減する上で非常に大きなメリットであり、早期解決が期待できます。
-
相手に「本気度」が伝わり、早期解決につながる:弁護士から通知が届くことで、相手も「これは本気だ。きちんと対応しなければ」と考え、交渉のテーブルにつきやすくなります。結果として、トラブルの長期化を防ぎ、早期解決につながるケースも少なくありません。
おわりに
遺留分をめぐる問題は、法改正によりルールが大きく変わりました。もはや「気合と根性」で乗り切れる問題ではなく、法律という専門知識に基づいた冷静な対応が不可欠です。
もしあなたが今、遺留分のことで悩んでいるなら、請求する立場であれ、請求された立場であれ、一人で抱え込まないでください。その一歩が、あなたの大切な権利を守り、一日も早い平穏な生活を取り戻すための最善の道筋となるはずです。
蒼生法律事務所では、遺留分をはじめとする相続問題に関するご相談を随時お受けしております。初回のご相談は無料ですので、「ちょっと話を聞いてみたい」という段階でも全く問題ありません。どうぞ、お気軽にお問い合わせください。
出典
遺留分制度に関する見直しなど(法務省)
遺留分侵害額の請求調停(裁判所)

2004年の弁護士登録以降、個人・法人問わず幅広い事件を担当し、クライアントにとっての重大事には誠実かつ丁寧に寄り添う。命運に配慮し、最善策を模索。豊富な実績と十分なコミュニケーションで、敷居の高さを感じさせない弁護士像を追求してきた。1978年大阪府出身、京都大学法学部卒業。2011年に独立。不動産・労務・商事・民事・破産・家事など多様な分野を扱い、2024年6月に蒼生法律事務所へ合流。相続・遺言