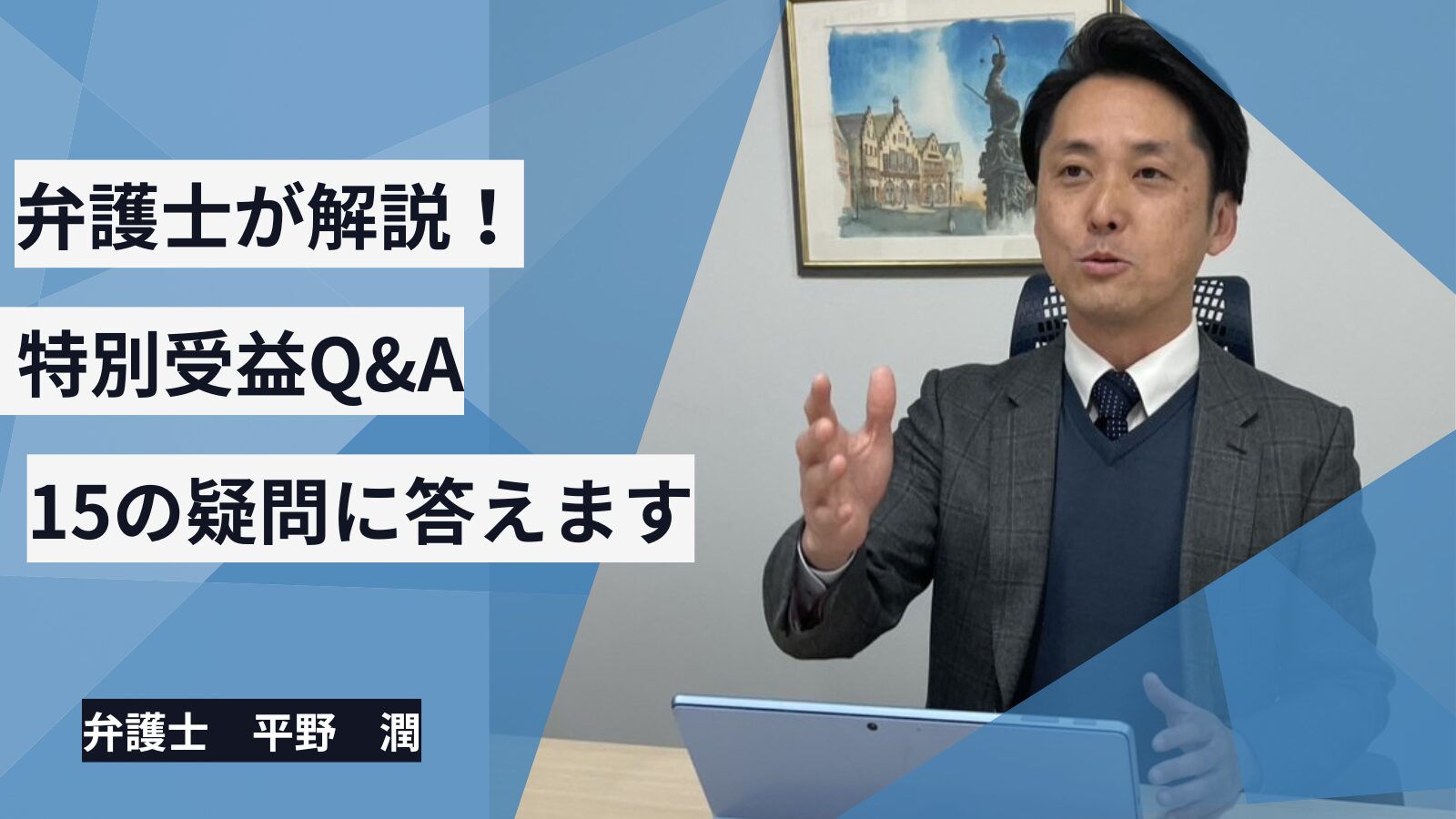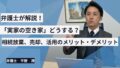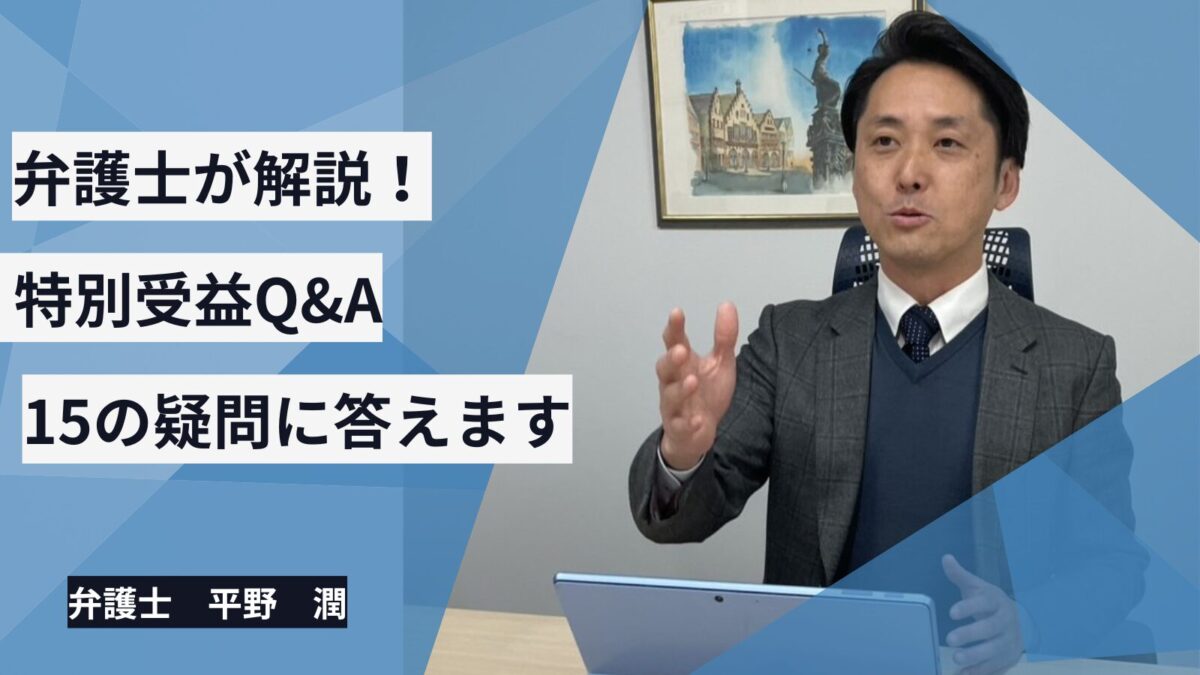
遺産相続の話になると、ご家族の間で「お兄ちゃんは昔、家を建てるのにお父さんからお金をもらっていたじゃないか」「妹は大学院まで行かせてもらったのに…」といった会話が出てくることがあります。
こうした、一部の相続人だけが生前に故人から受けた特別な援助をどう公平に扱うか、というのが今回テーマの「特別受益(とくべつじゅえき)」の問題です。
この問題は、相続トラブルの火種になりやすい非常にデリケートな部分です。そこで今回は、遺産相続の専門家である弁護士の視点から、特別受益に関するよくある疑問にQ&A形式で、分かりやすくお答えしていきます。
特別受益Q&A
はい、とても良い質問ですね。 「特別受益」とは、一部の相続人が、被相続人(亡くなった方)から生前に受け取った特別な利益(贈与)のことです。
相続が起こったとき、相続人の誰かがすでに多くの財産を受け取っていたとしたら、他の相続人と同じように遺産を分けるのは不公平ですよね。そこで、民法ではこの「特別受益」を遺産の前渡しとみなし、相続財産に一度持ち戻して(加算して)計算することで、相続人間の公平を図る制度を設けています。これを「特別受益の持ち戻し」と言います。
それは、相続人間の「公平」を保つためです。
例えば、お父さん(被相続人)の遺産が3000万円あり、相続人が長男と次男の2人だけだったとします。普通なら1500万円ずつ分けますよね。 しかし、もし長男が生前に、お父さんから事業資金として1000万円の援助を受けていたとしたらどうでしょう?次男からすれば、「兄さんだけずるい!」と感じるのが自然です。
そこで、特別受益の制度を使います。遺産3000万円に長男が受けた1000万円を「持ち戻し」て、遺産総額を4000万円とみなします。そして、この4000万円を法定相続分(2分の1ずつ)で分けると、各自の取り分は2000万円となります。
- 長男:本来の取り分2000万円 - すでに受け取った1000万円 = 実際の相続分1000万円
- 次男:実際の相続分2000万円
こうすることで、最終的に長男も次男も2000万円ずつ受け取ったことになり、公平が保たれるわけです。
特別受益は、大きく分けて以下の3つのケースが法律で定められています。
o 事業を始めるときの開業資金
o 家を建てたり、マンションを買ったりするための資金援助
o 借金の肩代わり
o 大学や大学院、留学など、他の兄弟とは異なるレベルの高等教育費用
原則として、特別受益にはなりません。
親には子を扶養する義務があります。そのため、未成年の子どもの生活費や通常レベルの教育費、あるいは一般的なお小遣いなどは、親の扶養義務の範囲内とみなされ、特別受益とは扱われません。
ただし、相続人の一人だけが私立の医科大学に進学し、その高額な学費(入学金や授業料)を親が支払ったようなケースでは、他の兄弟との間に著しい不公平が生まれるため、「生計の資本としての贈与」として特別受益と判断される可能性があります。
原則として、特別受益にはなりません。
生命保険金や死亡退職金は、受取人として指定された人の固有の財産と考えられているため、遺産そのものではなく、特別受益にもあたらないのが原則です。
しかし、例外もあります。受け取った保険金の額が、遺産総額などと比べてあまりにも大きく、これを特別受益としないと相続人間に著しい不公平が生じると裁判所が判断した場合には、例外的に特別受益とみなされることがあります(最高裁判所平成16年10月29日決定など)。これは非常に専門的な判断が必要となる部分です。
特別受益が認められるには、以下の要件を満たす必要があります。
特に3つ目の「生計の資本としての贈与」に該当するかどうかが、争いの中心になることが多いですね。
原則として、期間の制限はありません。
たとえ30年前、40年前の贈与であっても、それが特別受益の要件を満たす限り、主張することは可能です。ただし、あまりに昔のことになると、後述するように「証明」が非常に難しくなるという現実的な問題があります。
ただし、2023年の民法改正によって、特別受益が主張できる期間には制限が設けられましたので、その点は注意が必要です。
まずは、相続人全員で行う「遺産分割協議」の場で主張します。ここで他の相続人が納得すれば、その内容を遺産分割協議書に盛り込みます。
もし話し合いでまとまらなければ、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立て、調停委員を介して話し合いを進めることになります。調停でも合意に至らない場合は、「遺産分割審判」という手続きに移行し、最終的には裁判官が判断を下すことになります。
これが非常に重要なポイントです。特別受益は、主張する側がその事実を証明(立証)しなければなりません。
口約束だけでは「言った、言わない」の水掛け論になってしまいます。以下のような客観的な証拠や資料を集めることが不可欠です。
証拠がなければ、裁判所も特別受益を認めることはできません。
特別受益として受け取った財産の評価は、「相続開始時(被相続人が亡くなった時)」を基準に行います。
例えば、20年前に1000万円で贈与された土地が、相続開始時には3000万円に値上がりしていた場合、持ち戻すべき特別受益の額は3000万円として計算されます。現金の場合は、贈与時の金額を相続開始時の貨幣価値に換算して評価します。
はい、2019年7月1日に施行された改正相続法で、重要な変更がありました。
それは、婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用の不動産(マイホーム)を贈与した場合の扱いです。この場合、被相続人が「持ち戻しをしなくて良い」という意思表示(持ち戻し免除の意思表示)をしたものと推定されることになりました。
簡単に言うと、長年連れ添った配偶者が、住む場所に困らないようにとの思いやりから行ったマイホームの生前贈与は、原則として特別受益の計算から除外してよい、ということになったのです。これにより、残された配偶者の生活が保護されやすくなりました。
また、2023年4月1日に施行された改正相続法によって、特別受益を主張できる期間に制限が設けられました。
改正された民法では、相続開始時から10年を経過した後にする遺産分割は、基本的に、具体的相続分ではなく、指定相続分または法定相続分によると規定しています(民法904条の3)。
簡単に言うと、実際に特別受益に該当する事由があったとしても、相続開始後10年が経過してしまうと、原則として、特別受益の主張ができなくなり(寄与分の主張もできなくなります)、遺言によって指定された相続分や民法が定める相続分を基準とした遺産分割しかできなくなります。
最も多いのは、「証明」の難しさを軽く考えてしまうことです。 「昔、親がお金を出していたのを私は知っている」という確信があっても、それを客観的な証拠で示せなければ、法的な主張としては認められません。感情的に相手を問い詰めてしまい、関係が悪化するだけで終わってしまうケースは後を絶ちません。
また、「どんな援助も特別受益になるはずだ」と思い込んでしまうのも勘違いの一つです。扶養の範囲内の援助は特別受益にはあたりません。
特別受益の主張は、相手にとっては「あなたがもらい過ぎた分を返しなさい」と言っているのと同じです。そのため、感情的な対立が激化しやすいという大きなリスクがあります。
兄弟姉妹の関係に修復不可能な亀裂が入ってしまうことも少なくありません。また、調停や審判に発展すれば、解決までに時間も費用もかかります。主張する際は、感情的にならず、冷静に証拠に基づいて話し合いを進める姿勢が大切です。
やはり、相続開始後10年が経過してしまうと、原則として、特別受益の主張ができなくなる、という点です。改正民法が施行されたのは2023年4月1日のことですが、このルールは、改正民法の施行後に発生した相続だけでなく、施行前に被相続人が死亡したケースにも適用されます。
例えば、長男がマンションを購入する資金の贈与を行った父親が死亡したケースで、母親が元気なうちは特別受益だと言い出しにくく、10年以上が経過してしまった場合には、どれだけ生前贈与の証拠が揃っていたとしても、特別受益の主張ができなくなってしまいます。
特別受益の問題は、法律的な知識だけでなく、証拠の収集や相手との交渉など、非常に専門的な対応が求められます。弁護士にご依頼いただくメリットは、主に以下の5つです。
まとめ
遺産相続、特に特別受益が絡む問題は、ご家族だけでの解決が非常に難しい分野です。大切なご家族との関係を壊さず、ご自身の正当な権利を実現するためには、早い段階で専門家の力を借りることが最善の道だと私は考えています。
「これって特別受益になるのかな?」「他の兄弟の生前贈与に納得がいかない…」 少しでも疑問や不安を感じたら、一人で抱え込まずに、私たち相続のプロにご相談ください。蒼生法律事務所では、あなたの状況を丁寧にお伺いし、最善の解決策を一緒に考えます。
初回の法律相談は無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。
出典
•民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百三条(e-Gov法令検索)
•民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)(法務省)
•遺産分割調停(裁判所)

2004年の弁護士登録以降、個人・法人問わず幅広い事件を担当し、クライアントにとっての重大事には誠実かつ丁寧に寄り添う。命運に配慮し、最善策を模索。豊富な実績と十分なコミュニケーションで、敷居の高さを感じさせない弁護士像を追求してきた。1978年大阪府出身、京都大学法学部卒業。2011年に独立。不動産・労務・商事・民事・破産・家事など多様な分野を扱い、2024年6月に蒼生法律事務所へ合流。相続・遺言