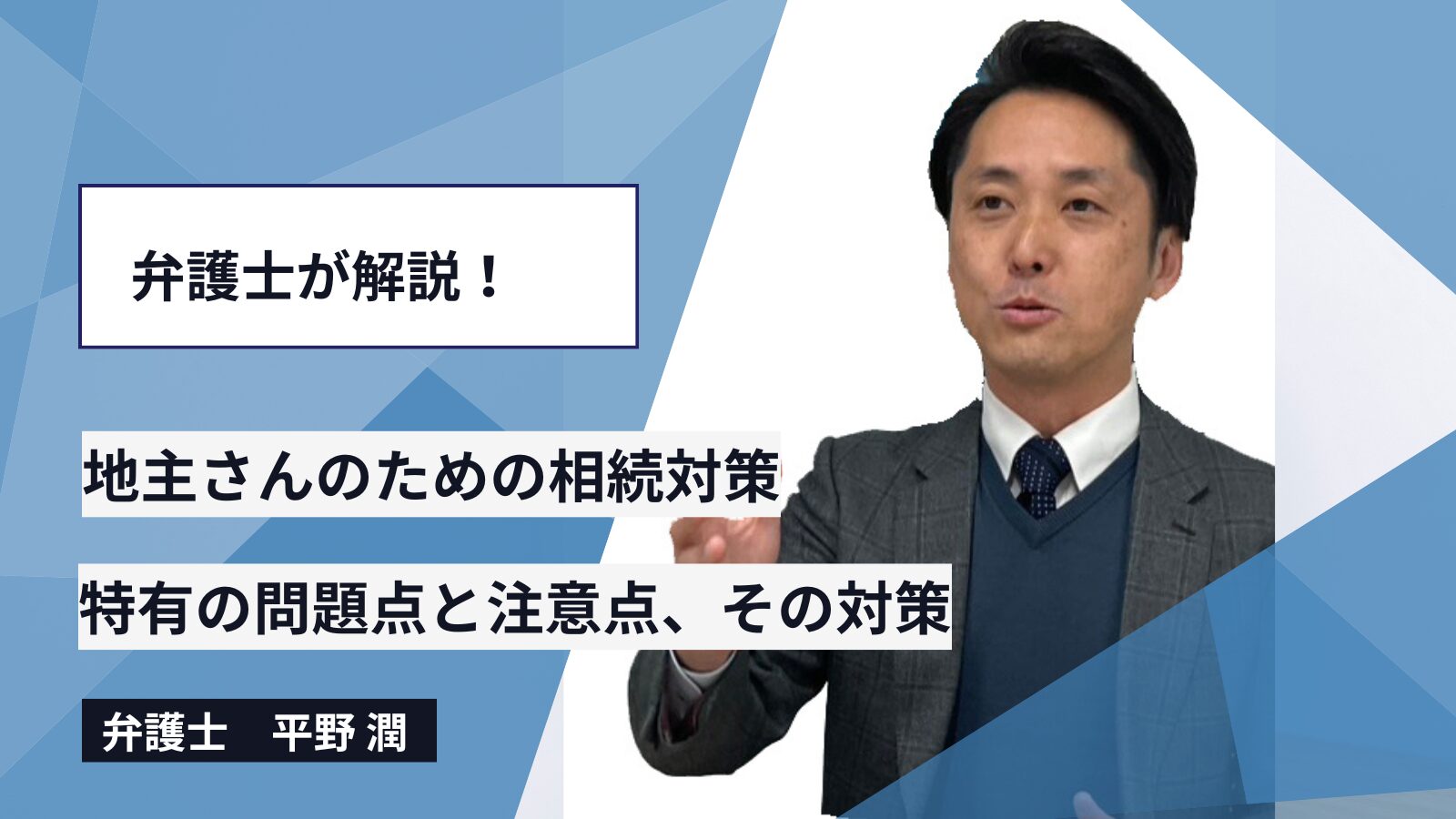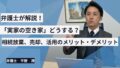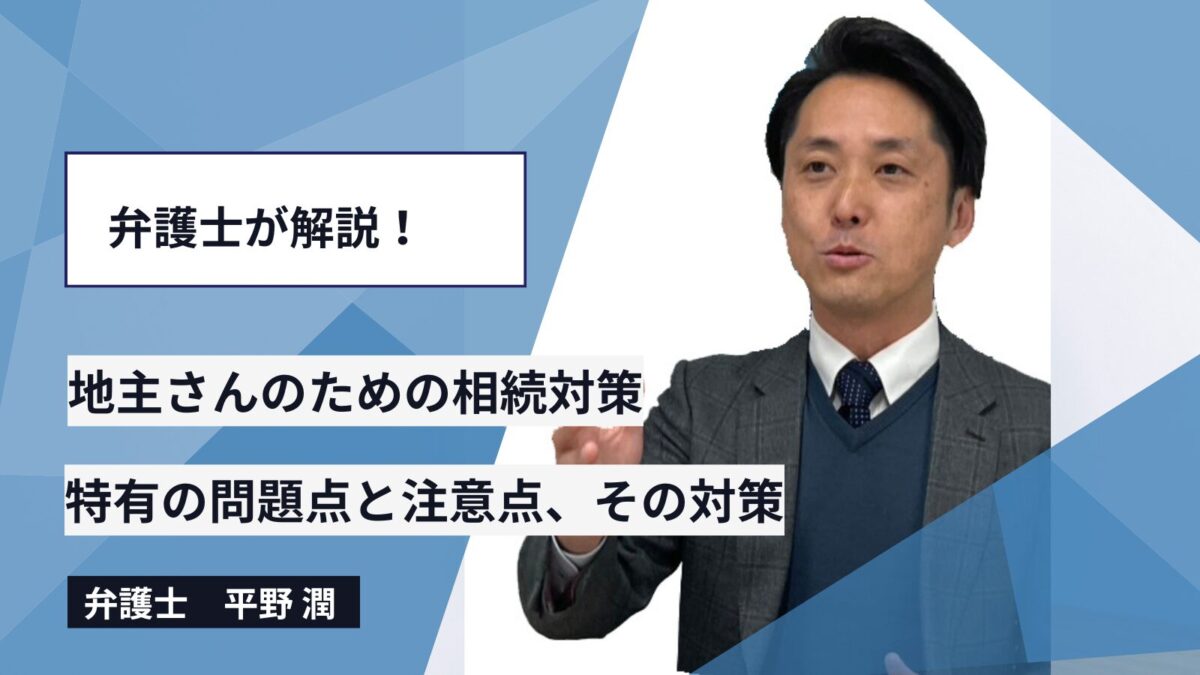
皆さん、こんにちは。蒼生(そうせい)法律事務所、代表弁護士の平野 潤です。
「うちは先祖代々の土地持ちだから、将来も安泰だ」 「財産といえば、ほとんどが土地と家くらいだよ」
このように考えていらっしゃる地主さんや、そのご家族は多いのではないでしょうか。しかし、法律家として多くの相続案件に携わってきた経験から申し上げますと、財産のほとんどが不動産である「地主さん」の相続こそ、最もトラブルになりやすいケースの一つなのです。
大切に守ってきたはずの土地が、ある日突然、家族の絆を引き裂く「争いの種」になってしまう…。そんな悲しい事態を避けるために、今回は地主さんの相続に特有の問題点と、今すぐ始めるべき対策について、分かりやすく解説していきます。
第1章:なぜ揉める?不動産相続に潜む「3つのワナ」

相続でもめる原因は、不動産が持つ特殊な性質にあります。預貯金や株式といった金融資産と比べて、不動産には大きく3つの「ワナ」があるのです。
| 特徴 | 不動産(土地・建物) | 金融資産(預貯金・株式) |
|---|---|---|
| 分割のしやすさ | 分けにくい | 分けやすい(1円単位で可能) |
| 評価のしやすさ | 評価しにくい | 評価しやすい(時価が明確) |
| 換金のしやすさ | 換金しにくい | 換金しやすい(すぐに現金化できる) |
この違いが、相続の現場で深刻な問題を引き起こします。
ワナ①:どうやっても公平に「分けにくい」
1億円の預貯金であれば、2人の相続人で5,000万円ずつ、と簡単に分けられます。しかし、1億円の価値がある土地を2人で分けるのは至難の業です。
- 現物分割(げんぶつぶんかつ):土地を物理的に分ける方法です。しかし、「兄さんの土地は道路に面した角地で、私のは奥まった日当たりの悪い土地。不公平だ!」といった争いが絶えません。
- 換価分割(かんかぶんかつ):土地を売却して現金で分ける方法です。公平ですが、「先祖から受け継いだ土地を売りたくない」という感情的な抵抗が強く、話がまとまらないことがよくあります。
- 代償分割(だいしょうぶんかつ):相続人の一人が土地をすべて相続する代わりに、他の相続人へお金(代償金)を支払う方法です。しかし、土地の評価額が高額なため、代償金を支払えるほどの現金を後継者が持っていないケースがほとんどです。
ワナ②:基準がバラバラで「評価しにくい」
不動産には、一つの決まった値段がありません。場面によって様々な評価基準が使われます。
【専門用語解説:不動産の評価額】
- 実勢価格:実際に市場で売買される価格。
- 相続税評価額(路線価など):相続税を計算するための国が定めた評価額。実勢価格の8割程度が目安です。
- 固定資産税評価額:固定資産税を計算するための市町村が定めた評価額。実勢価格の7割程度が目安です。
遺産分割の話し合いでは、代償金を支払う側は「相続税評価額で計算しよう」と主張し、もらう側は「いや、もっと高い実勢価格で計算すべきだ」と主張するなど、どの基準を使うかで対立し、議論が平行線になってしまうのです。
ワナ③:いざという時に「現金化しにくい」

地主さんの相続で最も深刻なのが、高額な相続税の納税資金問題です。 土地の評価額が数億円にのぼり、相続税が数千万円になることは珍しくありません。しかし、手元にそれだけの現金がない場合、どうすればよいのでしょうか。
不動産は、株式のように「明日売って納税資金にしよう」ということができません。買い手を見つけて、契約し、引き渡すまでには数ヶ月、場合によっては1年以上かかることもあります。これに対して、相続税の申告・納付期限は「相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内」と決まっており、悠長に待ってはくれません。
結果として、納税のために先祖代々の土地を慌てて安値で手放さざるを得なくなったり、銀行から多額の借金を背負ったりすることになるのです。
第2章:その判断が命取りに!不動産相続の落とし穴とよくある失敗

「とりあえず、法定相続分でみんなの共有名義にしておこう」 遺産分割がまとまらない時、こう考える方は非常に多いのですが、これは将来にトラブルを先送りしているだけで、問題をさらに深刻化させる最悪の選択と言っても過言ではありません。
落とし穴①:恐怖の「共有名義」と「負動産」化リスク
不動産を共有名義にすると、その不動産を売却したり、アパートを建てたりといった活用をする際に、毎回、共有者全員の同意が必要になります。一人でも反対すれば、何もできずに土地は塩漬け状態です。
さらに恐ろしいのが、二次相続、三次相続です。 例えば、兄弟3人で共有していた土地があったとします。兄が亡くなれば、その持ち分は兄の配偶者と子供たちに相続されます。次に弟が亡くなれば、その持ち分が…というように、世代を経るごとに権利関係者がネズミ算式に増えていきます。
数十年後には、会ったこともない親戚を含む数十人が共有者になっている、なんてことも。こうなると、もはや誰も活用も売却もできず、固定資産税だけがかかり続ける、まさに「負動産」と化してしまうのです。
落とし穴②:見落としがちな「維持費用」の負担
不動産は持っているだけでお金がかかります。相続した瞬間から、毎年固定資産税や都市計画税の支払い義務が発生します。マンションであれば管理費や修繕積立金もかかります。
収益を生む駐車場や賃貸物件ならまだしも、ただの更地や古い実家を相続した場合、この維持費が家計に重くのしかかり、相続したことを後悔する方も少なくありません。
よくある失敗・勘違い
- 「うちは家族仲が良いから揉めない」という過信
相続は、お金が絡む非常にデリケートな問題です。それまで仲が良かった兄弟姉妹でも、それぞれの配偶者や子供の意見などが加わることで、関係がこじれてしまうことは日常茶飯事です。
- 「物納すればいい」という安易な考え
確かに、納税資金がない場合に、不動産そのもので税金を納める「物納」という制度はあります。しかし、その要件は非常に厳しく、国が管理・処分しにくいと判断した土地(境界が確定していない土地など)はまず物納が認められません。安易に物納をあてにしていると、計画が破綻する可能性があります。
第3章:元気なうちから始める!「争族」を避けるための生前対策

ここまで不動産相続の怖さをお伝えしてきましたが、ご安心ください。これらの問題は、元気なうちにしっかりと対策をすれば、その多くが回避できるはずです。
対策①:最強の対策、「公正証書遺言」の作成
遺言書は、ご自身の想いを実現し、残された家族を「争族」から守るための最も強力なツールです。特に、誰にどの不動産を相続させるか明確に指定することで、無用な遺産争族を避けることができます。
【専門用語解説:遺言書の種類】
- 自筆証書遺言:自分一人で手軽に書けますが、形式の不備で無効になったり、発見されなかったりするリスクがあります。
- 公正証書遺言:公証役場で公証人に作成してもらう遺言です。費用はかかりますが、形式不備の心配がなく、原本が公証役場に保管されるため、最も確実で安全な方法です。
なぜこの土地をこの子に継がせたいのか、といった想いを「付言事項」として書き記すことも、他の相続人の納得を得る上で非常に有効です。
対策②:納税資金を確保する、「生命保険」の活用
生命保険は、納税資金対策として絶大な効果を発揮します。 被相続人(地主さん)がご自身を被保険者とし、相続人(後継者)を受取人とする生命保険に加入しておくのです。
相続が発生すると、受取人である後継者は死亡保険金を現金で受け取ることができます。この現金を、納税資金や、他の相続人へ支払う代償金の原資に充てることができます。
さらに、死亡保険金には「500万円 × 法定相続人の数」という非課税枠があり、受取人固有の財産となるため、遺産分割の対象にならないという大きなメリットもあります。
対策③:資産の組み換えと計画的な「生前贈与」
すべての土地を無理に残そうとせず、元気なうちに資産のポートフォリオを見直すことも重要です。
- 資産の組み換え:収益性の低い土地や管理が大変な土地は売却して、納税資金となる現金や、分割しやすい金融資産、あるいは収益性の高い不動産に買い換えるといった対策です。
- 生前贈与:暦年贈与(年間110万円まで非課税)や相続時精算課税制度などを活用し、計画的に次世代へ財産を移転していくことも有効な手段です。
第4章:相続問題、なぜ弁護士に相談すべきなのか?

相続の問題というと、税理士や司法書士を思い浮かべる方も多いかもしれません。もちろん、税金(相続税)の申告は税理士、不動産の名義変更(登記)は司法書士の専門分野です。
しかし、相続人間で意見が対立してしまった場合、代理人として他の相続人と交渉したり、家庭裁判所での調停や審判の場であなたの権利を守ったりできるのは、法律上、弁護士だけです。また、弁護士であれば、遺留分にも配慮した、遺産分割の方法を提案することも可能です。
弁護士に依頼するメリット
- 感情的な対立からの解放:当事者同士だと感情的になりがちな話し合いも、弁護士が間に入ることで冷静に進められます。
- 法的な見通しが立つ:あなたの状況で、法的にどのような主張が認められるのか、最善の解決策は何かを的確にアドバイスできます。
- 交渉や手続きのすべてを任せられる:相手方との交渉、煩雑な書類の作成や役所の手続きなど、精神的・時間的な負担から解放されます。
- 将来のトラブルを防ぐ:その場しのぎではない、将来にわたって禍根を残さない「遺産分割協議書」を作成し、円満な解決を目指します。
まとめ:相続対策は「まだ早い」はありません
相続対策は、決して「死」を意識したネガティブなものではありません。むしろ、ご自身が築き、守ってきた大切な財産と、愛するご家族の未来を守るための、前向きで愛情あふれる活動です。
そして、その準備は、ご自身が元気で、判断力もはっきりしているうちでなければできません。
「何から始めたらいいか分からない」 「うちの場合は、どんな対策が一番いいのだろう?」 「少しでも家族の間に不穏な空気を感じる…」
もし、少しでもご不安なことがあれば、一人で抱え込まないでください。私たち法律の専門家は、あなたの想いに寄り添い、最善の解決策を一緒に見つけるパートナーです。
蒼生法律事務所では、初回のご相談は無料で承っております。まずはお話をお聞かせいただくことから始めませんか。
どうぞ、お気軽にお問い合わせください。

2004年の弁護士登録以降、個人・法人問わず幅広い事件を担当し、クライアントにとっての重大事には誠実かつ丁寧に寄り添う。命運に配慮し、最善策を模索。豊富な実績と十分なコミュニケーションで、敷居の高さを感じさせない弁護士像を追求してきた。1978年大阪府出身、京都大学法学部卒業。2011年に独立。不動産・労務・商事・民事・破産・家事など多様な分野を扱い、2024年6月に蒼生法律事務所へ合流。相続・遺言