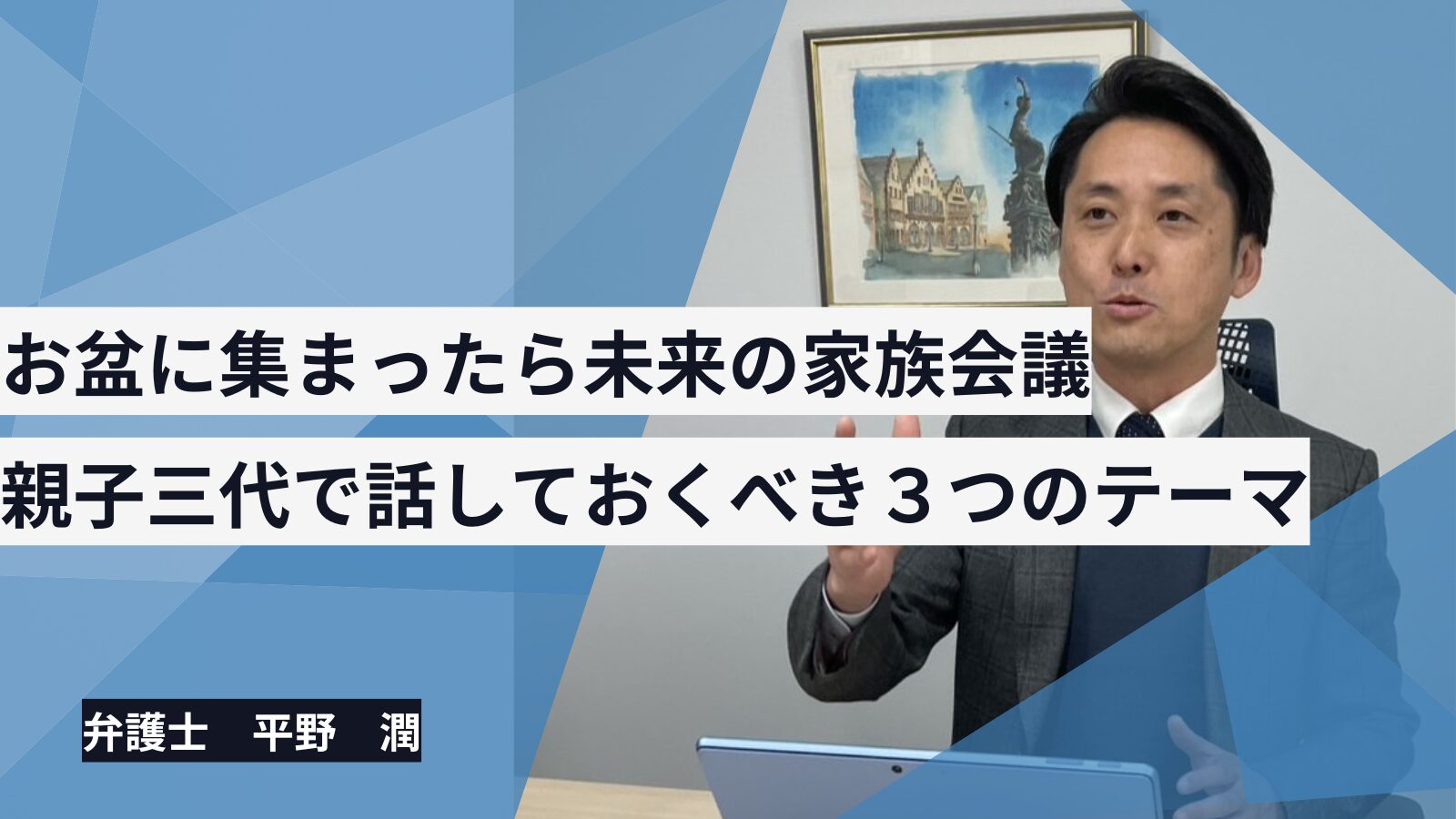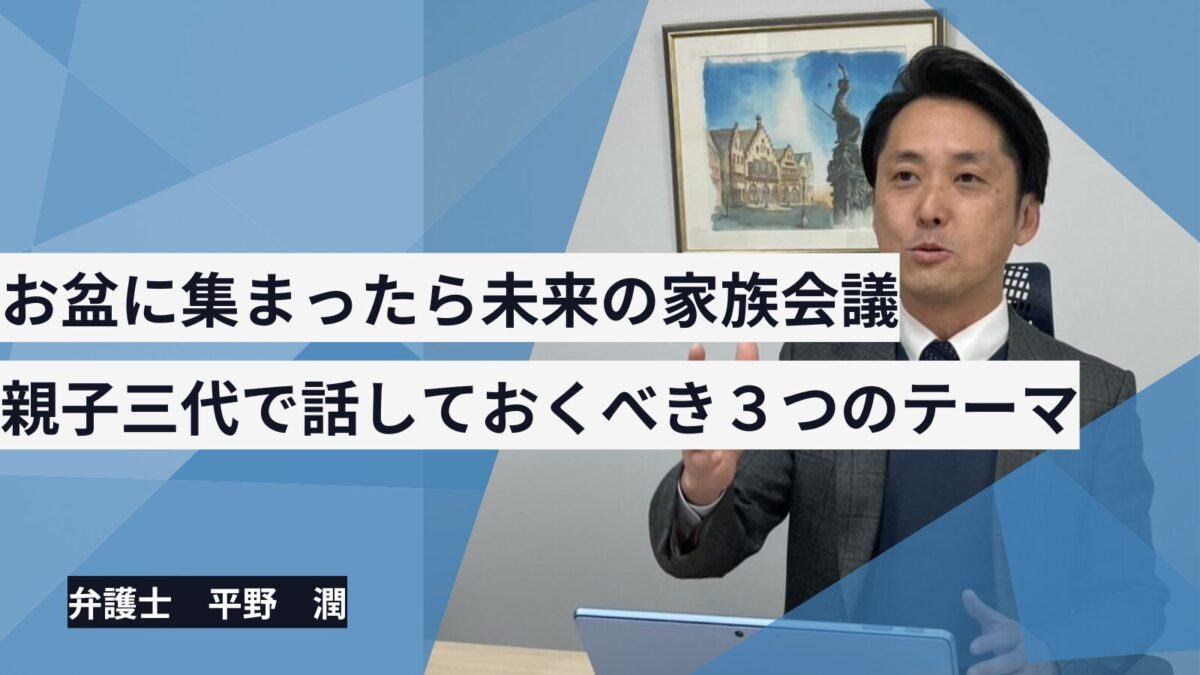
お盆の季節がやってきましたね。久しぶりにご家族やご親戚と顔を合わせ、積もる話に花を咲かせる方も多いのではないでしょうか。賑やかな食卓を囲みながら、お子さんやお孫さんの成長に目を細めたり、昔話に笑い合ったりするのは、何物にも代えがたい大切な時間です。
そんな和やかな雰囲気のなかで、少しだけ「未来の家族」について、親子三代で話す時間を持ってみませんか?
「お金の話は、なんだか切り出しにくい…」 「縁起でもない」
そう思われるかもしれません。しかし、多くのご家庭で相続が「争族」になってしまうのは、まさにこの「切り出しにくさ」が原因なのです。元気なうちに、皆の気持ちが穏やかなうちに話しておくことこそ、家族の絆を守る最大の備えになります。
今回は、お盆の機会にぜひ親子で話しておきたい、未来のための3つのテーマについて、弁護士の視点から分かりやすくお話しします。
テーマ1:親の「今」と「これから」について~財産管理と後見制度~

ご両親は、まだまだ元気に見えるかもしれません。しかし、年齢を重ねれば、誰でも少しずつ身体の自由が利かなくなったり、物事を判断する能力がゆっくりと低下したりするのは自然なことです。
●忍び寄る財産管理のリスク
最近、実家に帰ったら、見慣れない健康器具や高額な布団が増えていた、なんてことはありませんか?高齢者を狙った詐欺の手口は年々巧妙化しており、「自分は大丈夫」と思っていても、巧みな話術や親切を装ったアプローチで、大切なお金をだまし取られてしまうケースが後を絶ちません。
また、認知症などで判断能力が不十分になると、銀行でお金をおろしたり、不動産を売却したりといった法律行為がご自身ではできなくなってしまいます。例えば、親御さんの介護費用を捻出するために実家を売りたいと思っても、ご本人の意思確認ができなければ、手続きを進めることができません。
このような事態に備えるための制度が「後見制度(こうけんせいど)」です。
後見制度には、大きく分けて2つの種類があります。
-
1.法定後見(ほうていこうけん):すでに判断能力が低下してしまった場合に、ご家族などが家庭裁判所に申し立てて、後見人を選んでもらう制度です。ご本人の判断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があります。
-
2.任意後見(にんいこうけん):こちらは、まだ判断能力がしっかりしているうちに、将来判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめご自身で信頼できる人(任意後見人)を選び、どのような支援をしてもらいたいかを公正証書で契約しておく制度です。ご自身の意思を最大限に尊重できるのが大きな特徴です。
「まだ元気だから大丈夫」ではなく、「元気なうちだからこそ」、万が一の時に誰に財産管理を任せたいか、どんな生活を送りたいかを話し合っておくことが大切です。任意後見契約を結んでおけば、いざという時にスムーズに財産の管理や身上の監護をスタートでき、ご家族の負担も大きく軽減できます。
【出典】・後見制度について(法務省)
・成年後見制度(裁判所)
テーマ2:家業や財産の「未来」について~事業承継と生前贈与~

医師、会社経営者、不動産オーナーなど事業者の方々にとって、ご自身の財産は、単なる資産であるだけでなく、従業員の生活や地域経済、そして家族の未来そのものを支える大切な基盤です。
●「誰に継がせるか」という重要な決断
「会社は長男に」「クリニックは後を継いでくれる娘に」 そのお気持ちは、とても自然なものです。しかし、その思いを法的に有効な形で準備しておかなければ、残されたご家族が大変な苦労をすることになります。
例えば、会社の株式。中小企業の場合、株式が様々な親族に分散してしまうと、経営権が不安定になり、会社の意思決定がスムーズに進まなくなる恐れがあります。最悪の場合、経営権をめぐる争いに発展し、会社の存続そのものが危うくなることも少なくありません。
こうした事態を避けるために有効なのが、「遺言」や「生前贈与」の活用です。
-
【専門用語解説:生前贈与(せいぜんぞうよ)とは?】
ご自身が生きているうちに、ご自身の財産を特定の人に無償で分け与えることです。計画的に財産を移転できるため、事業承継や相続税対策として活用されることがあります。
後継者と決めたお子さんに、計画的に自社株や事業用資産を生前贈与していくことで、経営権を集中させ、スムーズな事業承継を実現できます。
●忘れてはならない「遺留分」への配慮

ただし、ここで一つ、非常に重要な注意点があります。それは「遺留分(いりゅうぶん)」への配慮です。
-
【専門用語解説:遺留分(いりゅうぶん)とは?】
兄弟姉妹を除く法定相続人(配偶者、子、親など)に、法律上最低限保障されている遺産の取り分のことです。例えば、「全財産を長男に相続させる」という遺言があったとしても、他の相続人(次男や長女など)は、この遺留分に相当する金額を長男に対して請求することができます。これを「遺留分侵害額請求」と呼びます。
事業承継のために特定のお子さんに財産を集中させると、他の相続人の遺留分を侵害してしまう可能性が高くなります。そうなると、後継者は他の兄弟姉妹から遺留分侵害額請求を受け、その支払いのために会社の資金繰りが悪化したり、事業用の不動産を手放さざるを得なくなったりするケースも現実に起きています。
そうならないためにも、 「なぜ、この子に会社を継がせたいのか」 「他の兄弟には、代わりにこの財産を残そう」 といった親御さんの想いを皆に伝え、全員が納得できるような分割案をあらかじめ検討しておくことが不可欠です。生命保険を活用して、後継者が遺留分を支払うための資金(代償金)を準備しておく、といった対策も有効です。
【出典】 ・法務省:民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)
テーマ3:「争族」を避けるための「思いやり」について~遺産分割のルール~

最後のテーマは、相続の最も中心的な問題である「遺産分割(いさんぶんかつ)」です。
親御さんが亡くなった後、残された財産を相続人全員の話し合いによって分ける手続きを「遺産分割協議」といいます。法律で定められた相続割合(法定相続分)はありますが、必ずしもその通りに分ける必要はなく、皆が合意すれば自由に分割方法を決めることができます。
しかし、この話し合いがまとまらないと、「争族」の火種になります。特に問題となりやすいのが、「特別受益(とくべつじゅえき)」と「寄与分(きよぶん)」です。
-
【専門用語解説】
一部の相続人だけが、被相続人(亡くなった方)から生前に特別な利益(例:マイホームの購入資金、事業の開業資金、多額の学費など)を受けていた場合、その利益を相続財産に加算して(持ち戻して)各相続人の相続分を計算する制度です。相続人間の公平を図るためのものです。
被相続人の財産の維持または増加に、特別な貢献をした相続人がいる場合に、その貢献度を金銭的に評価し、法定相続分に上乗せして財産を取得できる制度です。例えば、親の事業を無給で手伝い続けた、長年にわたり親の介護を一身に引き受けた、といったケースが該当します。
これらの制度は、相続人間の公平を図るための素晴らしいルールですが、一方で「何が特別受益にあたるのか」「どのくらいの貢献が寄与分として認められるのか」について、明確な基準がないため、感情的な対立を生みやすいのです。
●準備を怠ったばかりに…ある家族の失敗ケース

・・・ 生前にしっかりとした準備をしていないと、以下のような事態になるかもしれません。 ・・・
お父様が亡くなり、相続人は長男と次男の二人。お父様は生前、「事業は長男に継がせる。その代わり、自宅の土地建物は、ずっと同居して母親の面倒も見てくれた次男に」と口癖のように言っていました。兄弟もそのつもりでいました。
しかし、お父様は遺言書を作成していませんでした。
いざ遺産分割協議が始まると、事業を継いだ長男の奥様が「法律上の取り分は半分ずつのはず。次男さん一家が実家に住み続けるなら、それ相応の対価を支払うべきだ」と主張し始めたのです。
このようなことを長男さん側から言われてしまうと、次男さんからすれば、「親の面倒を見てきた貢献(寄与分)はどうなるんだ」「(長男さん側は)親から事業という大きな利益(特別受益)を受けているではないか」という思いが出てしまいます。
結局、兄弟間の話し合いは決裂。家庭裁判所での調停、審判へと進み、数年にわたる争いの末、兄弟の縁は完全に切れてしまいました。もし、お父様が元気なうちに、ご自身の想いを法的に有効な「遺言書」として残しておけば、こんな悲劇は避けられたはずです。
事前準備こそ最大の家族愛。まずは弁護士にご相談ください

ここまでお読みいただき、いかがでしたでしょうか。 相続の話は、お金の話であると同時に、家族の歴史や感情が複雑に絡み合う、非常にデリケートな問題です。
だからこそ、専門家である弁護士を間に立てるメリットは非常に大きいと考えています。
お盆で家族が集まるこの機会は、未来の家族について考えるまたとないチャンスです。 「うちの家族に限って、揉めるはずがない」 そう思っているご家庭ほど、いざという時の備えができていないものです。
問題が深刻化する前に、まずは専門家の話を聞いてみませんか?
蒼生法律事務所では、お一人お一人のご家庭の状況を丁寧にお伺いし、何が最善の道なのかを一緒に考えさせていただきます。
「何から話せばいいか分からない」という方も、まったく心配いりません。まずは現状をお話しいただくだけで、問題点を整理し、進むべき方向性をお示しします。
このお盆が、ご家族の絆をさらに深める、素晴らしいきっかけになることを心から願っています。
まずはお気軽にお問い合わせください。

2004年の弁護士登録以降、個人・法人問わず幅広い事件を担当し、クライアントにとっての重大事には誠実かつ丁寧に寄り添う。命運に配慮し、最善策を模索。豊富な実績と十分なコミュニケーションで、敷居の高さを感じさせない弁護士像を追求してきた。1978年大阪府出身、京都大学法学部卒業。2011年に独立。不動産・労務・商事・民事・破産・家事など多様な分野を扱い、2024年6月に蒼生法律事務所へ合流。相続・遺言