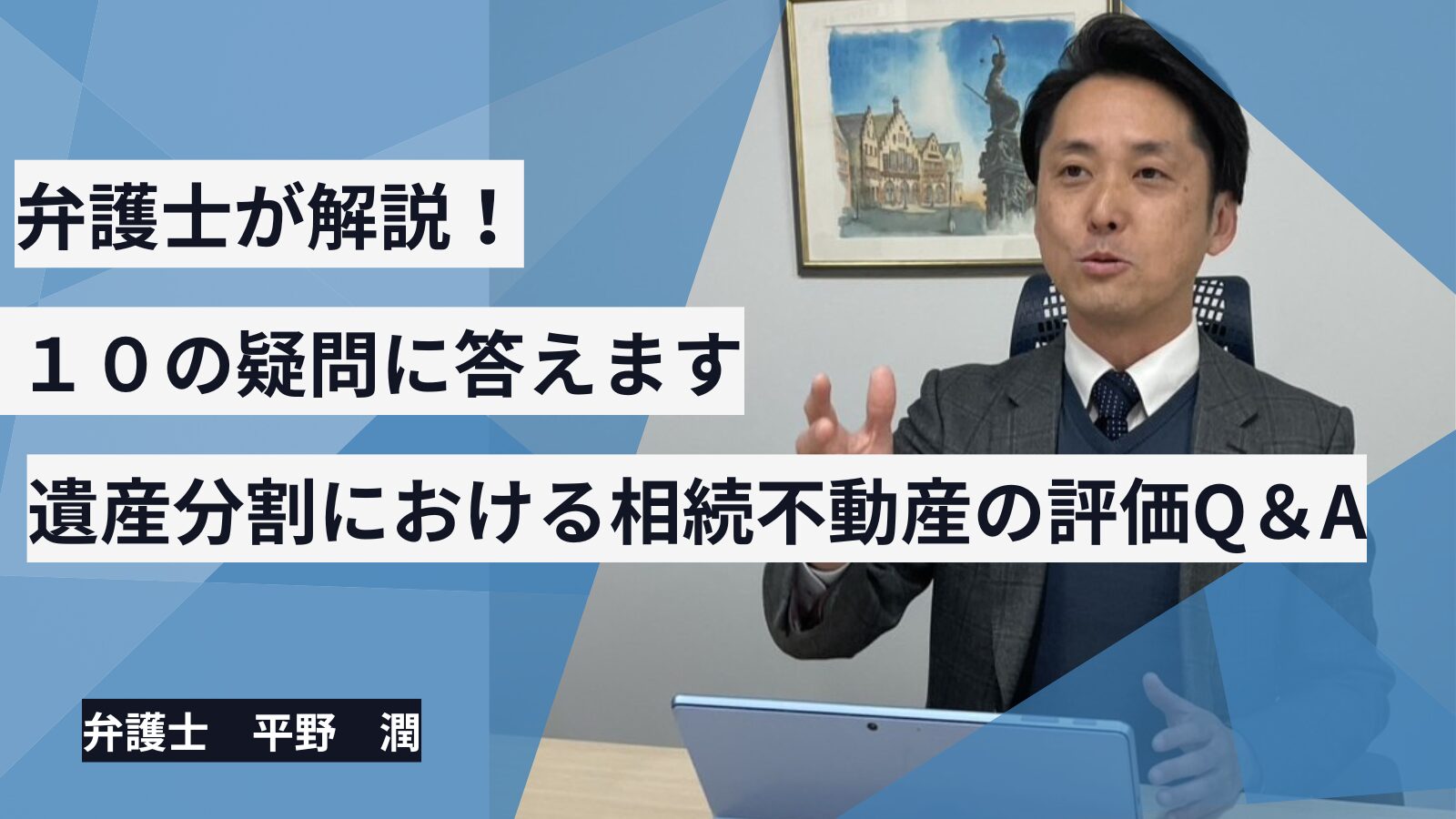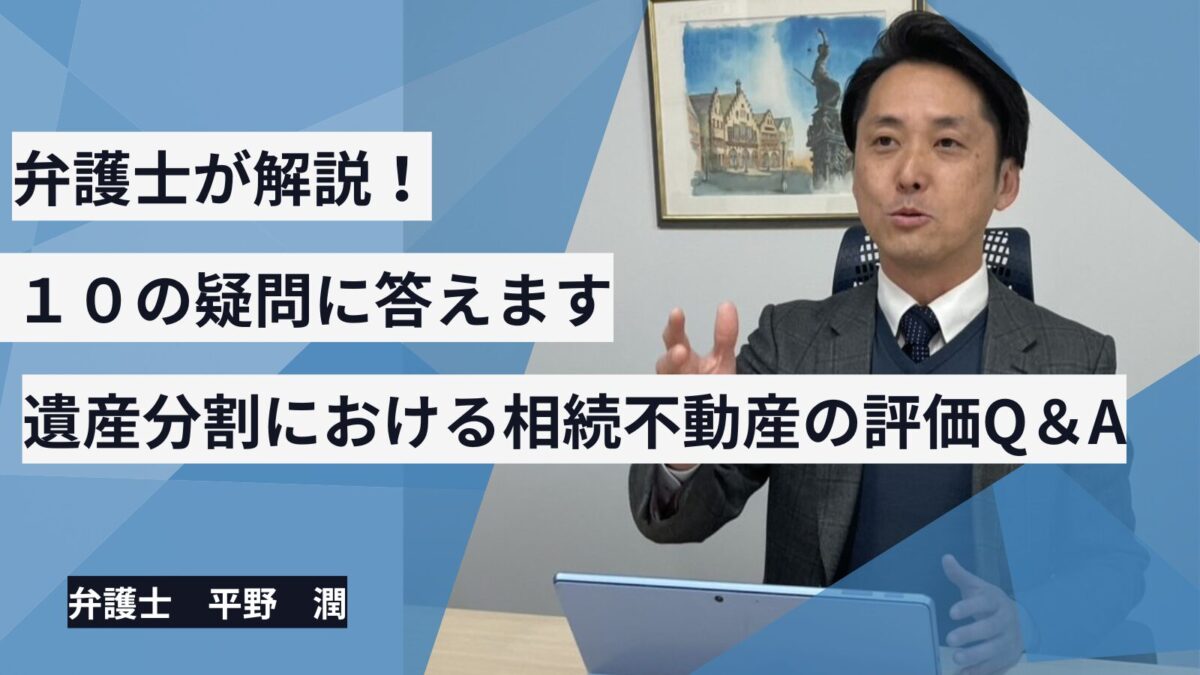
遺産相続の話合い(遺産分割協議)を進める中で、多くの方が頭を悩ませるのが「不動産」の扱いです。特に、不動産の価値をどう評価するかは、相続トラブルの大きな原因の一つになり得ます。
「実家をどう分ければいいの?」 「兄は都心のマンション、私は地方の土地。これって公平?」 「不動産の価値って、誰がどうやって決めるの?」
このような疑問や不安をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
今回のブログでは、遺産分割における不動産の評価について、皆さんが抱えがちな疑問にQ&A形式で分かりやすくお答えしていきます。この記事を読めば、不動産評価の基本的な考え方から、具体的な方法、そして思わぬ落とし穴まで、幅広く理解を深めることができるはずです。
- Q1. そもそも、なぜ遺産分割で不動産の評価が必要なのですか?
- Q2. 「共有」や「持分」という言葉をよく聞きますが、どういう意味ですか?
- Q3. 土地の種類(宅地、農地、山林)によって評価方法は変わりますか?
- Q4. 土地の形や場所も評価額に関係しますか?
- Q5. 具体的な不動産の評価方法には、どんな種類がありますか?
- Q6. 評価するタイミングはいつ時点の価格ですか?「相続開始時」と「遺産分割時」で違うのですか?
- Q7. 不動産の価値を自分で調べる方法はありますか?
- Q8. 「査定」と「鑑定」はどう違うのですか?
- Q9. 不動産評価でよくある失敗や注意点は何ですか?
- Q10. 不動産の遺産分割を弁護士に依頼するメリットは何ですか?
- まとめ
- 出典
Q1. そもそも、なぜ遺産分割で不動産の評価が必要なのですか?

A. 相続人全員が納得して、公平に遺産を分けるためです。
遺産分割は、亡くなった方(被相続人)の財産を、各相続人が法律で定められた割合(法定相続分)に応じて分け合う手続きです。預貯金のように1円単位で分けられるものであれば話は簡単ですが、不動産は物理的に分割することが難しく、その価値も一見しただけでは分かりません。
例えば、相続人が長男と次男の2人で、遺産が「都心にある評価額5,000万円のマンション」と「現金3,000万円」だったとします。もし、長男がマンションを、次男が現金を相続した場合、長男の方が2,000万円も多く相続することになり、不公平ですよね。
このような不公平をなくし、各相続人の相続分を正確に計算するために、不動産の価値を客観的な金額で評価する必要があるのです。この評価額を基準に、「誰がどの財産を相続するか」「相続分に差額がある場合、どうやって清算するか(代償金)」などを決めていきます。
Q2. 「共有」や「持分」という言葉をよく聞きますが、どういう意味ですか?

A. 「共有」とは一つの不動産を複数人で所有すること、「持分」とはその所有権の割合のことです。
不動産を相続したものの、すぐに売却したり、誰か一人が相続したりするのが難しい場合、相続人全員で共同所有する「共有」という状態になることがあります。
そして、それぞれの相続人が持つ所有権の割合を「共有持分(きょうゆうもちぶん)」または単に「持分(もちぶん)」と呼びます。例えば、兄弟3人で実家を相続した場合、特に取決めがなければ、それぞれの持分は3分の1ずつとなります。
共有状態は、一見すると公平な解決策に思えるかもしれません。しかし、将来的にその不動産を売却したり、建て替えたりする際には、共有者全員の同意が必要になるなど、権利関係が複雑になりがちです。ささいな意見の食い違いから、後々大きなトラブルに発展するケースも少なくありませんので、安易に共有状態を選択するのは避けるべきでしょう。
Q3. 土地の種類(宅地、農地、山林)によって評価方法は変わりますか?

A. はい、大きく変わります。土地の現況や法律上の規制によって評価方法が異なります。
- 宅地(たくち):家やビルが建っている、または建てられる土地のことです。一般的に、都市部にある宅地は「路線価方式」、それ以外の地域は「倍率方式」という方法で評価されます。
- 農地(のうち):田んぼや畑など、耕作に使われる土地です。農地は、農業を保護するための法律(農地法)で転用や売買が厳しく制限されています。そのため、単純な宅地としての評価はできず、「純農地」「中間農地」「市街地周辺農地」「市街地農地」といった区分に応じて、専門的な評価が必要になります。
- 山林(さんりん):木々が生い茂る山の土地です。こちらも「純山林」「中間山林」「市街地山林」に区分され、評価方法が異なります。保安林に指定されているなど、利用に制限がある場合は評価額が大きく変わることもあります。
このように、土地の種類によって評価の考え方が全く異なるため、専門的な知識が不可欠です。
Q4. 土地の形や場所も評価額に関係しますか?

A. はい、大きく関係します。同じ面積の土地でも、条件によって評価額は全く異なります。
土地の評価は、画一的なものではありません。以下のような個別の要因を考慮して、評価額が加算されたり、減額されたりします(「補正」といいます)。
- 形状:正方形や長方形といった「整形地」は評価が高く、旗竿地(はたざおち)や三角形、不整形な土地は評価が低くなる傾向があります。
- 隣地・周辺環境:角地は利用価値が高いため評価が上がります。一方で、墓地やごみ処理場、騒音の激しい工場などが近くにある場合は、評価が下がる要因になります。建築基準法上の道路に接していない土地(無道路地)も評価が下がります。
- 所在:駅からの距離、商業施設の有無、前面道路の幅など、利便性が高いほど評価は高くなります。
- 特殊な事情:土地の中に他人のガス管が埋設されている、高圧線が上空を通っている、土壌汚染の可能性があるといった特殊な事情がある場合、評価額は大きく減額される可能性があります。
これらの要因を一つ一つ丁寧に分析することが、適正な評価には欠かせません。
Q5. 具体的な不動産の評価方法には、どんな種類がありますか?

A. 主に4つの評価方法があり、それぞれ目的や評価額の水準が異なります。遺産分割では、どの評価方法を使うか相続人間で合意することが重要です。
| 評価方法 | 概要 | 評価する機関 | 価格水準の目安 | 主な利用目的 |
|---|---|---|---|---|
| 公示価格(こうじかかく) | 国が毎年公表する、標準的な土地の1㎡あたりの価格。土地取引の客観的な目安となる。 | 国土交通省 | 実勢価格の90%程度 | 公共事業用地の取得価格算定など |
| 固定資産税評価額(こていしさんぜいひょうかがく) | 固定資産税や都市計画税、不動産取得税などを計算するための基準となる価格。3年に1度見直される。 | 市町村(東京23区は都) | 公示価格の70%程度 | 固定資産税等の税額計算 |
| 相続税路線価(そうぞくぜいろせんか) | 相続税や贈与税を計算するための基準となる価格。道路に面する土地の1㎡あたりの価格で、毎年公表される。路線価が定められていない地域では、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じる「倍率方式」が用いられる。 | 国税庁 | 公示価格の80%程度 | 相続税・贈与税の税額計算 |
| 実勢価格(じっせいかかく) | 実際に市場で売買されると想定される価格(時価)。不動産会社による査定や、不動産鑑定士による鑑定評価によって求められる。 | 不動産会社、不動産鑑定士 | 時価 | 不動産売買、遺産分割 |
【ポイント】 遺産分割協議では、相続人全員が合意すればどの評価方法を用いても構いません。しかし、最も公平でトラブルになりにくいのは、実際に売却した場合の価格に近い「実勢価格」を基準にすることです。相続税の申告で用いた「相続税路線価」をそのまま使うケースもありますが、実勢価格とは開きがあるため、他の相続人から不満が出てしまう可能性もあります。
Q6. 評価するタイミングはいつ時点の価格ですか?「相続開始時」と「遺産分割時」で違うのですか?

A. 非常に重要なポイントです。相続税の計算では「相続開始時(亡くなった日)」の評価額を使いますが、遺産分割では「遺産分割時(話合いがまとまった日)」の評価額を基準にするのが一般的です。
不動産の価格は、社会情勢や周辺環境の変化によって常に変動しています。相続が発生してから遺産分割協議がまとまるまでには、数か月から数年かかることも珍しくありません。その間に不動産の価値が大きく上下することも考えられます。
例えば、相続開始時に3,000万円の価値だった土地が、再開発によって遺産分割時には5,000万円に値上がりしていた場合、「相続開始時」の3,000万円で計算すると、その土地を相続した人が不当に得をしてしまい、不公平になります。
そのため、公平な遺産分割を実現するためには、話合いがまとまった時点、つまり「遺産分割時」の時価(実勢価格)で評価することが最も望ましいとされています。
Q7. 不動産の価値を自分で調べる方法はありますか?
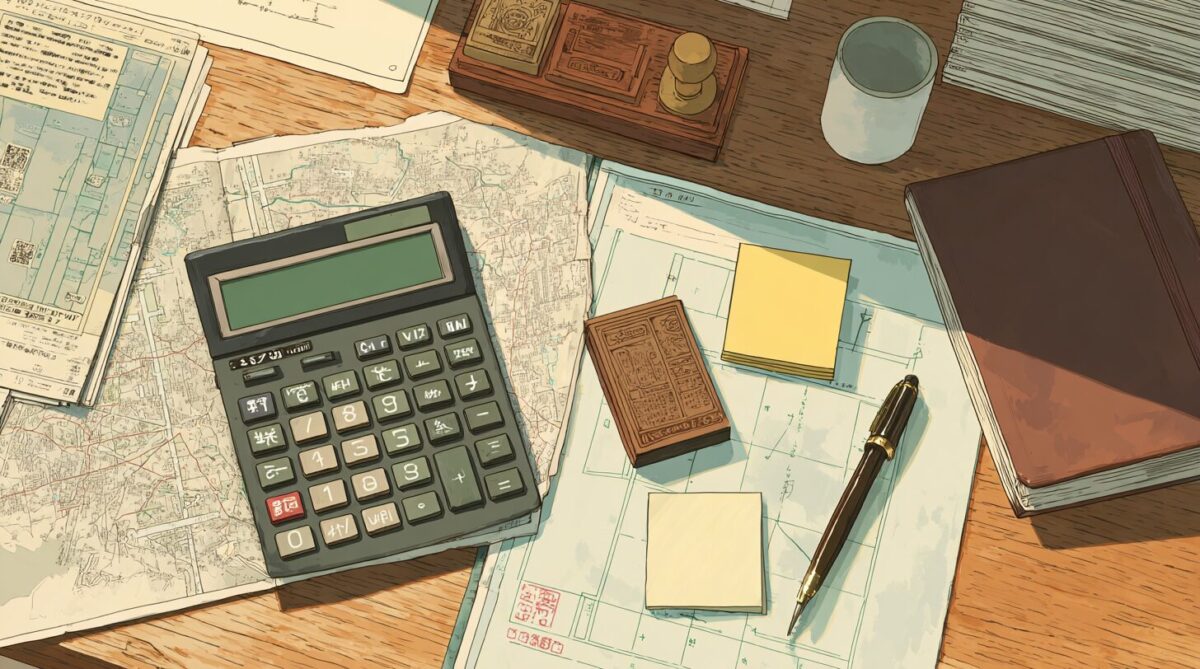
A. はい、ご自身で概算を把握する方法はいくつかあります。
- 固定資産税の納税通知書を確認する:毎年4月~6月頃に市町村から送られてくる納税通知書には、「価格」または「評価額」として固定資産税評価額が記載されています。これが一つの目安になります。
- 路線価図を調べる:国税庁のウェブサイトで公開されている「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」を見れば、相続税路線価を調べることができます。
- 不動産情報サイトで周辺の売出価格を調べる:SUUMOやLIFULL HOME’Sといった不動産ポータルサイトで、近隣の似たような物件がいくらで売りに出されているかを確認すれば、大まかな相場観を掴むことができます。
ただし、これらはあくまで概算です。特に路線価は、土地の形状や接道状況などの個別の要因が反映されていないため、実際の時価とは乖離が大きい場合があります。
Q8. 「査定」と「鑑定」はどう違うのですか?

A. 「査定」は不動産会社が行う価格についての”意見”、「鑑定」は不動産鑑定士が行う公的な”評価”です。
不動産会社の査定:
- 目的:主に売却を目的として、市場動向や取引事例をもとに「これくらいで売れるだろう」という価格(査定価格)を算出します。
- 費用:無料で行われることがほとんどです。
- 信頼性:あくまで不動産会社の意見であり、公的な証明力はありません。会社によって査定額にばらつきが出ることもあります。遺産分割で使う場合は、複数の不動産会社から査定を取り、その平均値を参考にするなどの工夫が必要です。
不動産鑑定士による鑑定評価:
- 目的:不動産の経済価値を客観的に判定し、公的な証明力を持つ「不動産鑑定評価書」を作成します。
- 費用:数十万円程度の費用がかかります。
- 信頼性:不動産鑑定評価基準という国の定めた基準に則って評価されるため、非常に信頼性が高く、税務署や裁判所に対しても強い証明力を持ちます。相続人間で評価額についての争いが大きい場合や、調停・審判に移行した場合には、鑑定評価が重要となります。
Q9. 不動産評価でよくある失敗や注意点は何ですか?

A. 次のような失敗が考えられます。よくある失敗や勘違いを知っておくことで、無用なトラブルを避けられます。
- 失敗例1:相続税評価額をそのまま遺産分割に使ってしまった
相続税の申告で使った路線価評価額を、安易に遺産分割でも使ってしまい、後から実勢価格との差を知った他の相続人から「不公平だ!」とクレームが入るケースです。 - 失敗例2:一つの不動産会社の査定額を鵜呑みにしてしまった
不動産会社によっては、売却の仲介契約を取りたいがために、相場より高い査定額を提示することがあります。その額を基準に遺産分割を進めると、いざ売却しようとした際に「そんな値段では売れない」という事態になりかねません。 - 失敗例3:共有名義にしたところ、後で揉めてしまった
公平のつもりで、とりあえず共有にして問題を先送りにした結果、いざ売却したいと思っても兄弟の一人が反対して売れなかったり、一部の相続人が亡くなってさらに権利関係が複雑化してしまったりするケースがあります。
【注意点・リスク】 不動産の評価は、単に計算すればよいというものではありません。相続人の感情的な対立が絡むと、どの評価方法を採用するかという点だけでも話合いが紛糾しがちです。また、評価額を巡る争いが長引けば、その間に不動産市場が変動し、売却のタイミングを逃してしまうリスクもあります。
Q10. 不動産の遺産分割を弁護士に依頼するメリットは何ですか?

A. 法律と交渉の専門家である弁護士が介入することで、スムーズで公平な解決を目指せます。
相続不動産の評価と分割は、法律、税金、不動産実務など、多岐にわたる専門知識が求められる非常に複雑な問題です。私たち弁護士にご依頼いただくことで、以下のようなメリットがあります。
- 最適な評価方法の提案:ご状況を詳しくお伺いした上で、相続人全員が納得できる、最も公平で合理的な評価方法をご提案します。必要に応じて、信頼できる不動産業者や不動産鑑定士をご紹介することも可能です。
- 冷静で有利な交渉:ご依頼者様の代理人として、感情的になりがちな当事者間の話し合いに入り、法的な根拠に基づいて冷静に交渉を進めます。相手方との直接のやり取りによる精神的な負担を大幅に軽減できます。
- 多様な分割方法の検討:不動産を売却して金銭で分ける「換価分割」、誰か一人が相続して他の相続人に代償金を支払う「代償分割」など、ご意向や不動産の特性に合わせた多様な分割方法を検討し、最善の解決策を導き出します。
- 法的手続きの代理:遺産分割協議書の作成はもちろん、話合いがまとまらない場合の家庭裁判所での調停や審判といった法的な手続きも、全てお任せいただけます。
まとめ
遺産分割における不動産の評価は、相続を円満に進めるための非常に重要なステップです。しかし、その方法は一つではなく、どの方法を選ぶかによって相続人間の利害が大きく対立することもあります。
「うちの場合は、どの評価方法がいいんだろう?」 「他の相続人に、どうやって評価額を提案すればいいか分からない…」 「すでに不動産の評価額で揉めてしまっている」
もし、あなたがこのような状況にあるのなら、問題を一人で抱え込まずに、私たち相続問題の専門家にご相談ください。蒼生法律事務所では、ご依頼者様のお気持ちに寄り添いながら、法律と不動産の両方の視点から、最善の解決策をご提案いたします。
初回のご相談は無料です。まずは、あなたの状況をお聞かせください。
蒼生法律事務所へのお問い合わせは、お電話またはウェブサイトのフォームから、お気軽にご連絡ください。
出典
- 財産評価基準書|国税庁, https://www.rosenka.nta.go.jp/
- No.4602 土地家屋の評価|国税庁, https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4602.htm
- 地方税制度|固定資産税 – 総務省, https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/150790_15.html

2004年の弁護士登録以降、個人・法人問わず幅広い事件を担当し、クライアントにとっての重大事には誠実かつ丁寧に寄り添う。命運に配慮し、最善策を模索。豊富な実績と十分なコミュニケーションで、敷居の高さを感じさせない弁護士像を追求してきた。1978年大阪府出身、京都大学法学部卒業。2011年に独立。不動産・労務・商事・民事・破産・家事など多様な分野を扱い、2024年6月に蒼生法律事務所へ合流。相続・遺言