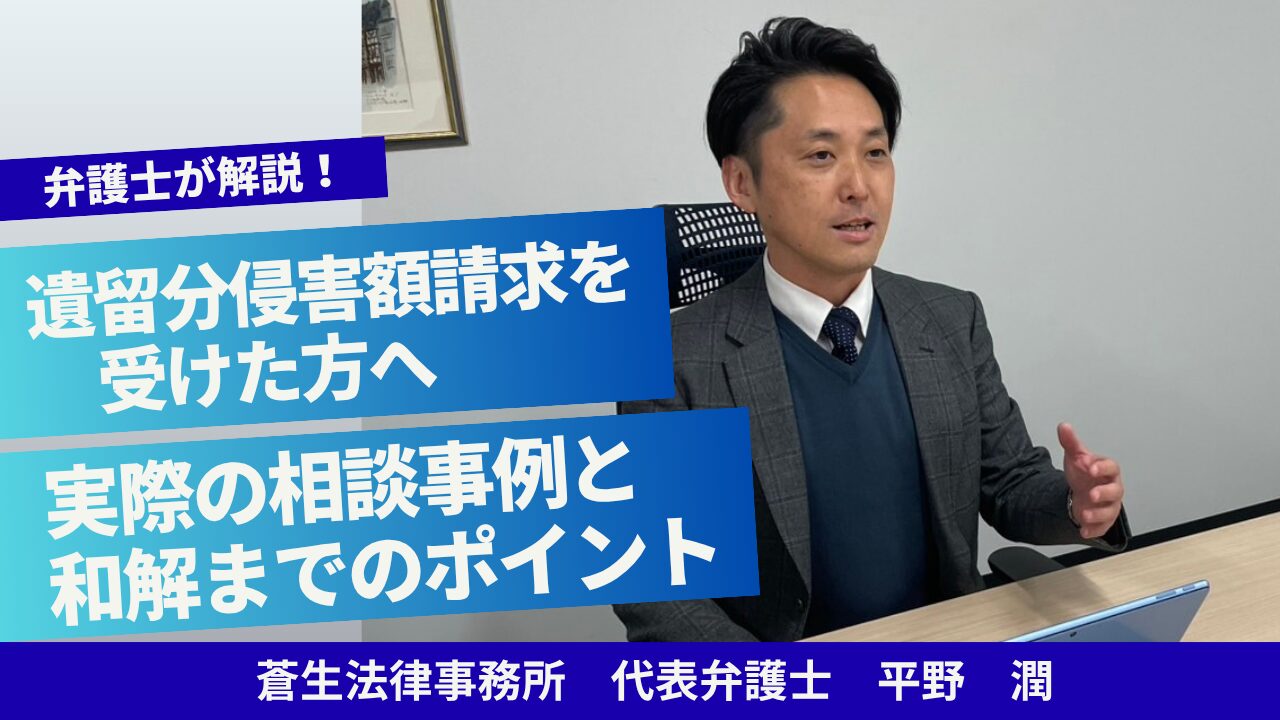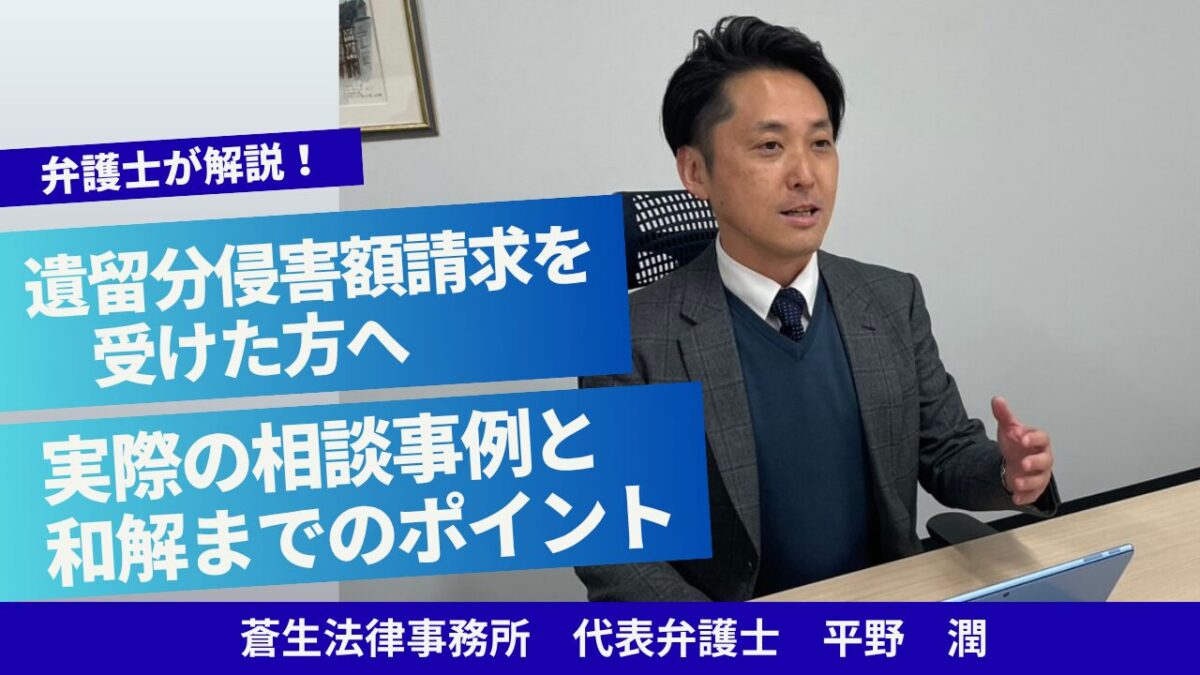
ある日突然、ご兄弟や他の親族から、内容証明郵便で「遺留分侵害額請求通知書」という物々しい書面が届く。 「父の遺言通りに遺産を相続しただけなのに、なぜ?」 「長年、親の面倒を見てきた貢献は無視されるのか?」 「こんな大金を、どうやって支払えばいいんだ…」
このように、遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう)の通知を受け取り、大きなショックと不安で当事務所にご相談に来られる方は後を絶ちません。
もしあなたが今、同じような状況に置かれているなら、まずは落ち着いてください。請求を無視することは最悪の選択ですが、慌てて相手の言い分を鵜呑みにする必要もありません。適切な初動対応が、その後の交渉を有利に進め、円満な解決に至るための鍵となります。
今回は、遺留分侵害額請求を「受けた側」の視点から、制度の基本、実際の相談事例、そして和解に至るまでの重要なポイントを、弁護士が分かりやすく解説します。
そもそも「遺留分」とは?

まず、この問題の根幹にある「遺留分」という制度についてご説明しますね。
遺留分とは、亡くなった方(被相続人)の兄弟姉妹を除く法定相続人に、法律上最低限保障されている遺産の取り分のことです。
例えば、お父様が「全財産を長男に相続させる」という遺言書を遺して亡くなったとします。遺言は故人の最終的な意思として尊重されるべきものですが、その内容によっては、残された他のご家族(例えば、次男や配偶者)の生活が成り立たなくなる可能性があります。
そこで、民法は、遺族の生活保障などの観点から、「遺言の内容にかかわらず、これだけは最低限もらえますよ」という権利を一部の相続人に認めているのです。これが遺留分の正体です。
2019年の民法改正により、この遺留分を侵害された場合、以前のように不動産などそのものを取り戻す(現物返還)のではなく、侵害された分に相当する「お金」で支払うよう請求する「遺留分侵害額請求」という形に変わりました。
【出典】
- 遺留分制度の概要や法改正については、法務省のウェブサイトが参考になります。
- 法務省: 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)
遺留分の権利があるのは誰?計算方法は?

では、誰に、どのくらいの遺留分が認められるのでしょうか。
- 遺留分の権利者(遺留分権利者)
配偶者、子(子が亡くなっている場合は孫などの代襲相続人)、直系尊属(父母や祖父母)です。 - ポイント:亡くなった方の兄弟姉妹には、遺留分はありません。
遺留分の計算方法(非常に簡略化したイメージです) 遺留分の計算は非常に複雑ですが、大まかな流れは以下の通りです。
- 基礎となる財産の確定:亡くなった時点のプラスの財産(預貯金、不動産など)に、一定期間内に行われた生前贈与などを加算して、遺留分を計算するための元となる財産額を算出します。
- 全体の遺留分割合を計算:基礎財産に、法律で定められた割合(相続人が配偶者や子の場合は2分の1、父母などの直系尊属のみの場合は3分の1)を掛け合わせます。
- 個人の遺留分額を計算:上記で計算した全体の遺留分額に、各相続人の法定相続分を掛け合わせます。これが、その人の本来の遺留分額です。
- 侵害額の確定:本来の遺留分額から、その人が実際に相続したり、生前贈与で受け取ったりした財産額を差し引きます。それでも不足する分が「遺留分侵害額」として請求できる金額になります。
この計算、特に「生前贈与をどこまで含めるか」「不動産や自社株の評価額をいくらにするか」といった点で争いになることが多く、専門的な知識や経験が非常に重要となります。
弁護士が語る!遺留分トラブル・よくある3つの相談事例
言葉だけではイメージしにくいと思いますので、当事務所でよくお受けする相談事例を3つご紹介します。
ケース1:「事業承継」で自社株と工場を相続した経営者のケース
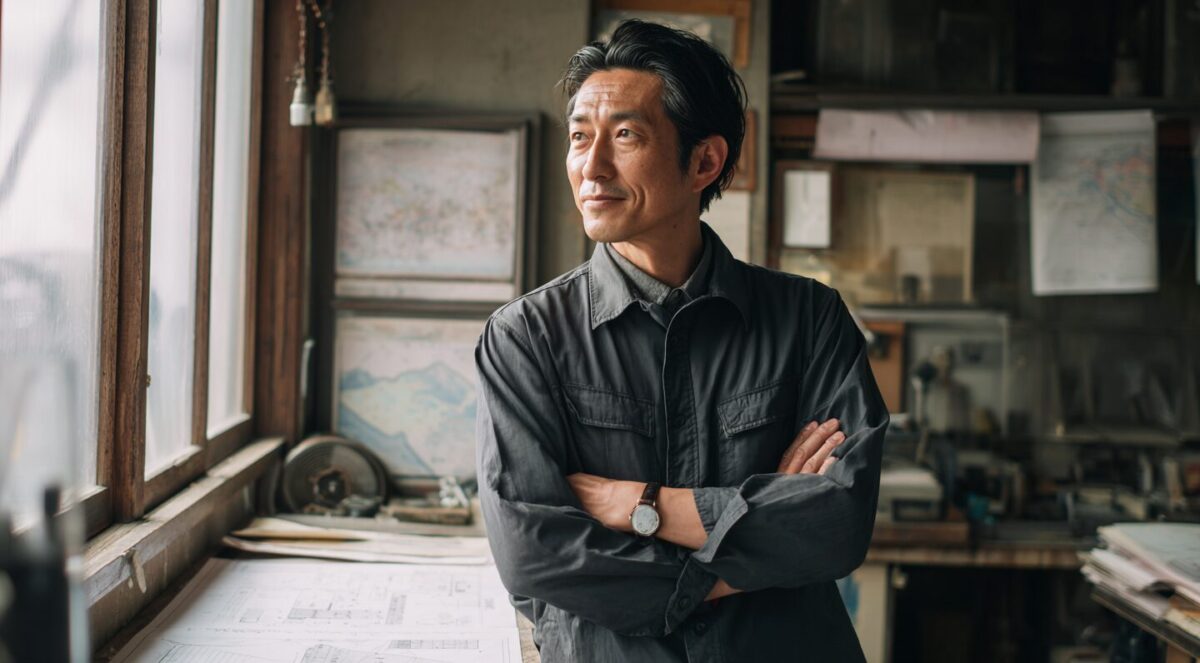
会社経営者だった父が亡くなり、「事業の後継者である長男に、自社株と事業用の不動産(工場・本社ビル)のすべてを相続させる」という遺言がありました。長男は遺言通りに相続しましたが、しばらくして海外に住む弟(次男)の代理人弁護士から、数千万円の遺留分侵害額請求を受けました。
- 長男の言い分:「父の会社を守るために必要なことだ。弟は昔から会社に無関心だったのに、今さら金だけ要求するなんて許せない!」
- ポイント:事業承継のための遺贈は遺留分トラブルの典型例です。自社株や事業用不動産の評価額が非常に高額になり、請求額も大きくなりがちです。
ケース2:「親の介護」を一身に担い、実家を生前贈与されたケース

長年にわたり、同居して母親の介護を一身に担ってきた長女。母親は感謝の気持ちとして、生前に自宅不動産を長女に贈与しました。母親が亡くなった後、遠方に住み、介護にはほとんど関わってこなかった他の兄弟から、「その生前贈与は不公平だ」として遺留分侵害額請求の通知が届きました。
- 長女の言い分:「他の兄弟は何もしてくれなかった。私がどれだけ大変な思いをして母の面倒を見てきたか知らないくせに…!」
- ポイント:介護などの貢献(寄与分)と、特定の相続人への多額の贈与(特別受益)が絡み合う複雑なケースです。感情的な対立が激しくなりやすい傾向があります。
ケース3:「内縁の妻」に全財産を遺贈する遺言があったケース

長年連れ添った内縁の妻(籍は入れていないパートナー)に、男性が「全財産を遺贈する」という遺言を遺して亡くなりました。しかし、男性には前妻との間に子供がおり、その子供から内縁の妻に対して遺留分侵害額請求がなされました。
- 内縁の妻の言い分:「何十年も連れ添い、身の回りのお世話をしてきたのは私。法律上の妻ではないというだけで、何ももらえないのはおかしい」
- ポイント:相続人ではない第三者への遺贈も、遺留分侵害の対象となります。請求された側は、故人との生活実態などを主張しますが、法律上の権利である遺留分に対抗するのは簡単ではありません。
これらのケースのように、請求された側には「故人の意思なのに」「自分が貢献したのに」といった正当な理由や感情があります。しかし、遺留分は法律で定められた強力な権利であり、感情論だけで対抗することは難しいのが現実です。
通知が届いたら?調停・訴訟の流れと、和解への分岐点

では、実際に請求の通知書が届いたら、どのように対応すべきでしょうか。
ステップ1:通知内容の精査【最初の分岐点】
まず、絶対に無視してはいけません。無視を続けると、相手方は家庭裁判所に調停を申し立て、最終的には訴訟に移行します。そうなると、時間も費用も余計にかかってしまいます。
届いた書面を見て、以下の点を確認する必要があります。
- 請求は正当か?:相手にそもそも遺留分の権利があるか?請求の時効(相続開始と遺留分侵害を知った時から1年、または相続開始から10年)は過ぎていないか?
- 請求額は妥当か?:計算の基礎となる財産のリストや評価額は正しいか?特に不動産や非上場株式の評価額は、相手方が自分に有利な高い金額を提示してきている可能性があります。
この段階で、弁護士に相談し、相手の請求が法的に妥当なものかを見極めることが、最初の重要な分岐点です。
ステップ2:交渉
相手方の請求に反論の余地があれば、それを指摘し、減額を求めて交渉します。例えば、「不動産の評価額が高すぎる」「計算に含まれていない負債がある」「自分には介護などの貢献(寄与分)があるため考慮してほしい」といった主張を行います。
ステップ3:遺留分侵害額請求調停
当事者間での交渉がまとまらない場合、通常、請求者側が家庭裁判所に「調停」を申し立てます。調停は、裁判官と民間の有識者からなる調停委員が間に入り、話し合いによる解決を目指す手続きです。訴訟と違って非公開で行われ、柔軟な解決が期待できます。
【出典】
- 調停手続きの詳細は、裁判所のウェブサイトで確認できます。
- ページ名:遺留分侵害額の請求調停 | 裁判所
ステップ4:訴訟
調停でも合意に至らない場合、最終手段として「訴訟」に移行します。訴訟では、公開の法廷でお互いの主張と証拠を出し合い、最終的に裁判官が判決を下します。判決には強制力がありますが、解決までには1年以上、時には数年かかることも覚悟しなければなりません。
請求された側の注意点と、よくある間違い
- ✕ 安易に支払いを約束する
動揺して、電話などで「分かりました、払います」などと安易に約束しないでください。その会話が録音されていると、後で不利な証拠になり得ます。 - ✕ 感情的に相手を非難する
「お前は親不孝者だ!」などと感情的に相手を責めても、問題は解決しません。むしろ交渉がこじれる原因になります。冷静に、法的な観点から対応することが重要です。 - ✕「遺言書は絶対」という勘違い
「故人の意思が書かれた遺言書は絶対だ」と信じている方が多いですが、その遺言書をもってしても侵害できないのが遺留分です。この法的な力関係を理解しておく必要があります。
悩んだらすぐに弁護士へ。弁護士に依頼するメリットとは?

遺留分侵害額請求は、時間との勝負であり、専門知識・経験の有無が結果を大きく左右します。請求を受けたら、できるだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士にご依頼いただくことで、以下のようなメリットがあります。
- 法的な反論の糸口を見つけられる:相手の請求額が不当に高くないか、財産評価は適正か、こちらから寄与分などを主張できないか、専門家の目で厳しくチェックします。
- 交渉の窓口となり、精神的負担を軽減:相手方との直接のやり取りはすべて弁護士が引き受けます。感情的な対立からあなたを守り、冷静な交渉を実現します。
- 適正な財産評価の実現:必要であれば、不動産鑑定士や税理士と連携し、相手方の提示する不当な評価額に対抗し、請求額の減額を目指します。
- 調停や訴訟での代理活動:法的な手続きに移行した場合も、あなたの代理人として、有利な和解や判決を得るために最善を尽くします。
- 支払い方法の交渉:一括での支払いが難しい場合、分割払いや不動産での代物弁済など、現実的な支払い方法を相手方と交渉します。
終わりに:一人で抱え込まず、まずはご相談ください
遺留分侵害額請求という突然の出来事に、今は目の前が真っ暗に感じているかもしれません。しかし、正しい知識を持ち、適切な手順を踏めば、必ず解決の道筋は見えてきます。重要なのは、一人で抱え込み、問題をこじらせてしまう前に、専門家の助けを求めることです。
蒼生法律事務所では、相続・遺留分の問題に関する初回のご相談は無料です。「弁護士に相談するのは大事(おおごと)だ」とためらわずに、まずは現状をお聞かせください。私たちがあなたの状況を整理し、これから何をすべきか、どのような解決策が考えられるかを丁寧にご説明します。
その通知書を握りしめて悩む前に、まずはお気軽にお問い合わせください。

2004年の弁護士登録以降、個人・法人問わず幅広い事件を担当し、クライアントにとっての重大事には誠実かつ丁寧に寄り添う。命運に配慮し、最善策を模索。豊富な実績と十分なコミュニケーションで、敷居の高さを感じさせない弁護士像を追求してきた。1978年大阪府出身、京都大学法学部卒業。2011年に独立。不動産・労務・商事・民事・破産・家事など多様な分野を扱い、2024年6月に蒼生法律事務所へ合流。相続・遺言