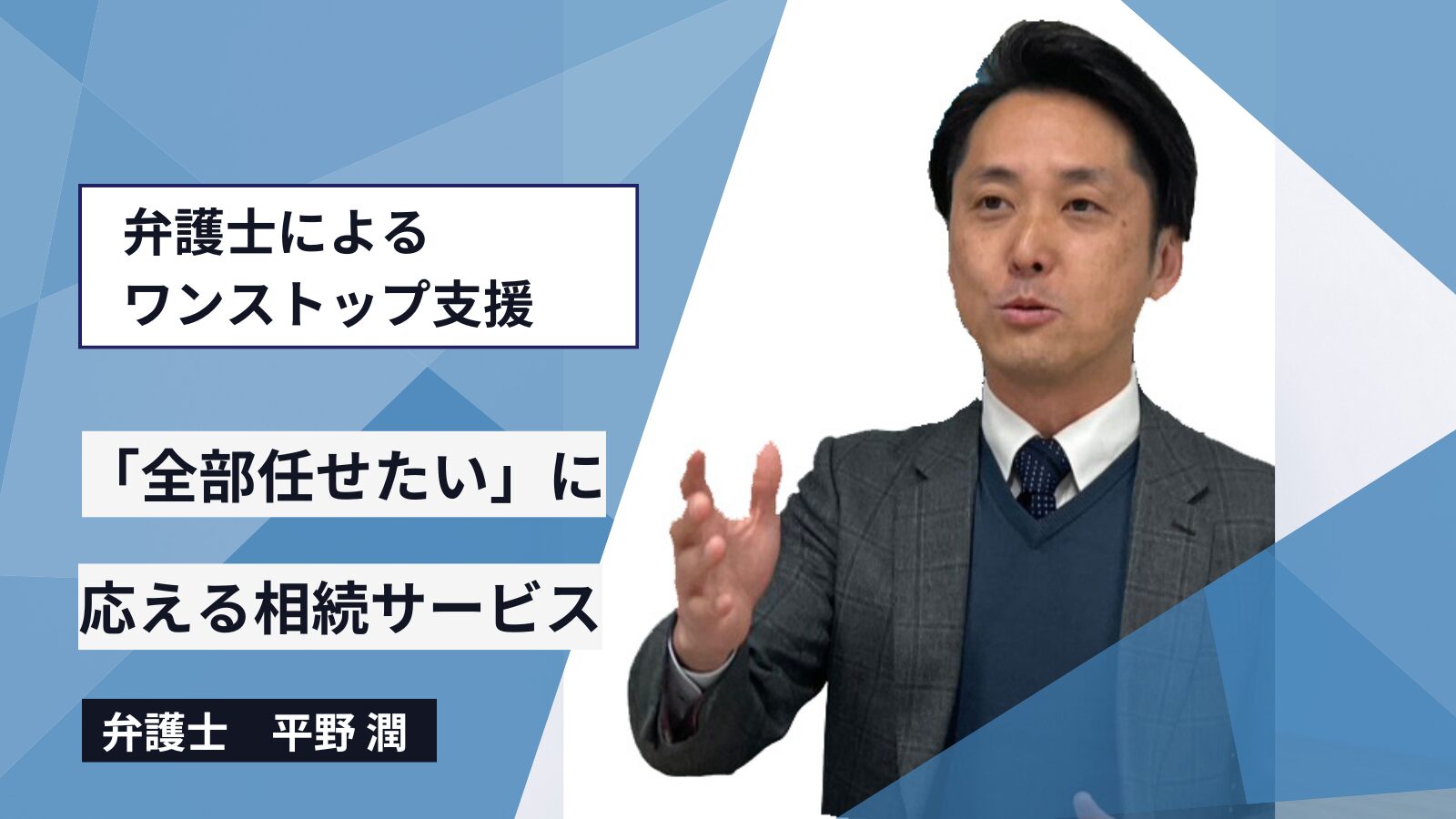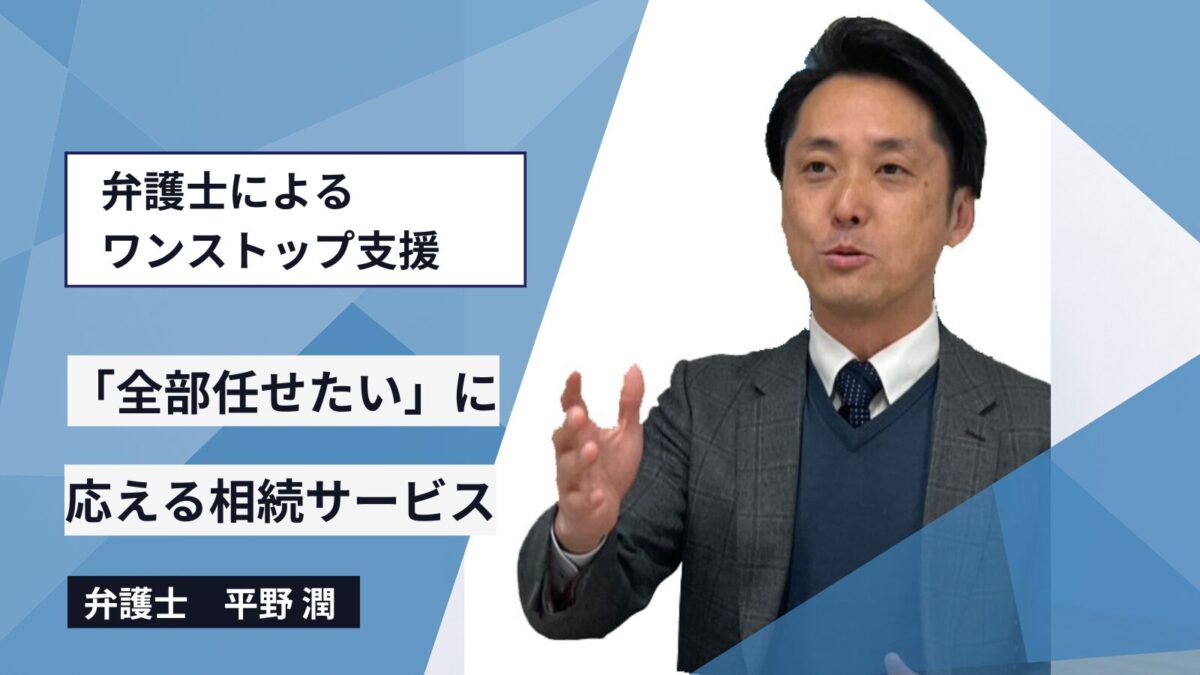
皆様、こんにちは。
蒼生(そうせい)法律事務所、代表弁護士の平野 潤(ひらの じゅん)です。
この度は、私たちのブログをお読みいただき、ありがとうございます。
大切なご家族が亡くなられたとき、深い悲しみの中で、様々な手続きに追われることになります。しかし、相続は人生で何度も経験するものではないため、「何から手をつけていいのか分からない」「やるべきことが多すぎてパニックになってしまう」という方がほとんどではないでしょうか。
「疎遠だった兄弟にも連絡しないといけないの?」
「父さんに借金があったらどうしよう…」
「銀行や役所の手続き、平日は仕事で休めない…」
このようなお悩みやご不安を抱え、当事務所の扉を叩かれる方は後を絶ちません。実は、相続手続きは皆様が想像されている以上にやることが多く、時間も手間もかかる、非常に複雑で骨の折れる作業なのです。
しかし、ご安心ください。その煩雑で専門的な手続きのすべてを、専門家である私たち弁護士にまとめてお任せいただける「相続手続 丸ごと代行サービス」があることをご存知でしょうか。
今回の記事では、相続手続きの全体像を追いながら、なぜ専門家に「全部任せる」ことが最善の選択肢となり得るのか、具体的なケースを交えて、分かりやすく解説していきたいと思います。相続という大きな課題を前に、一筋の光を見出すきっかけとなれば幸いです。ぜひ、最後までお付き合いください。
相続手続きの全体像 – なぜ「全部任せたい」と思うほど大変なのか?
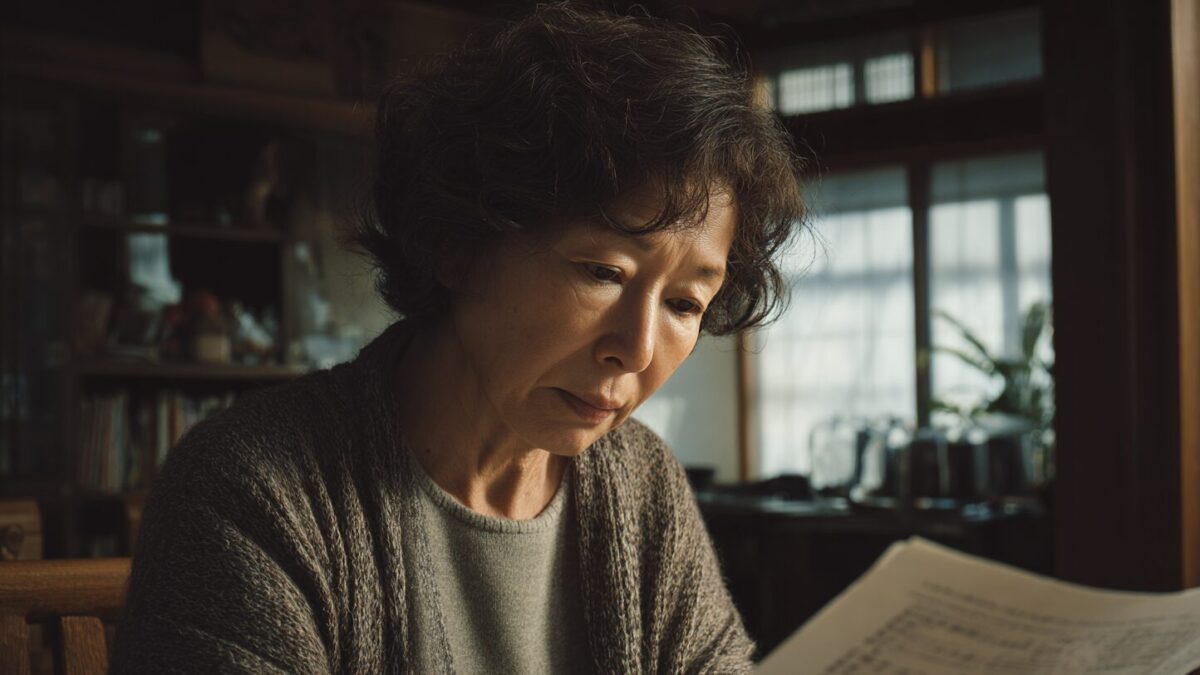
まず、相続が発生してから完了するまでの、大まかな流れを見てみましょう。
| 相続人の調査 | 「誰が相続する権利を持っているのか」を確定させます。 |
|---|---|
| 相続財産の調査 | 「何を相続するのか(プラスもマイナスも)」をすべて洗い出します。 |
| 遺産分割協議 | 相続人全員で「誰が何を相続するのか」を話し合い、合意します。 |
| 各種名義変更 | 預貯金の解約、不動産の登記、株式の名義書換などを行います。 |
| 相続税の申告・納付 | 財産額に応じて、相続税を計算し、税務署に申告・納付します。 |
相続税の申告・納付:財産額に応じて、相続税を計算し、税務署に申告・納付します。
これらの手続きには、それぞれ期限が設けられています。例えば、相続放棄の判断は3ヶ月以内、相続税の申告・納付は10ヶ月以内と、悲しみに暮れている間にも時間は刻一刻と過ぎていきます。
これら膨大なタスクを、ご自身の仕事や家事、育児をこなしながら、不慣れな法律や税金について調べ、平日の昼間に何度も役所や金融機関に足を運ぶ…そのご負担は計り知れません。だからこそ、多くの方が「専門家に全部任せたい」と感じられるのです。
それでは、各ステップで具体的にどのような壁が待ち受けているのか、詳しく見ていきましょう。
【ステップ1】「誰が相続人?」- 意外と知らない家族の存在(相続人調査)

相続手続きのスタートは、「誰が相続人なのか」を法的に確定させる「相続人調査」です。これを怠ると、後々の手続きが全て無駄になってしまう可能性があるため、非常に重要なステップです。
-
なぜ相続人調査が必要?
遺産の分け方を決める「遺産分割協議」は、相続人全員の参加と合意がなければ法的に無効となります。もし一人でも相続人が漏れていた場合、せっかくまとまった協議を全てやり直さなければなりません。
-
調査は想像以上に大変
相続人を確定させるには、故人の「出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本も含む)」をすべて取得する必要があります。本籍地が何度も変わっている方の場合、全国各地の役所に請求をかけることになり、これだけでも大変な作業です。
そして、この戸籍を読み解く中で、ご遺族が知らなかった事実が判明することも少なくありません。
ケース1:両親の離婚・再婚で疎遠だった家族
「父は母と結婚する前に一度離婚しているらしい…」という場合、前妻との間にお子さんがいれば、その方も現在の家族と同じく法律上の相続人です。何十年も会っていなくても、連絡を取って遺産分割協議に参加してもらう必要があります。また、ご両親が離婚し、親権者となった母に引き取られた子も、当然、離れて暮らす父の相続人となります。
ケース2:婚外子や認知していないかもしれない子
故人が婚姻関係にない女性との間に子をもうけ、その子を「認知」していた場合、その子も相続人となります。遺言書で初めてその存在を知ったり、亡くなった後に認知を求める訴えが起こされたりするケースもあります。
ケース3:養子縁組
故人が誰かを養子にしていた場合、その養子も実子と同じ相続権を持ちます。戸籍を丹念に追わなければ、養子縁組の事実に気づかないこともあります。
弁護士に依頼するメリット
私たち弁護士は、職務上の権限で戸籍謄本等をスムーズに収集することができます。皆様が全国の役所に個別に連絡する手間は一切ありません。そして、収集した難解な戸籍を正確に読み解き、法的に誰が相続人となるのかを確定させ、分かりやすい「相続関係説明図」を作成します。疎遠な相続人がいる場合も、弁護士が代理人として冷静かつ中立的な立場で連絡を取り、円滑な話し合いをサポートします。
【ステップ2】「何がある?」- プラスもマイナスも全部見つける(相続財産調査)

相続人が確定したら、次は「何を相続するのか」を調べる「相続財産調査」です。プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金など)もすべて洗い出す必要があります。
調査対象となる財産の例
| 預貯金 | 全ての取引金融機関を特定し、残高証明や取引履歴を取得します。 |
|---|---|
| 不動産 | 自宅、土地、マンション、農地、山林など。名寄帳や登記簿謄本で確認します。 |
| 有価証券 | 上場株式、投資信託、非公開株式など。 |
| その他 | ゴルフ会員権、リゾート会員権、生命保険、自動車、美術品、骨董品、暗号資産、海外資産など。 |
これら多種多様な財産を、漏れなく、かつ正確に評価していくのは至難の業です。特に、非公開株式や美術品、海外資産などは、評価に高度な専門知識を要します。
忘れてはならない「借金」の調査
最も注意すべきなのが、借金やローン、誰かの保証人になっているといった「マイナスの財産」の存在です。もしプラスの財産よりマイナスの財産のほうが多い場合、相続人は「相続放棄」という選択をすることができます。
しかし、この相続放棄の手続きは、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内」に家庭裁判所に申述しなければなりません。
出典: 相続の放棄の申述(裁判所)
財産調査が遅れ、この3ヶ月の期間(熟慮期間)を過ぎてしまうと、故人の借金をすべて背負わなければならなくなる可能性があります。
弁護士に依頼するメリット
私たちは、弁護士法23条に基づく「弁護士会照会」などの強力な調査権限を駆使して、ご遺族が把握していない財産も網羅的に調査します。信用情報機関への照会により、借金の有無も迅速に確認できます。万が一、多額の負債が見つかった場合でも、相続放棄や、プラスの財産の範囲内でのみ借金を返済する「限定承認」といった手続きについて、皆様の状況に合わせた最適なアドバイスと手続きの代行が可能です。
【ステップ3&4】「どうする?」- 遺産分割から面倒な名義変更まで

相続人と財産が確定したら、いよいよ「誰が」「何を」「どれだけ」相続するのかを、相続人全員で話し合います。これが「遺産分割協議」です。
合意した内容は「遺産分割協議書」という法的な書面にまとめ、相続人全員が署名・実印を押します。この協議書が、その後のあらゆる名義変更手続きの根拠となります。
立ちはだかる、煩雑な名義変更の壁
| 銀行手続き | 金融機関ごとに異なる書式、膨大な量の書類への署名・捺印。 窓口で何度もダメ出しをされ、心が折れそうになる方も少なくありません。 |
|---|---|
| 不動産相続登記 | 法務局で不動産の名義を故人から相続人へ変更します。 これは専門知識が必要な上、2024年4月1日から義務化され、正当な理由なく怠ると過料が科される可能性もあります。 |
| 株式の名義変更 | 証券会社や、非公開株式の場合は発行会社との間で、株主名簿の書換請求を行います。 |
「とりあえず共有」が招く、将来のトラブル

不動産などを「とりあえず兄弟の共有名義にしておこう」と安易に決めてしまうのは非常に危険です。
将来、その不動産を売却したり、家を建て替えたりするには、基本的に共有者全員の同意が必要になります。もし共有者の一人が認知症になったり、亡くなってさらにその相続人(甥や姪など)に権利が移ったりすると、関係者はネズミ算式に増えるなど、話し合いは困難を極めます。
このような共有状態を解消するための「共有物分割請求」という裁判手続きもありますが、時間も費用もかかり、親族間の亀裂を深めることにもなりかねません。
弁護士に依頼するメリット
私たちは、皆様の代理人として、全ての金融機関や役所とのやり取り、書類作成を代行します。
皆様が平日の昼間に時間を割く必要は一切ありません。
また、将来のトラブルの種にならないよう、各ご家庭の事情に合わせた最適な遺産分割案をご提案し、法的に有効な遺産分割協議書を作成します。
不動産登記は提携の司法書士と、共有物分割が争点になる場合は法的な代理人として、あらゆる手続きをワンストップで、かつ最善の形で進めることができます。
【ステップ5】「税金は?」- 期限は10ヶ月!でも使える控除も(相続税申告)

相続財産の総額が一定額を超える場合、相続税の申告と納付が必要になります。
申告・納付期限は「10ヶ月」
相続税の申告・納付期限は「相続の開始があったことを知った日の翌日から10箇月以内」です。
これは想像以上に短く、相続人調査や財産調査、遺産分割協議が長引けば、あっという間に期限が迫ってきます。
相続税がかかるかどうかの目安
相続税には「基礎控除」という非課税枠があります。この額を超える部分にのみ、相続税がかかります。
基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)
例えば、相続人が妻と子2人(計3人)の場合、3,000万円 + (600万円 × 3人) = 4,800万円が基礎控除額となります。遺産の総額がこの額以下であれば、原則として相続税の申告は不要です。
知っているかどうかで大違い!税金の特例
相続税には、納税者の負担を軽減するための様々な特例や控除があります。
| 配偶者の税額軽減 | 配偶者が相続した財産のうち、1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額までは相続税がかからない制度。 |
|---|---|
| 生命保険金の非課税枠 | 故人が契約していた生命保険金は、「500万円 × 法定相続人の数」までは非課税となります。 |
| 小規模宅地等の特例 | 故人の自宅や事業用の土地を相続した場合、その土地の評価額を最大80%減額できる強力な特例。 |
これらの特例を適用するには、複雑な要件を満たした上で、相続税の申告書を提出する必要があります。
弁護士に依頼するメリット
私たちは、相続案件に精通した税理士と緊密に連携しています。
弁護士が法的な問題を整理し、税理士が税務の専門家として正確な財産評価と税額計算を行うことで、適用可能な特例を漏れなく活用し、皆様にとって最も有利な形での相続税申告を実現します。
税務調査が入った場合も、私たちが窓口となって毅然と対応しますのでご安心ください。
まとめ:大切な時間を、手続きではなく、故人を偲ぶために

ここまでお読みいただき、相続手続きがいかに広範囲で、専門的で、時間のかかるものであるか、お分かりいただけたかと思います。
遺産相続というものは、法的な手続きであると同時に、ご家族にとっては故人を偲び、これからのことを考えるための大切な時間です。
その貴重な時間を、煩雑な書類集めや役所とのやり取りに費やしてしまうのは、あまりにもったいないことです。
私たち蒼生法律事務所の「相続手続 丸ごと代行サービス」は、皆様をその全ての煩わしさから解放し、心穏やかに故人様と向き合う時間を取り戻していただくためのサービスです。
相続人や財産の調査から、遺産分割協議、各種名義変更、相続税申告まで、全てをワンストップでお任せいただけます。
弁護士が総合窓口となり、必要に応じて司法書士や税理士といった各分野の専門家と連携し、チーム一丸となって皆様の相続をサポートします。
将来起こりうるトラブルを未然に防ぎ、ご家族全員が納得できる円満な相続の実現を目指します。
「何から相談すればいいか分からない」
「うちの場合は、弁護士に頼むほどのことだろうか?」
どうか、一人で抱え込まないでください。どのような些細なことでも構いません。
まずは、あなたが今、何に悩み、何に不安を感じているのかを、私たちにお聞かせください。問題がこじれてしまう前にご相談いただくことが、スムーズな解決への何よりの近道です。
蒼生法律事務所では、相続に関する初回のご相談を無料で承っております。私、平野が、皆様のお話をじっくりと伺い、進むべき道を照らす「羅針盤」となります。
あなたからのお問い合わせを、心よりお待ちしております。

2004年の弁護士登録以降、個人・法人問わず幅広い事件を担当し、クライアントにとっての重大事には誠実かつ丁寧に寄り添う。命運に配慮し、最善策を模索。豊富な実績と十分なコミュニケーションで、敷居の高さを感じさせない弁護士像を追求してきた。1978年大阪府出身、京都大学法学部卒業。2011年に独立。不動産・労務・商事・民事・破産・家事など多様な分野を扱い、2024年6月に蒼生法律事務所へ合流。相続・遺言