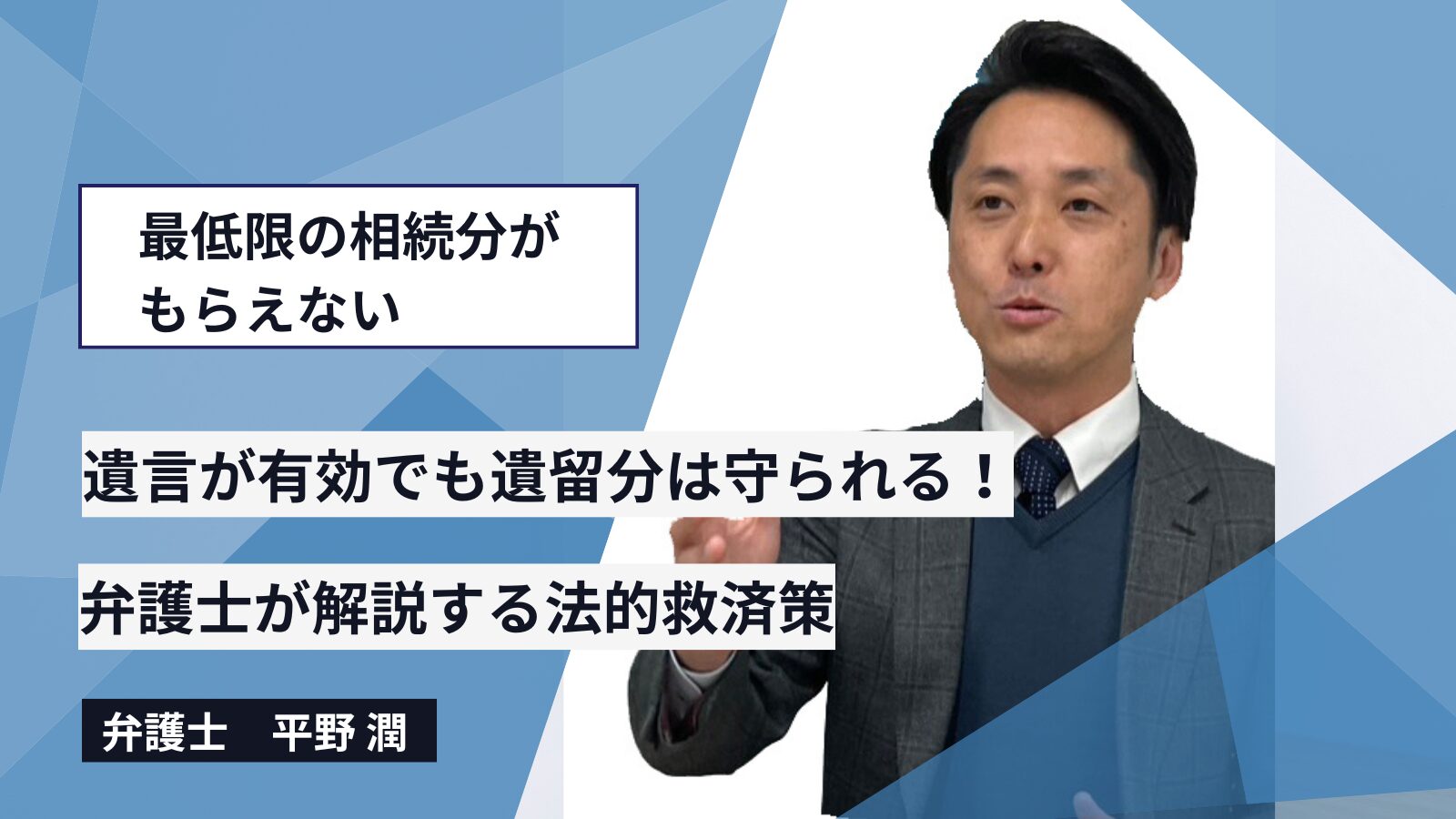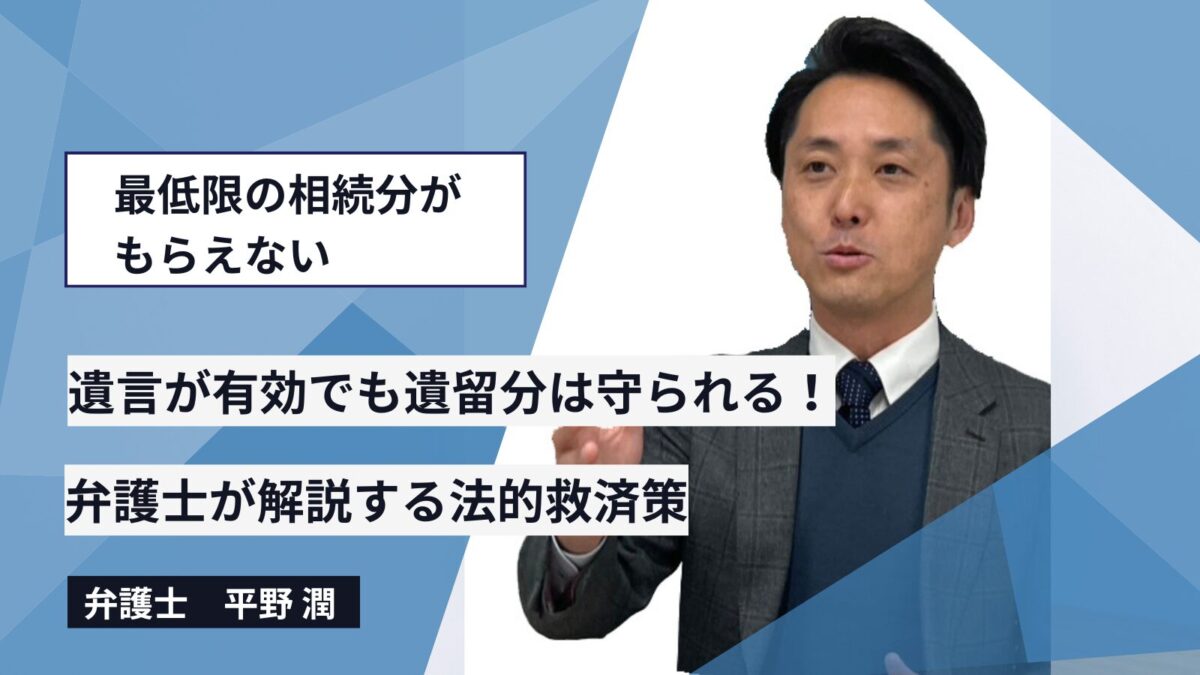
皆様、こんにちは。
蒼生(そうせい)法律事務所、代表弁護士の平野 潤(ひらの じゅん)です。
この度は、数ある法律事務所のサイトの中から、私たちのブログをお読みいただき、誠にありがとうございます。
「父が残した遺言書を開いてみたら、全財産を長男である兄に相続させると書かれていた…」
「母は、晩年お世話になったからと、全財産を特定の病院に遺贈(いぞう)する、と書き残していた。私たち子供には何も残されていないのだろうか…」
「内縁の妻に全ての財産を譲るとの遺言が。長年連れ添ったとはいえ、内縁の妻には法的に何の権利もないはずなのに。私たちは、ただ黙って受け入れるしかないの?」
大切なご家族を亡くされた悲しみの中、ようやく見つかった遺言書にこのような内容が書かれていたとしたら、その衝撃と戸惑いは計り知れません。「故人の最後の意思だから尊重したい」という気持ちと、「でも、私たちのこれからの生活はどうなるの?」という現実的な不安との間で、心が引き裂かれるような思いをされることでしょう。
もし、あなたが今、そのような状況に置かれているのだとしたら、どうかこの記事を最後までお読みください。
ご安心ください。法律は、故人の意思を尊重すると同時に、残されたご家族の生活を守るための「最後の砦」ともいえる制度をちゃんと用意しています。それが「遺留分(いりゅうぶん)」という権利です。
今回の記事では、あまりにも不公平な遺言を前に、泣き寝入りしないための対抗策について、専門家の視点から、分かりやすく解説していきます。あなたの正当な権利を取り戻すための、最初の一歩を踏み出すお手伝いができれば幸いです。
ステップ1:そもそも、その遺言は法的に「有効」ですか?

遺言(遺言書)の内容に憤りを感じたとき、まず検討すべきは、「遺留分」の前に、「その遺言書自体が、法的に有効なものなのか?」という点です。もし遺言が無効であれば、その遺言は初めからなかったことになり、相続人全員で遺産分割協議を行うことになるからです。
遺言が無効になるケースは、大きく分けて2つあります。
ケース1:形式的な不備がある場合
遺言には、法律で厳格な形式が定められています。特に、ご自身で書かれる「自筆証書遺言」は、以下の要件を一つでも欠くと無効になってしまいます。
- 全文が自筆であること(パソコンや代筆はNG)(ただし、添付する財産目録はパソコンOK)
- 作成した日付が明確に記載されていること(「令和7年吉日」などはNG)
- 氏名が自署されていること
- 押印があること(認印でも可ですが、実印が望ましい)
出典: 自筆証書遺言(民法第968条)(e-Gov法令検索)
これらの形式が守られていない遺言は、たとえ故人の意思が明確に書かれていても、法的には効力を持ちません。まずは、遺言書がこの形式を満たしているかを冷静に確認することが重要です。
ケース2:内容的な問題(遺言能力の欠如)がある場合
形式は整っていても、遺言を作成した当時、故人に「遺言能力」がなかったと判断されれば、遺言は無効となります。「遺言能力」とは、簡単に言えば、「自分がどのような内容の遺言を書き、それによってどのような法的な結果が生じるのかを、正しく理解・判断できる能力」のことです。
特に問題となるのが、故人が認知症などを患っていたケースです。
「遺言書が作られた時期、父はかなり認知症が進んでいたはずだ…」
「成年後見人をつけるかどうかの話し合いをしていた矢先に、公正証書遺言が作られていたことが分かった…」
ただし、「認知症だった=即、遺言は無効」となるわけではありません。認知症の症状には波があり、作成当時に一時的に判断能力が回復していた可能性もあるからです。
遺言能力の有無を争うには、客観的な証拠が不可欠です。
| 医療記録(カルテ)や介護記録 | 遺言作成日時の前後の、医師の診断や介護士の記録は極めて重要な証拠です。 長谷川式認知症スケール(HDS-R)やミニメンタルステート検査(MMSE)などのテスト結果 |
| 故人の生前の言動 | 日記や手紙、周囲の人々の証言など。 |
弁護士に依頼するメリット
遺言の有効性を争う「遺言無効確認訴訟」は、非常に専門的な手続きです。私たちは、法律の専門家として、遺言書の形式的な不備を的確に指摘します。また、遺言能力が争点となる場合は、弁護士会照会制度などを利用して病院や介護施設から記録を取り寄せ、医学的な証拠を分析し、皆様の代理人として法廷で故人の当時の状況を主張・立証します。
ステップ2:残された家族の最後の砦「遺留分」とは何か?

遺言が無効だと主張するのが難しい場合、あるいは遺言自体は有効だと認めざるを得ない場合でも、まだ諦める必要はありません。ここからが、本題である「遺留分」の出番です。
「遺留分」とは、一言でいえば、「法律によって、相続人に最低限保障されている遺産の取り分」のことです。
故人は原則として、遺言によって自分の財産を誰に、どれだけ渡すかを自由に決めることができます(遺言自由の原則)。しかし、その自由も無制限ではありません。故人の財産は、故人一人の力で築かれたものではなく、家族の協力や支えがあってこそ形成・維持されたものである、という考え方に基づき、法律は残された家族の生活保障や期待を保護するために、この「遺留分」という制度を設けているのです。
誰に遺留分があるのか?(遺留分権利者)
ここで非常に重要なポイントがあります。遺留分は、全ての相続人に認められているわけではありません。
| 遺留分が【ある】相続人 | 配偶者、子(子が亡くなっている場合は孫などの代襲相続人)、直系尊属(父母や祖父母) |
| 遺留分が【ない】相続人 | 兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥・姪) |
つまり、故人に子がおらず、両親もすでに亡くなっている場合、相続人となる兄弟姉妹には遺留分がありません。したがって、「全財産を愛人に遺贈する」という遺言があった場合、兄弟姉妹はそれに異議を唱えることができないのです。この点は、ぜひ正確に覚えておいてください。
出典: 遺留分の帰属及びその割合(民法第1042条)(e-Gov法令検索)
どれくらいの割合がもらえるのか?
遺留分の割合は、法定相続分とは異なります。まず、相続人全体で保障される割合(総体的遺留分)が決まっています。
- 相続人が直系尊属(父母など)のみの場合 → 遺産の3分の1
- それ以外の場合(配偶者や子が含まれる場合) → 遺産の2分の1
そして、各相続人の個別の遺留分は、この全体の割合に、各自の法定相続分を掛け合わせて算出します。
【例】相続人が妻と子2人(計3人)、遺産総額が6,000万円の場合
- 全体の遺留分割合:配偶者と子なので2分の1です。 遺産総額6,000万円 × 1/2 = 3,000万円
- 各人の法定相続分:妻が1/2、子がそれぞれ1/4です。
●各人の遺留分
- 妻:3,000万円 × 1/2 = 1,500万円
- 子1:3,000万円 × 1/4 = 750万円
- 子2:3,000万円 × 1/4 = 750万円
この金額が、法律によって最低限保障されている取り分となります。
ステップ3:「私の遺留分を返して!」と声を上げる方法

遺留分は、権利があるからといって、黙っていては誰も払ってくれません。自分の権利が侵害されていることを知った相続人が、自らの意思で「請求」して初めて効力を発揮します。この請求のことを「遺留分侵害額請求」といいます。
誰に、どうやって請求する?
請求の相手方は、遺言や生前贈与によって、あなたの遺留分を侵害するほど多くの財産を受け取った人です。特定の相続人かもしれませんし、内縁の妻や、お世話になったという団体・病院かもしれません。
まずは当事者間で話し合うのが第一歩ですが、感情的な対立から難しい場合がほとんどです。そこで、法的に極めて重要になるのが、「内容証明郵便」で請求の意思表示を送付することです。これにより、「いつ」「誰が」「誰に」「どのような内容の請求をしたか」を郵便局が公的に証明してくれるため、後々の裁判などで強力な証拠となります。
絶対に注意すべき「時効」というタイムリミット!
ここが最も重要で、注意すべき点です。遺留分侵害額請求権には、非常に短い時効があります。
遺留分の権利を侵害する遺言や贈与があったことを知った時から【1年間】
この1年という期間は、あっという間に過ぎてしまいます。「どうしようか」と悩んでいるうちに、あるいは相手方との話し合いが長引いているうちに時効が完成してしまい、せっかくの権利が消滅してしまうケースが後を絶ちません。
また、遺言の内容などを知らなかった場合でも、相続開始の時から10年が経過すると、同様に権利は消滅します。
弁護士に依頼するメリット
「時効」という時間との戦いにおいて、専門家である弁護士の存在は不可欠です。ご依頼いただければ、まず時効を中断させるための確実な手続き(内容証明郵便の送付や調停の申立て)を迅速に行います。弁護士名で請求を行うことで、相手方も問題を軽視できなくなり、真摯な交渉に応じやすくなるというメリットもあります。皆様が時効の心配をすることなく、安心して交渉や手続きに臨めるよう、私たちが盾となります。
ステップ4:遺留分の計算 – 生前贈与も対象になります!

遺留分侵害額請求は、以前は「現物(不動産など)を返せ」という請求でしたが、2019年の民法改正により、侵害された額に相当する「お金を払え」という金銭請求に変わりました。
そのため、「いくら請求できるのか」を正確に計算することが非常に重要になります。この計算の基礎となる財産には、故人が亡くなった時に持っていた財産だけでなく、生前に行われた贈与も含まれる場合があります。
| 相続人に対する生前贈与(特別受益) | 原則として、相続開始前の10年間に行われたものが、遺留分算定の基礎財産に加算されます。 |
| 相続人以外への贈与 | 原則として、相続開始前の1年間に行われたものが加算されます。 |
これにより、「亡くなる直前に、愛人に全財産を贈与して、遺産をゼロにしてしまおう」といった、遺留分制度を骨抜きにするような行為を防いでいるのです。
弁護士に依頼するメリット
過去の生前贈与を洗い出し、それぞれの財産を正確に評価し、複雑な法律のルールに則って遺留分の侵害額を計算するのは、大変な作業です。私たちは、預金通帳の履歴を分析し、不動産等の評価を適切に行い、法改正の内容も踏まえて、皆様が請求できる正当な金額を正確に算出します。
究極のケース:「相続させない」と意思表示される「相続人廃除」

最後に、遺留分すらも認められない究極のケースとして、「相続人廃除」という制度にも触れておきます。これは、遺留分を持つ相続人が、故人に対して「虐待」や「重大な侮辱」、「その他の著しい非行」を行った場合に、故人の意思に基づいて、家庭裁判所の手続きを経て、その相続人の権利を完全に剥奪する制度です。相続人排除が認められた場合には、相続権がはく奪されるため、遺留分も請求できなくなります。
ただし、これは非常に強力な制度であるため、その要件は極めて厳格であり、単に「親子仲が悪かった」という程度では認められることはありません。
まとめ:泣き寝入りする前に、あなたの「最後の砦」の扉を叩いてください

故人が残した遺言書。その一枚の紙が、残された家族の間に深い溝を作ってしまうことがあります。
しかし、その内容に納得がいかないからといって、決して泣き寝入りする必要はありません。
- まずは、遺言自体の有効性を疑ってみる(遺言無効の主張)。
- それが難しくても、あなたには最低限の取り分である「遺留分」を請求する権利がある。
この二段構えの対抗策があることを、どうか忘れないでください。
ただし、これらの権利を主張するには、専門的な法律知識と、何よりも「1年」という時効との戦いが待っています。感情的な対立が深まる中、ご自身でこれを乗り越えるのは、あまりにも過酷な道のりです。
「故人の意思も分かるけれど、自分の権利も主張したい…」
その複雑な想いを、どうか私たち弁護士にお預けください。私たちが皆様の代理人となることで、相手方との直接の対立を避け、冷静かつ法的な根拠に基づいて、皆様の正当な権利の実現を目指します。
蒼生法律事務所では、相続に関する初回のご相談を無料で承っております。あなたのその悔しい想い、不安な気持ちを、まずは私たちにお聞かせください。そこから、解決への道は必ず開けます。
あなたの「最後の砦」を守り抜くために。
あなたからの一歩を、心よりお待ちしております。

2004年の弁護士登録以降、個人・法人問わず幅広い事件を担当し、クライアントにとっての重大事には誠実かつ丁寧に寄り添う。命運に配慮し、最善策を模索。豊富な実績と十分なコミュニケーションで、敷居の高さを感じさせない弁護士像を追求してきた。1978年大阪府出身、京都大学法学部卒業。2011年に独立。不動産・労務・商事・民事・破産・家事など多様な分野を扱い、2024年6月に蒼生法律事務所へ合流。相続・遺言