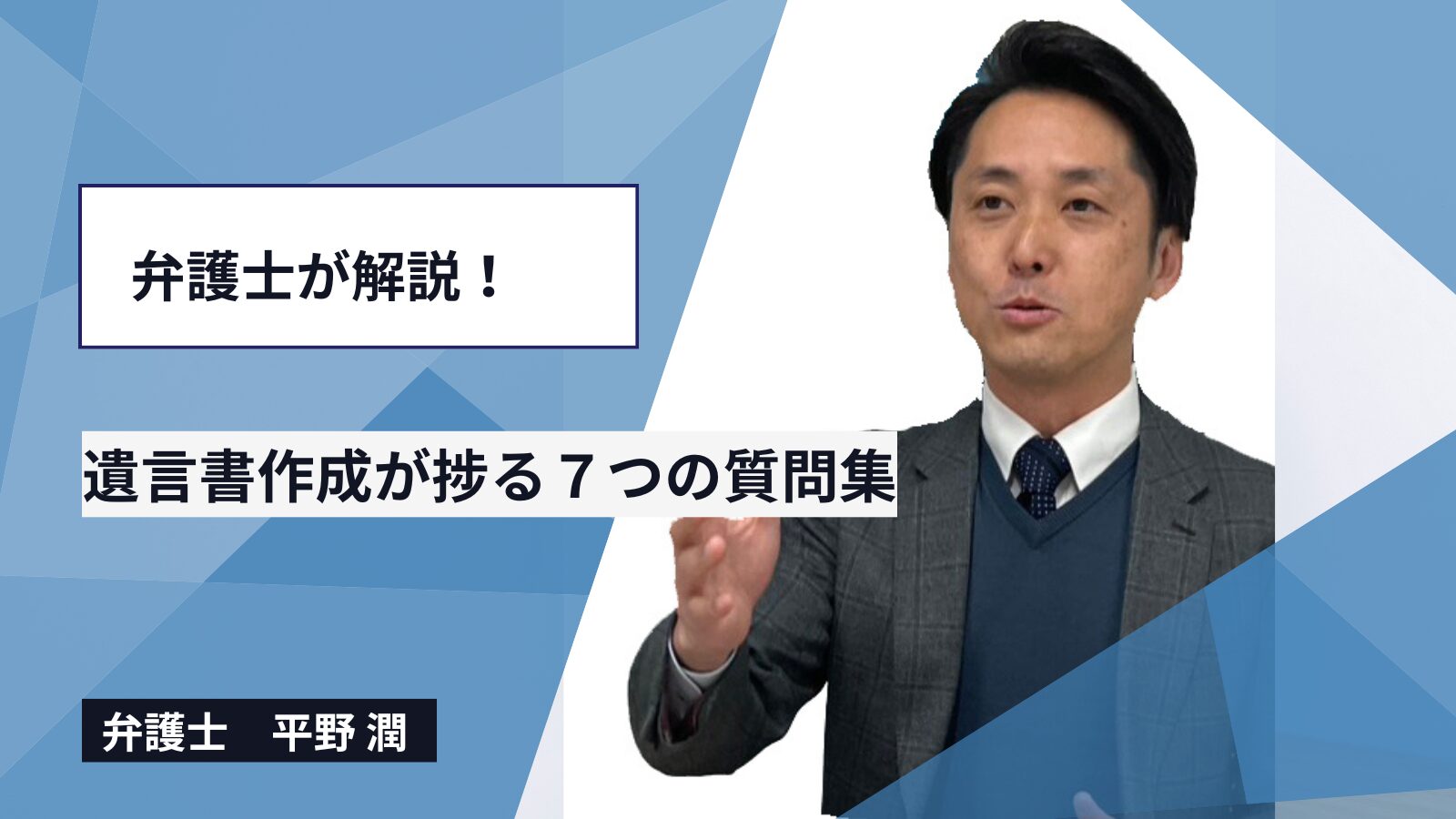
「自分の死後、大切な家族が財産を巡って争う『争族』だけは絶対に避けたい」
近年、このように考えてご自身の意思を明確にするため、遺言書の作成を検討される方が増えています。
しかし、いざ遺言書を書こうと思っても、「何から始めればいいのか?」「法的に正しい書き方は?」「どの種類を選べばいい?」といった多くの疑問や不安から、なかなか筆が進まないという方も少なくありません。
この記事では、遺言書作成を検討されている皆様が抱える共通の疑問について、相続問題の専門家である弁護士が「7つの質問集」としてQ&A形式で分かりやすくお答えします。これを読めば、あなたの遺言書作成はきっと捗るはずです。
質問1:そもそも「遺言書」とは?なぜ必要なのでしょうか?

A1:遺言書は、あなたの最終意思を実現し、残された家族を「争族」から守るための、最も有効な手段です。
遺言書とは、ご自身の財産を、死後、誰に、どのように遺したいかを示す、法的な効力を持つ最終意思表示です。これがあることで、法律で定められた相続分(法定相続)とは異なる割合で財産を分配することが可能になります。
では、なぜ遺言書が必要なのでしょうか。それは、遺言書がない場合、相続人全員による「遺産分割協議」が必須となり、これが深刻な争いの火種になるからです。
裁判所の司法統計(令和4年)によれば、遺産分割をめぐり家庭裁判所に持ち込まれた事件のうち、遺産の価額が「5000万円以下」のケースが全体の約76%を占めています。
(出典:裁判所 司法統計「令和4年 司法統計年報(家事編)」第52表)
このデータが示す通り、「うちは財産が多くないから大丈夫」という考えは通用しません。協議がまとまらなければ、家庭裁判所での調停や審判へと発展し、時間も費用も、そして何より大切な家族関係も失われてしまいます。
遺言書は、このような悲劇を未然に防ぎ、あなたの感謝の気持ちを伝える「家族への最後のラブレター」なのです。
質問2:遺言書の種類と、それぞれの違いが知りたいです。

A2:代表的なものは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。メリット・デメリットを正しく理解しましょう。
遺言書にはいくつか種類がありますが、一般的に利用されるのは以下の2つです。
| 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
| 作成方法 | 全文、日付、氏名を自書し、押印する。 | 公証役場で、証人2名立会いのもと、公証人が作成する。 |
| メリット |
|
|
| デメリット |
|
|
| 保管 | 自己責任で保管。 ※法務局の保管制度あり |
公証役場で原本を保管 |
参考:遺言書の検認 | 裁判所
手軽な「自筆証書遺言」ですが、検認された自筆証書遺言のうち、押印がない、日付がないといった理由で効力が争われるケースが少なくないというのが実情です。
自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、検認は不要となり、紛失のリスクもなくなります。ただし、この制度はあくまで遺言書を「保管」するもので、内容が法的に有効であることまで保証するものではありません。
(参考:法務省「自筆証書遺言書保管制度」)
そのため、確実性を最優先するなら、「公正証書遺言」が最もお勧めです。
質問3:自分で遺言書を書く場合、よくある失敗や注意点は何ですか?

A3:主に「形式不備」「内容の曖昧さ」「遺留分への無配慮」の3つが、争いの火種になります。
自筆証書遺言を作成する際には、特に以下の点に注意しないと、良かれと思って書いた遺言書が、かえって争いを引き起こす原因になりかねません。
- 1. 形式の不備で無効になる:「令和〇年吉日」といった日付の特定ができない記載、押印漏れ、全文がパソコン作成(財産目録を除く)など、民法が定める厳格な要件を満たさず、遺言書自体が無効と判断されるケースです。
- 2. 内容が曖昧で解釈が分かれる:「自宅不動産を妻に」と書いても、土地と建物の地番・家屋番号が特定されていなければ、手続きができません。「預貯金は子供たちで仲良く分けるように」といった表現も、具体的な割合が不明なため、結局相続人同士の話し合いが必要になり、争いの原因となります。
- 3. 遺留分(いりゅうぶん)を侵害している:配偶者や子など、一定の相続人には、法律上最低限保障された財産の取り分である「遺留分」があります。「全財産を愛人に遺す」といった遺言は作成できますが、相続人は遺留分を請求する権利(遺留分侵害額請求)を持ちます。これを無視した遺言は、新たな金銭トラブルを確実に引き起こします。
質問4:遺言書作成の手続きと費用は、どのくらいかかりますか?

A4:方式によって大きく異なります。「公正証書遺言」の場合、財産額に応じた公証人手数料が必要です。
【手続きの一般的な流れ】
- 1. 相続財産の洗い出し:預貯金、不動産、有価証券、借金などをリスト化した「財産目録」を作成します。
- 2. 内容の決定:誰に、どの財産を、どのくらい遺すかを決めます。
- 3. 方式の決定:自筆証書遺言か、公正証書遺言かを選びます。
- 4. 作成・保管:方式に従い作成します。公正証書の場合は、公証役場との打ち合わせや必要書類の準備が必要です。
【費用の目安】
- 自筆証書遺言:基本的に無料です。(法務局の保管制度を利用する場合は手数料3,900円 ※令和7年7月時点)
- 公正証書遺言:公証役場に支払う手数料がかかります。これは法律で定められており、相続させる財産の価額や相続人数によって変動します。
質問5:遺言書作成を「弁護士」に依頼するメリットは何ですか?

A5:「法的な有効性」の確保はもちろん、「争族を起こさせない」戦略的な内容を提案できる点です。
弁護士に依頼するメリットは、単に「間違いのない書類が作れる」という点に留まりません。
- 1. 法的に完璧な遺言書の作成:民法の要件を満たし、形式不備で無効になるリスクを完全に排除します。
- 2. 「争族」を予防する最適な内容の提案:ご家族の状況を丁寧にお伺いし、将来起こりうる遺留分トラブルなどを予測。それを未然に防ぐための財産の分け方、想いを伝える「付言事項」の書き方など、法律知識と紛争解決の経験を駆使して「争わせない」ための遺言書を設計します。
- 3. 正確な財産調査と「遺言執行者」就任:財産の調査漏れを防ぎます。また、弁護士を遺言内容を実現する「遺言執行者」に指定することで、あなたの死後、相続人全員の代理人として、中立公正な立場で、迅速かつ確実に預貯金の解約や不動産の名義変更などの手続きを進めます。残されたご家族の負担を劇的に軽減できます。
質問6:弁護士以外(信託銀行など)に頼むのと何が違いますか?

A6:弁護士は、唯一「紛争の予防」から「万一の紛争解決」まで一貫して対応できる専門家です。
遺言作成は、信託銀行や他の士業でも相談に応じています。しかし、対応できる業務範囲に大きな違いがあります。
- 信託銀行・行政書士・司法書士:弁護士以外の士業は「法律相談」や「交渉代理」を行うことが法律で禁じられています(非弁行為)。そのため、遺留分など法的に対立が生じる可能性のある事案については、具体的なアドバイスはできません。万が一、相続発生後にトラブルになった場合も、代理人として交渉できず、結局、ご家族が改めて弁護士を探す必要が出てきます。
- 弁護士:弁護士は、遺言書の作成段階から、将来の紛争リスクを完全に見据えた法的アドバイスが可能です。そして、万が一トラブルが発生してしまった場合でも、唯一、代理人として相手方と交渉し、調停や裁判まで一貫してご家族をサポートできる法律専門家なのです。
入り口から出口まで、すべての相続問題に対応できるのが弁護士の最大の強みです。
質問7:弁護士に遺言書作成を依頼する費用はどれくらいですか?

A7:将来の紛争コストを考えれば、安心を確保するための「価値ある投資」です。
弁護士費用は弁護士や法律事務所によって異なりますが、一般的な目安は以下の通りです。
- 遺言書作成手数料:10万円~30万円程度の定額報酬が中心です。(財産額や内容の複雑さにより変動することが多いと思います)
- 公正証書遺言にする場合:上記に加え、質問4で述べた公証人手数料が別途かかります。
この費用を「高い」と感じるかもしれません。しかし、もし遺言書がなく「争族」が起きてしまい、ご家族が裁判で争うことになれば、弁護士費用は数十万~数百万円に及ぶこともあります。
何よりも、お金には代えられない家族の絆が失われる精神的なコストは計り知れません。遺言書作成にかかる費用は、大切なご家族の未来と平穏を守るための「安心料」であり、極めて価値のある投資と言えるでしょう。
最後に
あなたの想いを、法的に正しく、そして争いのない形でご家族に遺すために。
遺言書作成に少しでも不安を感じたら、手遅れになる前に、ぜひ一度、相続問題に精通した私たち蒼生法律事務所にご相談ください。

2004年の弁護士登録以降、個人・法人問わず幅広い事件を担当し、クライアントにとっての重大事には誠実かつ丁寧に寄り添う。命運に配慮し、最善策を模索。豊富な実績と十分なコミュニケーションで、敷居の高さを感じさせない弁護士像を追求してきた。1978年大阪府出身、京都大学法学部卒業。2011年に独立。不動産・労務・商事・民事・破産・家事など多様な分野を扱い、2024年6月に蒼生法律事務所へ合流。相続・遺言




