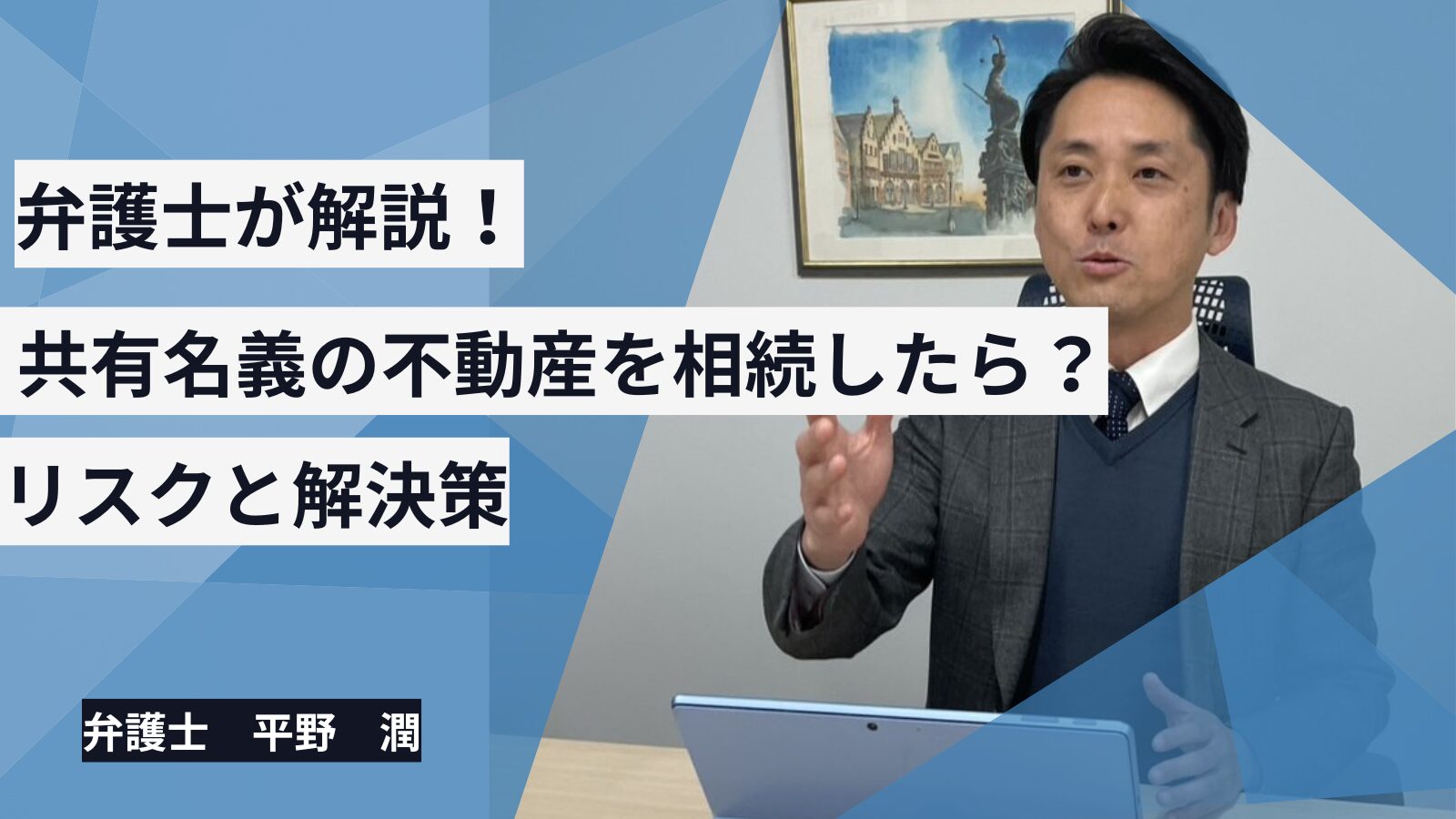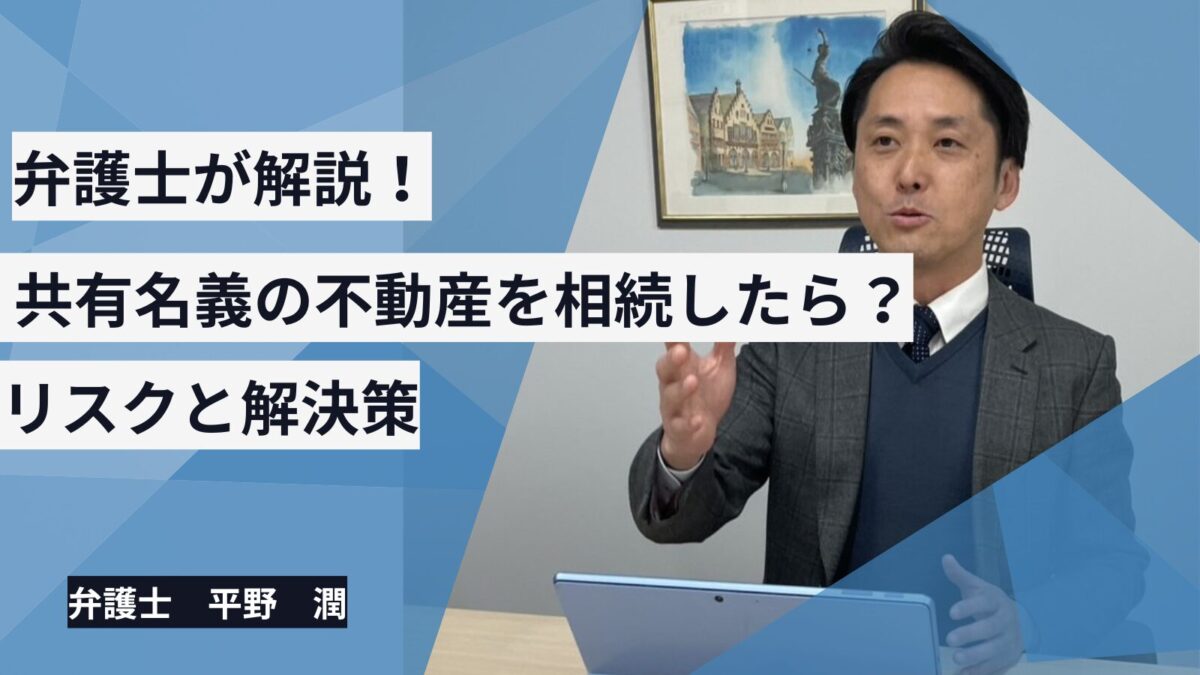
皆さん、こんにちは。蒼生(そうせい)法律事務所、代表弁護士の平野潤です。
遺産相続の話合いの中で、ご実家などの不動産をどう分けるかという問題は、非常によくあるご相談の一つです。特に、「兄弟みんなで平等に」という思いから、不動産を共有名義(きょうゆうめいぎ)にしようかと考えている方、あるいは、すでに共有名義になっている不動産を相続してしまい、どうすれば良いか悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
一見すると公平に見える「共有名義」ですが、実は後々、大きなトラブルの火種になってしまうケースが少なくありません。「あの時、もっとよく考えておけば…」と後悔される方を、私はこれまでたくさん見てきました。
そこで今回は、相続した不動産を共有名義とした場合に潜むリスクと、その具体的な解決策について、専門家の視点から分かりやすく解説していきます。
そもそも「不動産の共有名義」って何?

まず基本からお話ししますね。不動産の「共有名義」とは、一つの土地や建物を、複数人の名義で所有している状態のことを指します。それぞれの所有者が、その不動産に対して持っている権利の割合を「持分(もちぶん)」と呼びます。
例えば、お父様が亡くなり、ご兄弟3人(長男、次男、三男)でご実家を相続したとします。このとき、法定相続分に従って3分の1ずつ、それぞれの名前で登記をすると、このご実家は「長男 持分3分の1、次男 持分3分の1、三男 持分3分の1」という共有名義の不動産になります。
この「持分」は、不動産そのものを物理的に3つに分けるという意味ではありません。不動産全体を利用したり、そこから得られる利益(家賃など)を受け取ったりする権利を、持分割合に応じて持っている、という意味になります。
単独名義との違いは?共有名義の知られざるリスク

では、自分一人の名前で所有する「単独名義」と、この「共有名義」では何が違うのでしょうか。ここに、共有名義の大きな問題点とリスクが隠されています。
一言でいえば、「自分一人の意思では、不動産を自由に使ったり、処分したりできなくなる」という点が最大のリスクです。
法律では、共有不動産に対して行える行為を、その内容の重要度に応じて3つに分類しています。
1.保存行為(ほぞんこうい)
-
内容:不動産の現状を維持するための行為(例:雨漏りの修繕、不法占拠者への明渡し請求など)
-
各共有者が単独で行うことができます。
2.管理行為(かんりこうい)
-
内容:不動産を利用・収益化するための行為(例:人に貸して家賃収入を得る(賃貸借契約の締結)、賃貸借契約の解除など)
-
各共有者の持分の価格に従い、その過半数の同意が必要です。3分の1ずつの共有なら、2人以上の同意が必要になります。
3.変更・処分行為(へんこう・しょぶんこうい)
-
内容:不動産そのものに物理的な変化を加えたり、法律上の権利を変動させたりする行為(例:売却、建て替え、大規模なリフォーム、土地の一部を他人のために利用させる(地上権の設定)など)
-
共有者全員の同意が必要です。
【出典】
•共有物の変更(民法第251条)、共有物の管理(民法第252条)については、e-Gov法令検索の民法をご参照ください。
•民法 | e-Gov法令検索URL
お気づきでしょうか?
「実家を売却して、そのお金をみんなで分けたい」 「古くなったから、一度更地にして駐車場として活用したい」 といった、不動産の活用に関する重要な決定(処分行為)は、共有者が一人でも反対すれば、一切進めることができなくなってしまうのです。
さらに、時間は問題をより深刻にします。 もし共有者の一人である長男が亡くなったらどうなるでしょう?長男に奥さんと子供2人がいれば、長男が持っていた3分の1の持分は、さらにその3人に相続されます(これを数次相続(すうじそうぞく)と言います)。
すると、ご実家の共有者は、次男、三男、長男の妻、長男の子供2人の合計5人に増えてしまいます。最初は仲の良かった兄弟3人だけの話だったはずが、世代が代わるにつれて、面識の薄い親戚や、場合によっては行方不明の人が共有者に入ってくる可能性もあるのです。そうなると、全員の同意を取り付けるのは、ほとんど不可能に近い状態になってしまいます。
その他にも、
-
固定資産税の支払い:共有者全員に支払い義務がありますが、代表者一人に納税通知書が届くことが多く、他の人が払ってくれないというトラブルが起きやすい。
-
活用の意見対立:「自分は住みたい」「いや、売りたい」「人に貸すべきだ」と意見がまとまらない。
-
自分の持分だけの売却は困難:理論上、自分の持分だけを売ることは可能ですが、不動産の一部分の権利だけを買いたいという人は、不動産業者などを除き、まず現れません。
こうしたリスクを避けるためにも、安易に不動産を共有名義にすることは、弁護士としては決してお勧めできません。
どうすればいい?共有状態を解消するための解決策

では、すでに共有名義になってしまった不動産や、これから相続する不動産を共有にしないためには、どうすれば良いのでしょうか。主な解決策をご紹介します。
1. 遺産分割協議で共有を避ける
相続が発生した直後であれば、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で、共有状態を避ける分割方法を選択することが最も望ましいです。
-
代償分割(だいしょうぶんかつ):ある相続人(例えば長男)が不動産を単独で相続する代わりに、他の相続人(次男、三男)に対して、それぞれの相続分に見合う現金(代償金)を支払う方法です。不動産を維持したい人がいる場合に有効です。
-
換価分割(かんかぶんかつ):不動産を売却して現金化し、その現金を相続分に応じて分配する方法です。誰もその不動産に住む予定がない場合に、最も公平で分かりやすい方法と言えます。
-
現物分割(げんぶつぶんかつ):土地が広く、分割可能(分筆)な場合に、土地を物理的に分けてそれぞれが単独で所有する方法です。ただし、土地の形状や法的な規制により、分筆が難しい場合も多くあります。
2. 共有物分割請求
すでに共有状態にある不動産について、共有者間での話し合いがまとまらない場合は、「共有物分割請求(きょうゆうぶつぶんかつせいきゅう)」という法的な手続きを利用して、共有関係の解消を求めることができます。
まずは共有者間で分割方法について協議を行いますが、それでも話がまとまらなければ、裁判所に訴訟(共有物分割請求訴訟)を提起することになります。
裁判所は、当事者の主張や証拠を踏まえ、公平な分割方法を判断します。多くの場合、現物での分割が困難であれば、不動産全体を競売にかけてその代金を分ける「換価分割」や、特定の共有者に不動産を取得させ、他の共有者に賠償金を支払わせる「全面的価格賠償(代償分割に似た方法)」といった判決が下されます。
この裁判手続きは、一般的に、解決までに半年から2年以上かかることもあり、精神的にも時間的にも負担の大きい手続きです。そのため、できる限り、訴訟になる前の話し合いで解決することが理想です。
よくある失敗や勘違い

ここで、共有不動産に関するよくある失敗例や勘違いをいくつかご紹介します。
-
「とりあえず共有」という先送り:これが最も多い失敗です。「今はみんな仲が良いから大丈夫」と思っていても、将来の状況変化(結婚、死亡、経済状況の変化など)までは予測できません。問題の先送りは、事態を悪化させるだけです。
-
「法定相続分で登記するのが当たり前」という勘違い:法定相続分はあくまで相続分の目安です。遺産分割協議で合意すれば、誰か一人が相続するなど、自由に分割方法を決めることができます。必ずしも法定相続分の通りに共有名義にする必要はないのです。
-
「固定資産税を払っていれば権利が強くなる」という誤解:固定資産税を一人で払い続けていたとしても、それだけで自分の持分が増えたり、他の共有者の同意なしに売却できるようになったりするわけではありません。ただし、支払った分を他の共有者に請求する権利はあります(求償権)。
悩んだら、まず弁護士にご相談を!そのメリットとは?

ここまで読んでいただき、「うちのケースも、もしかしたら…」と不安に思われた方もいらっしゃるかもしれません。共有名義の不動産問題は、法律だけでなく、親族間の感情も絡み合う非常にデリケートな問題です。当事者同士で話し合うと、どうしても感情的になり、話がこじれてしまいがちです。
このような時こそ、私たち弁護士がお力になれます。弁護士に依頼するメリットは、単に法律手続きを代行するだけではありません。
-
冷静な交渉の代理人:あなたの代理人として、感情的な対立を避け、法的な根拠に基づいて冷静に相手方と交渉を進めることができます。
-
最適な解決策のご提案:ご状況を詳しくお伺いした上で、代償分割、換価分割、共有物分割請求など、あなたにとって最も有利で現実的な解決策をご提案します。
-
複雑な手続きの一任:遺産分割協議書の作成から、調停や訴訟になった場合の対応まで、専門的で煩雑な手続きをすべてお任せいただけます。
-
行方不明の共有者調査:戸籍等をたどり、連絡の取れない共有者の所在を調査することも可能です。
-
精神的な負担の軽減:何より、複雑でストレスの多い問題から解放され、ご自身の普段の生活に専念できることが最大のメリットかもしれません。
終わりに

共有名義の不動産問題は、放置すればするほど、権利関係が複雑になり、解決が困難になります。「まだ大丈夫だろう」と思わず、問題が小さいうちに、できるだけ早く対策を講じることが重要です。
もし、あなたが共有名義の不動産について少しでもお悩みでしたら、一人で抱え込まずに、まずは私たち専門家にご相談ください。蒼生法律事務所では、相続問題に関する初回のご相談は無料でお受けしております。どのような解決方法があるのか、費用はどのくらいかかるのか、まずはお話をお伺いするだけでも構いません。
あなたにとって最善の解決が見つかるよう、親身にサポートさせていただきます。
まずはお気軽にお問い合わせください。

2004年の弁護士登録以降、個人・法人問わず幅広い事件を担当し、クライアントにとっての重大事には誠実かつ丁寧に寄り添う。命運に配慮し、最善策を模索。豊富な実績と十分なコミュニケーションで、敷居の高さを感じさせない弁護士像を追求してきた。1978年大阪府出身、京都大学法学部卒業。2011年に独立。不動産・労務・商事・民事・破産・家事など多様な分野を扱い、2024年6月に蒼生法律事務所へ合流。相続・遺言