
不動産の相続においては、いくつかの注意点があります。
地主・不動産経営者としては、相続税の負担や相続後の維持・管理、分割に関するトラブルを避けるために、事前にしっかりと準備しておくことが重要です。
また、相続人としては、相続した不動産の維持・管理や賃貸・売却などについて、他の相続人との協議を含めて、対応していくことが重要です。
地主・不動産経営者としての対応

相続における不動産の取り扱いは、相続税評価額の問題、遺産分割の方法、そして相続税の支払い資金の確保など、多くの課題が伴います。
適切な対策を講じずに相続を迎えると、多額の税負担や相続人間のトラブルを引き起こす可能性があります。
不動産を次世代へ円滑に承継するためには、事前の準備と戦略的な相続対策が不可欠です。
当事務所では、地主・不動産経営者の皆さまが直面する相続の課題に特化し、法的な視点から最適な対策をご提案します。
- 相続税評価額を抑え、税負担を軽減する方法は?
- 不動産を巡る遺産分割のトラブルを回避するには?
- 相続税を円滑に支払うための資金確保の手段は?
これらの疑問を解決し、大切な資産を守るために、今からできる対策を一緒に考えていきましょう。
経験豊富な弁護士が、あなたの状況に合わせた相続対策をサポートいたします。
相続税の評価額

不動産の相続税は、当該不動産の評価額に基づいて計算されますが、評価額が必ずしも市場価格と一致するわけではありません。相続税評価額が高くなると、それに伴って相続税の負担も増えるため、評価額を下げるための対策を検討することが重要です。具体的な方法としては、以下のようなものがあります。
①小規模宅地等の特例
自宅や事業用の土地について、一定の条件を満たすと評価額を引下げることが可能となります。
この特例を利用するためには要件を確認しておく必要があります。
②土地の利用方法
土地を賃貸したり、建物を建てて賃貸することで、評価額を下げることが可能となります。
将来的な利用方法・目的を考慮したうえで、賃貸条件を設定する必要があります。
遺産分割方法の指定

不動産を複数の相続人で相続する場合、どの相続人がどの不動産を取得するかについて意見が整わず、争いとなることが少なくありません。
また、一つの土地を分割する場合にも、東西南北などの方角や隣接地を含む環境など分割方法について、意見が整わないこともあります。
他方、不動産を相続人間の共有とした場合には、分割に関する争いを防ぐことができる反面、使用や賃貸、売却などについての意見が整わず、将来、紛争を招く危険性があります。
また、共有状態で相続を繰り返した場合には、相続人が多数となり、調整がより困難となる可能性があります。
そのため、相続人の生活状況や仕事内容などを考慮して、遺言書を作成し、どの相続人がどの不動産を取得するのか、遺産分割方法を指定しておくことが重要です。
相続税の支払い資金の確保

評価額の高い不動産を相続した場合、それに伴って相続税の負担も増えることになります。
ところが、現預金などの流動資産が不足していると、相続税を一括で支払うことが困難になることがあります。
そのため、以下のように、相続税の支払いに備えた資金を確保しておくことが重要です。
①生命保険の活用
生命保険契約をして、不動産を取得する相続人を保険金の受取人に指定することで、相続税の支払い資金を確保することができます。
②不動産の売却
生前に不動産を売却することで、相続税の支払い資金を確保することができます。
ただし、不動産の売却による税(譲渡所得税)負担が生じる点には注意が必要です。
地主・不動産経営者の相続人としての対応

相続により不動産を取得した場合、単に資産が増えるだけでなく、その維持・管理や処分に関する責任も伴います。
特に、賃貸経営を引き継ぐ場合や、空き家・共有不動産を抱えるケースでは、適切な対策を講じなければ、大きな経済的負担や法的トラブルに発展する可能性があります。
- 相続した不動産をどのように管理すればよいのか?
- 賃貸や売却を検討すべきタイミングとは?
- 共有不動産や借地権付きの物件を適切に処分する方法は?
このような不動産相続の課題に対し、専門的な知識をもとに最適な解決策をご提案します。
相続した不動産を資産として最大限に活かすために、当事務所が全面的にサポートいたします。
まずはお気軽にご相談ください。
不動産の維持・管理

不動産を相続した場合、固定資産税・都市計画税の負担が生じるだけでなく、その維持や管理をしなければいけなくなります。
特に、広い土地や古い建物を相続した場合には、維持・管理の負担が大きくなることがあります。
①賃貸と管理
土地や建物を賃貸することにより、収益を得ながら維持・管理するという方法もあります。
ただし、賃借人の募集や契約、物件の管理は簡単なものではありません。
また、建物の改修(メンテナンス)や賃料の回収・増減額など、法的な問題が生じることも少なくありません。
②空き家問題
空き家の管理をしないまま放置した場合、近隣住民からの苦情や建物の劣化が進む可能性があります。
特定空き家や管理不全空き家と認定された場合、固定資産税が6倍となるため、適切に管理することが重要です。
不動産の処分・売却

①共有不動産
遺産分割協議がまとまらず、長年共有状態となったままの不動産がある場合、固定資産税などの維持費の負担ばかりが生じる可能性があります。
このように共有者間で分割方法について合意が得られない場合、裁判所を通じて、共有物の分割請求を行うことが可能です。
②借地上建物
借地上建物の相続には、地主の承諾は不要ですが、売却するためには地主の承諾が必要です。
地主の承諾が得られない場合には、裁判所に地主の承諾に代わる許可を求めることになります。
また、借地上建物の改築にも地主の承諾が必要となる可能性がありますので、注意が必要です。
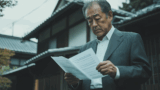
大切な不動産を守り、円滑な相続を実現するために

地主・不動産経営者にとって、相続は単なる資産の継承ではなく、相続税負担の最小化、適切な遺産分割、不動産の維持管理、売却や賃貸の判断など、多くの課題が伴います。
また、相続人としても、引き継いだ不動産をどのように活用・管理するかを慎重に考える必要があります。
適切な対策を取らないまま相続を迎えると、税負担の増加、相続人間のトラブル、不動産の資産価値の低下といった問題に直面する可能性があります。
そのため、事前の準備と専門家のサポートが不可欠です。
当事務所では、地主・不動産経営者の皆さまが円滑に資産を次世代へ継承できるよう、法的視点から最適な相続対策をご提案します。
相続税の軽減、遺産分割の円滑化、不動産管理や売却のサポートなど、お客様の状況に合わせた解決策をご提供いたします。
大切な資産を守り、未来へとつなぐために、まずはお気軽にご相談ください。
不動産オーナーの相続【お悩み別 Q&A】
お客様から多く寄せられるご質問をご紹介します。
まずは「相続人」と「全財産」の確定から始めましょう。
ご心痛お察しいたします。不動産相続はやるべきことが多く、途方に暮れてしまいますよね。
相続手続きの基本は、どのようなケースでも同じです。まずは以下の2つを確定させることから始めます。
相続人の調査:故人の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて集め、法的に誰が相続人になるのかを確定させます。
相続財産の調査:不動産はもちろん、預貯金、株式、そして借金などのマイナスの財産も含め、故人の全財産をリストアップします。
この2つが確定しないと、遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議」に進むことができません。特に不動産は、この後の手続きが複雑になりますので、最初の段階で専門家である弁護士にご相談いただくことを強くお勧めします。
私たちは、相続の全体像を見据えた上で、今やるべきこと、今後の見通しを明確にご提示いたします。
「名寄帳(なよせちょう)」を取得することで、網羅的に調査できます。
素晴らしいお父様ですね。しかし、管理は大変です。不動産がありそうな市区町村の役所(都税事務所や市役所の資産税課など)で「名寄帳」という書類を取得しましょう。これは、その市区町村内に故人が所有していた不動産の一覧が記載されているものです。
とはいえ、どの市区町村にあるか見当もつかない場合、全国の役所をしらみつぶしに当たるのは現実的ではありません。私たち弁護士にご依頼いただければ、故人の過去の住所地や関係先などから当たりをつけ、職務上の権限で、全国の役所に一括して名寄帳の取得請求をかけることが可能です。皆様の手を煩わせることなく、迅速かつ正確に全財産を把握するお手伝いをいたします。
絶対にお勧めしません。「争族」の火種を、次世代に先送りするだけです。
「とりあえず共有」は、一見すると円満で公平な解決に見えますが、将来、非常に高い確率で深刻なトラブルを引き起こします。
売れない・貸せない・建て替えられない:共有不動産を処分・活用するには、共有者「全員」の同意が必要です。一人でも反対すれば、何もできません。
関係者がネズミ算式に増える:兄弟の一人が亡くなると、その持ち分はさらにその配偶者や子に相続されます。会ったこともない甥や姪と、不動産の管理について話し合わなければならない…という事態になりかねません。
共有状態は、いわば「問題の先送り」です。相続が発生したこのタイミングで、誰か一人が単独で相続する(他の相続人には代償金として現金を支払う)、あるいは売却して現金で分ける(換価分割)など、きっちりと解決しておくべきです。
地主さんとの関係が非常に重要になります。名義変更料などが必要な場合も。
借地権も、立派な相続財産です。相続によって借地権を引き継ぐこと自体に、地主さんの承諾は必要ありません。
しかし、今後、その家を建て替えたり、第三者に売却したりする際には、地主さんの承諾が必要となり、一般に「承諾料」の支払いが発生します。また、地代の支払いや更新料など、地主さんとの良好な関係を維持していくことが、その不動産の価値を守る上で不可欠です。
地主さんとの間でトラブルになったり、法外な承諾料を請求されたりした場合には、弁護士が代理人として交渉にあたります。借地非訟といった法的な手続きも視野に入れ、皆様の権利を守ります。
勝手に部屋に入ったり、荷物を処分したりしてはいけません。
大家さんとしての責任も引き継ぐことになります。まず、その入居者様の相続人がいるかどうかを調査する必要があります。相続人がいれば、その方と未払い家賃の精算や、部屋の明け渡し、残置物の処分について話し合います。
もし相続人がいない場合や、相続人全員が相続放棄をした場合は、家庭裁判所に**「相続財産管理人」**の選任を申し立て、その管理人と法的な手続きを進めていくことになります。
いずれにせよ、法的な手順を踏まずに荷物を処分すると、後から損害賠償を請求されるリスクがあります。対応に迷われたら、すぐに私たちにご相談ください。
出典: 相続財産管理人の選任(裁判所)
放置は非常に危険です。「特定空家」に指定されると、固定資産税が最大6倍になる可能性があります。
空き家の放置は、倒壊の危険、景観の悪化、不審者の侵入など、多くの社会問題を引き起こします。そのため、国は「空家等対策の推進に関する特別措置法」を定め、管理が不適切な空き家を**「特定空家」**に指定し、勧告や命令を行えるようにしました。
勧告を受けると、固定資産税の住宅用地特例が適用されなくなり、税額が跳ね上がってしまいます。そうなる前に、売却するのか、賃貸に出すのか、あるいは解体するのか、早急に方針を決める必要があります。私たちは、提携する不動産会社や解体業者と連携し、皆様にとって最適な空き家対策をご提案します。
メリットもデメリットもあります。資産規模やご家族の状況による、慎重な判断が必要です。
いわゆる「資産管理会社」を設立して不動産を所有する方法ですね。
メリット:家賃収入が個人の所得ではなく法人の所得になるため、所得税・住民税の税率を抑えられる可能性があります。また、相続の際には、不動産そのものではなく「会社の株式」が相続対象となるため、評価額の算定や分割がしやすくなります。
デメリット:法人設立・維持のコストがかかります。また、法人から個人に役員報酬としてお金を移す際に、給与所得課税が発生します。
法人化が有利かどうかは、所有不動産の規模や収益性、ご家族の構成などによって全く異なります。税理士とも連携の上、長期的な視点でのシミュレーションが不可欠です。
会社の株式を、遺言書によって後継者に集中させることが最も重要です。
会社の経営権は、株式の議決権によって決まります。お父様が遺言書を書かずに亡くなると、会社の株式が他のご兄弟にも分散してしまい、あなたの経営権が不安定になる恐れがあります。
そうならないために、生前にお父様に「会社の全株式を長男に相続させる」という内容の公正証書遺言を作成してもらうことが、最も確実で強力な事業承継対策です。場合によっては、M&A(会社の売却)や、従業員への承継(EBO)なども選択肢となり得ます。私たちは、M&Aの専門家とも連携し、最適な事業承継プランを設計するお手伝いをいたします。
「小規模宅地等の特例」の活用が最大のポイントです。
あります。不動産オーナーの相続税対策で最も重要なのが「小規模宅地等の特例」です。これは、ご自宅の土地や、事業(アパート経営など)で使っていた土地について、一定の要件を満たせば、その土地の評価額を最大で80%も減額できるという、非常に強力な制度です。
例えば、1億円と評価される土地が、2,000万円の評価で済むのですから、相続税額に絶大なインパクトがあります。
この特例を適用できるかどうかは、土地の種類や面積、相続する人との関係など、非常に複雑な要件が絡み合います。相続に強い税理士と連携し、確実に適用できるよう準備を進めることが肝心です。
「延納」や「物納」という制度があります。ただし、ハードルは低くありません。
相続税は、原則として現金一括納付です。しかし、それが困難な場合には、
延納:担保を提供し、利子を払うことで、年賦で分割払いにする制度。
物納:延納も困難な場合に、不動産そのもので税金を納める制度。
という選択肢があります。ただし、いずれも税務署の許可が必要で、手続きも複雑です。物納できる財産にも厳しい条件があり、全ての不動産が認められるわけではありません。
そうなる前に、生前から納税資金をどう確保するかを計画しておくことが重要です。生命保険の活用(死亡保険金は受取人固有の財産となり、納税資金に充てやすい)や、一部不動産の売却準備などを、計画的に進めていきましょう。
あなたの想いを込めた「遺言書」の作成と、より柔軟な「家族信託」の活用が有効です。
ご心配はもっともです。不動産は分けにくい財産だからこそ、生前の対策が何よりも重要です。
遺言書:「このアパートは長男に、こちらの土地は次男に」というように、あなたの意思で分け方を明確に指定しておくことで、子どもたちの争いを未然に防ぎます。なぜそのように分けたのか、想いを綴る「付言事項」も効果的です。
家族信託:より柔軟な対策として、元気なうちに不動産の管理を信頼できるお子様(受託者)に託し、家賃収入はご自身(受益者)が受け取る、という契約も可能です。これにより、あなたの認知症対策にもなり、あなたが亡くなった後の承継先もスムーズに指定できます。
どちらの方法が最適か、ぜひ一度、私たち専門家にご相談ください。
あります。相続人が複数いる場合の売却は、単なる不動産取引ではないからです。
相続不動産の売却には、
相続人全員の同意取り付けと、遺産分割協議書の作成
前提となる相続登記の手続き
売却代金の公平な分配
譲渡所得税の申告
など、多くの法的な手続きが絡みます。私たち弁護士が窓口となることで、これらの複雑な手続きをワンストップで調整し、提携する信頼できる不動産会社と連携して、スムーズかつ有利な売却を実現します。相続人間のトラブルを未然に防ぎ、皆様が納得できる形で資産を整理する「交通整理役」として、私たちをご活用ください。
不動産相続の羅針盤として、弁護士をご活用ください
不動産オーナーの相続は、法律、税務、そして経営という、異なる分野の知識が複雑に絡み合う、まさに「総合芸術」のようなものです。
個別の問題は、司法書士、税理士、不動産会社といった専門家でも対応できるかもしれません。しかし、それら全てを見渡し、あなたの、そしてご家族全体の利益を最大化するための最適な戦略を立てる「司令塔」こそ、相続全体を俯瞰できる弁護士の最も重要な役割です。
あなたの、そしてご先祖様が大切に守り育ててきた資産を、争いなく、そして確実に、未来へ繋いでいくために。
まずは、どんな些細なことでも構いません。皆様が今抱えているご不安や、将来への想いを、私たちにお聞かせください。
蒼生法律事務所は、あなたの相続という航海の、頼れる羅針盤となります。
あなたからのお問い合わせを、心よりお待ちしております。



