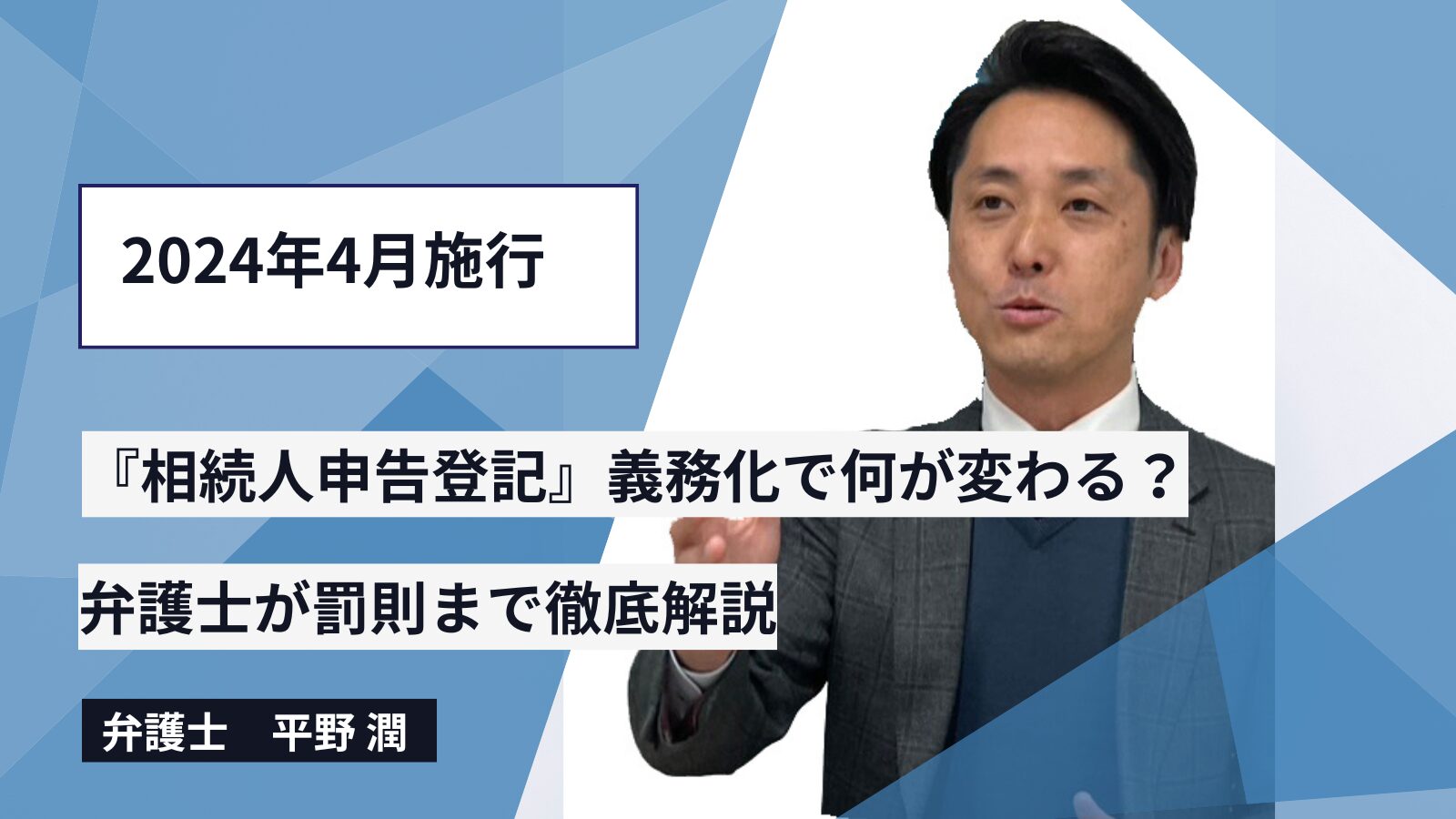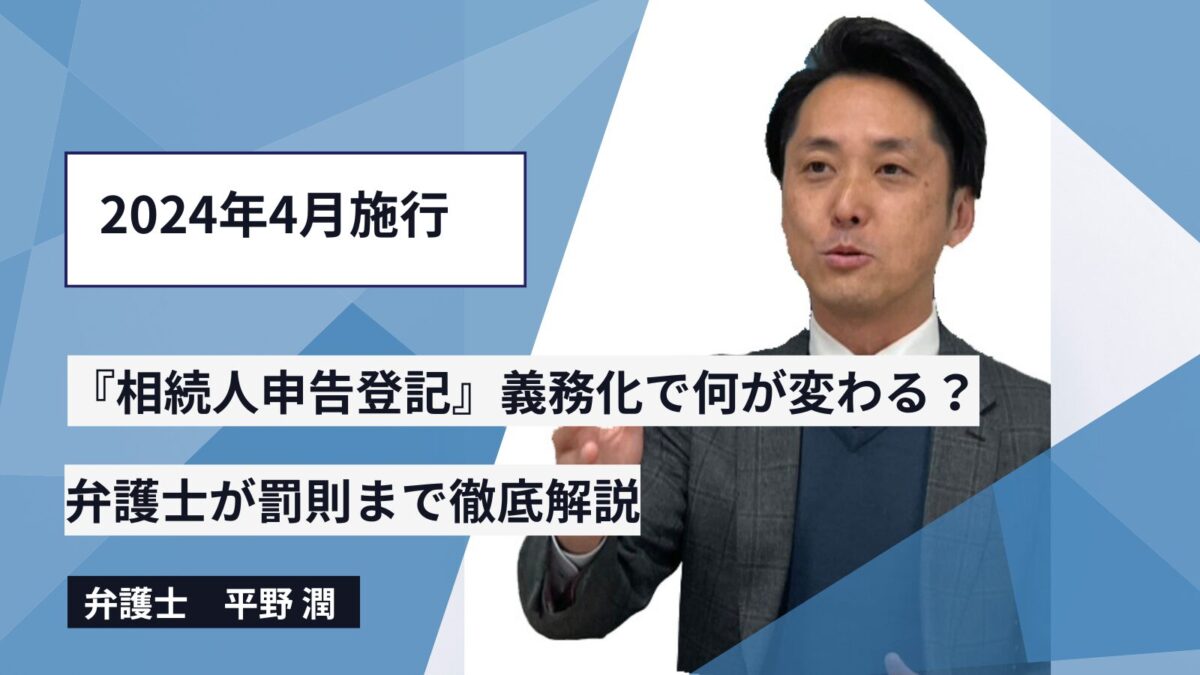
 こんにちは。蒼生法律事務所の弁護士、平野潤です。
こんにちは。蒼生法律事務所の弁護士、平野潤です。
今日は 2024年4月から始まった「相続人申告登記」の義務化 について、初心者の方にもわかりやすく徹底解説します。相続でお悩みの皆さんにとって、とても大切な制度変更ですので、ぜひ最後までお読みください。今回の法改正によって相続登記(不動産の名義変更)が義務化され、正当な理由なく放置すると過料(罰則)の対象となりました。
一体なぜこんな制度ができたのか? 何をしなければならないのか? 弁護士の視点から、制度の概要、罰則の内容や新設の「相続人申告登記」の仕組みまで、ポイントを押さえて解説していきます。
相続登記が放置されてきた背景 – 面倒・費用・期限なしで後回しに…
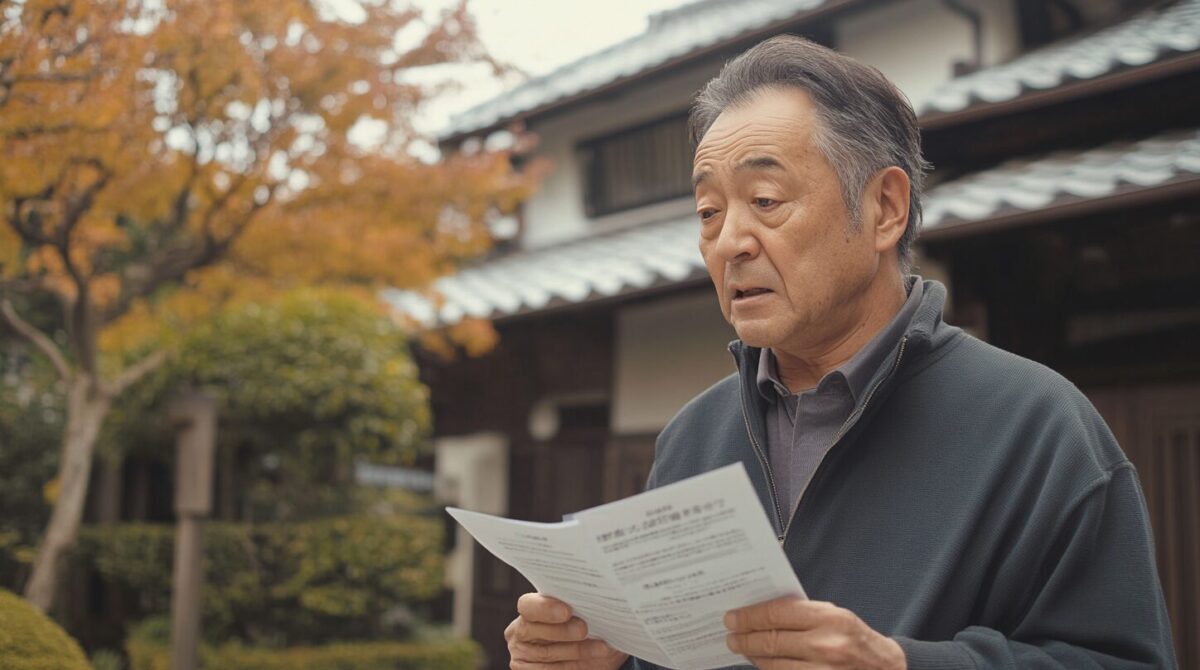
まず、今回の義務化以前には「相続登記はしなくても特に罰則がない任意の手続き」でした。そのため、多くの方が相続が発生しても不動産の名義変更(相続登記)を長年放置してしまうケースが珍しくありませんでした。なぜ人々は相続登記を後回しにしがちだったのでしょうか?主な理由は次の通りです。
手続きが煩雑で大変: 相続登記の手続きには多くの書類集めが必要で、戸籍謄本を出生から死亡まで遡って取得したり、法務局へ何度も足を運んだりと大変手間がかかります。
法律で細かいルールが定められており、申請書の書き方ひとつとっても決して簡単ではありません。
インターネットで調べても、実際に不備なく書類を揃えて申請するには相当な時間と労力が必要です。
費用の問題: 登記をするには登録免許税という税金や各種証明書の発行手数料がかかりますし、専門家(司法書士や弁護士)に依頼すればその報酬も必要です。
相続する不動産の評価額の0.4%が登録免許税として課税されるので、例えば評価額1,000万円の土地なら4万円の税金がかかります。
不動産を売却すれば費用を回収できますが、売る予定もないような土地だと「お金をかけて名義変更しても意味がないのでは?」と感じて放置してしまう方もいたのです。
相続人全員の協力が必要: 不動産の相続登記は、遺言がない場合は相続人全員で遺産分割協議をして誰が取得するか決め、その合意に基づいて行います。近しい親族が2~3人程度ならまだしも、相続人の数が多かったり遠方で疎遠な親族がいると連絡を取るだけでも一苦労です。
中には意見が合わず揉めてしまったり、協力してくれない人がいるケースもあります。
「家族がまとまらないから登記が進まない」と先延ばしにしているうちに年月が経ってしまうことも多いのです。
こうした 「面倒・お金がかかる・みんなの同意が必要」 というハードルの高さから、相続登記は後回しにされがちでした。実際、私が相談を受ける依頼者の方からも「いつかやらなきゃと思いつつ、そのままになっていました…」という声をよく耳にします。特に地方の土地や古い実家など、すぐに売ったり使ったりしない不動産ほど放置されやすい傾向があります。
相続人が多いとこんなに大変!登記放置が招く複雑化の問題

相続登記を長期間放置すると、相続人の範囲が世代を経てどんどん広がり、事態はますます複雑になります。 親から子への相続登記をしないまま子も亡くなれば、その次は孫世代…と相続の連鎖が数次相続になっていきます。時間が経つほど「相続人が誰なのか分からない」「遠い親戚まで含めると膨大な人数になった」といった問題が発生しやすくなるのです。
例えば、実際にあった例ですが、1952年(昭和27年)に亡くなった大叔母さんの不動産について、何十年も名義が亡くなった方のまま放置されていたケースがありました。
大叔母さんには配偶者もお子さんもいなかったため、法定相続人は兄弟姉妹となりますが、兄弟姉妹も亡くなった方が多く、その子どもたち(甥や姪)が相続人になりました。
想像するだけでかなり相続人の数が多くなりそうですよね。
案の定、相続人を確定させるためには大叔母さんの出生から死亡までの戸籍、両親および兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍…と何十通にも及ぶ戸籍謄本を集める必要がありました。
依頼者である甥御さんは固定資産税をずっと支払っていたものの、ご自身で法務局に相談に行ったところ「あまりに複雑なので専門家にお願いした方がいい」と言われ、最初に相談した近所の司法書士事務所では渋い顔をされたそうです。
最終的には「自分の代でなんとか片付けたい」「自分の子供には迷惑をかけたくない」という思いから弁護士に依頼して無事登記を完了できましたが、相続人を特定して必要書類を揃えるだけでも膨大な時間と労力がかかりました。
このように、相続人が多かったり代替わりしていたりすると、一般の方が自力で相続人を特定して登記を進めるのは非常に困難です。
戸籍の読み解きや収集には専門知識が要りますし、海外在住の相続人がいれば連絡や書類の取り寄せも一筋縄ではいきません。相続人の中に高齢で判断能力が衰えている方がいたり、疎遠で音信不通の方がいる場合も問題です。
こうした場合こそ、弁護士の出番です。
私たち弁護士であれば、戸籍調査から相続関係の確定、さらには協力してくれない相続人への対応まで含めてサポートできます。司法書士は登記の専門家ですが、相続人間の争いがあるケースでは、弁護士が交渉や調停の代理人となって問題解決に当たることもできます。
相続登記が何世代にもわたって放置されて「どこから手を付ければいいの?」という場合でも、弁護士に相談すれば解決への道筋が見えてきますので、あきらめずにご相談くださいね。
空き家・所有者不明土地問題…社会に広がる放置の弊害

相続登記を放置することは、相続人個人の問題に留まらず社会的にも大きな弊害を生んでいます。
その代表例が 「所有者不明土地」 の増加問題です。
所有者不明土地とは、登記簿などを調べてもすぐに所有者が判明しない土地や、所有者が分かっていても連絡がつかない土地のことです。
相続登記がされないまま所有者が亡くなり、さらにその相続人も行方不明だったり膨大な人数になったりすると、もはやその土地の持ち主を特定できなくなってしまいます。
実は日本全国でこうした所有者不明土地が広がっており、国土交通省の調査によれば日本の国土の約24%が所有者不明土地になっているとの推計もあります。なんと九州全土の面積を上回る規模です。
所有者不明の土地や空き家が増えるとどんな問題が起きるのでしょうか?まず、公共事業や災害復興のために土地を使おうとしても持ち主に許可を得られず、計画が止まってしまう妨げになります。
また、誰も管理していない空き地・空き家が長年放置されることで、雑草が生い茂って害虫が発生したり、不法投棄のゴミが山積みになったり、最悪は不審者に占拠されるといった事態も起こり得ます。
実際、総務省の統計では全国に約840万戸もの空き家が存在し、住宅全体の13.5%が空き家だという報告もあります。
管理されていない空き家は景観を損ねるだけでなく、老朽化して倒壊すれば周囲に被害を及ぼす危険もあります。こうした問題から周辺の治安や公衆衛生に悪影響を及ぼし、地域社会にとって大きな悩みの種となっています。
所有者不明土地や空き家問題の大きな原因の一つが「相続登記の放置」です。
相続登記をしないと、土地建物の名義は亡くなった人のまま止まってしまいます。そして時間だけが過ぎれば相続人は雪だるま式に増え、誰にも管理されない不動産が次々と生まれてしまいます。
私も仕事柄、様々な場所を訪れますが、明らかに人が住んでいない古い家屋や荒れたままの土地を見かけます。「持ち主が分からなくて手入れも売却もできない」というケースが少なくありません。 こうした社会問題に対応するため、行政も本腰を入れて空き家対策に乗り出しています。
2015年には「空家等対策の推進に関する特別措置法(空き家対策特別措置法)」が施行され、倒壊の恐れがあるような危険な放置空き家を「特定空家等」に指定して行政代執行で除去したり、固定資産税の優遇を外して税負担を増やすなどの措置が取られるようになりました。また 2023年にはこの空き家対策法が改正され、行政が所有者不明の空き家土地を処分しやすくする仕組みや、自治体による管理権限の強化などが盛り込まれています。とはいえ、どんな対策も「誰が所有者なのか」がはっきりしないことには始まりません。そこで登場したのが、次章で説明する相続登記の義務化と相続人申告登記という新制度です。
国は相続登記をきちんと行ってもらうことで所有者を明確にし、空き家や所有者不明土地の発生を予防しようと考えているのです。
相続登記の申請義務化スタート!新制度の概要と罰則

こうした背景を受けて、2024年4月1日から不動産の相続登記が法律で義務化されました。
具体的には、相続(遺言による取得を含みます)で土地や建物を取得した人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に法務局へ相続登記の申請をしなければならない、と定められたのです
もし遺産分割協議によって特定の相続人が不動産を取得した場合は、その遺産分割が成立した日から3年以内が期限になります。
要するに、今までは「いつ相続登記するかは皆さんの自由ですよ」という状態だったのが、これからは期限内にちゃんと登記しないといけませんよ、というルールに変わったわけです。 では、万一この義務を守らなかった場合はどうなるのでしょうか? 新しい法律では、正当な理由なく期限を過ぎても相続登記の申請をしなかったときは、10万円以下の過料(罰金のようなもの)が科される可能性があると定められました。
過料というのは刑罰ではなく行政上のペナルティですが、簡単に言えば「反則金」のようなものです。最高で10万円となっていますが、悪質性や事情に応じて額が決まります。「正当な理由」がある場合は過料が免除されることもありますが、基本的には期限を守ることが求められます。
正当な理由が認められるケースとは?
義務化とはいえ、現実には「すぐに相続登記したくてもできない」場合もあります。そのため法律上、「正当な理由」があれば期限内に登記できなくても過料は科さないことになっています。具体的には、相続人の数が極端に多くて協議に時間がかかっているケース、遺言書の有効性や遺産の範囲を巡って相続人間で紛争中のケースなどが代表例とされています。
他にも、相続登記をすべき人自身が重病で動けない場合や、DV被害に遭っていて配偶者と連絡を取れないケース、手続きをしたくても費用をどうしても工面できないような経済的困窮ケースなども考えられます。
ただし注意したいのは、「正当な理由」があって過料を免れたとしても、それで義務そのものが免除されるわけではない点です。
あくまで過料を一時的に猶予されるだけで、登記義務は引き続き残ります。いずれにせよ、義務を履行できない事情がある場合は専門家に相談しつつ速やかに対応策を講じることをお勧めします。
なお、この義務化は2024年4月1日より前に発生した相続にも適用されます。
たとえば極端な話、「昭和や平成の時代に相続が起きてまだ登記をしていないケース」も対象です。「昔のことだから関係ないよね」では済まされませんので注意が必要です。
ただし、過去分についていきなり「明日までにやれ」というわけではなく、経過措置として2027年3月31日までに登記申請すればOKとされています。
今現在、親御さん名義のままになっている土地建物をお持ちの方は、この3年間の猶予期間のうちに手続きを済ませましょう。もし「もう権利関係が複雑で自分では無理!」という場合でも、次に説明する新制度を活用すればひとまず義務を果たすことができます。
すぐに名義変更できないときの救済策:「相続人申告登記」とは?
義務化とは言っても、先ほど触れたように相続人同士の話し合いがまとまらなかったり、相続人の一人が協力してくれなかったりと、3年以内に正式な相続登記を完了させるのが難しいケースもあります
「ちゃんとやらなきゃと思うけど、諸事情あって間に合わないかも…」と不安な方もご安心ください。そんな場合に備えて、今回の法改正ではより簡易な方法で義務を果たせる新制度が用意されています。それが 「相続人申告登記」 と呼ばれる手続きです
相続人申告登記はココがポイント!
義務履行としてみなされる簡易な申出制度: 相続人申告登記とは、一言でいうと「私はこの不動産の相続人ですよ」と法務局に申し出て登録してもらう手続きです
具体的には、登記簿上の所有者(被相続人)について相続が開始したことと、自分がその相続人であることを登記官に申告します
これを行うと申出をした相続人の氏名・住所が登記簿上に記載され、その人については相続登記の申請義務を履行したものとみなされる仕組みになっています
つまり、この申告登記を済ませておけば、正式な名義変更がまだ完了していなくてもひとまず罰則の対象外になるというわけです
一人でも申請OK、他の相続人を待たなくていい: 相続人申告登記は相続人のうちの一人からでも単独で申出可能です
通常の相続登記のように相続人全員の協力を取り付ける必要はありません。極端な話、5人相続人がいて3人だけが申告登記をした場合、その3人は義務を果たしたことになりますが、残り2人は未了という扱いです
このように各自で手続きできるので、「兄弟の一人が全然協力してくれなくて…」という場合でも自分だけでも義務を果たせるのは安心ですね。
持分の割合は不問、必要書類も最低限: 通常、不動産の相続登記をするには相続人全員を確定させ、それぞれの持分(誰がどの割合で相続するか)を決める必要があります。しかし相続人申告登記では持分の割合までは登記されないため、煩雑な遺産分割の合意書などは不要です
提出書類も「自分が相続人であることを証明できる戸籍」など最低限のものだけで足ります
極端に言えば、他の相続人が何人いようと関係なく、自分の身分関係を証明する戸籍さえ提出すれば手続きができるのです。これは大きな簡素化ポイントです。
登録免許税など手続き費用が無料: さらに嬉しいことに、相続人申告登記には登録免許税(国に納める登記の税金)がかかりません。
通常の相続登記なら不動産評価額に応じた税金がかかりますが、この申出手続きは税金ゼロです。
法務局への申請自体も郵送やオンラインで可能で、印鑑証明書の提出や押印も不要とされています。
戸籍取得の手数料や郵送費は多少かかりますが、手続きそのものはほぼコストをかけずに行えるよう配慮されています。
権利証ではないので後で正式登記が必要: 注意点として、相続人申告登記は 「私は相続人です」と公に名乗りを上げるだけの手続きであって、不動産の所有権そのものを移転する効果はありません。
したがって、この申出をしただけでは、その不動産を第三者に売ったり銀行からお金を借りる担保に入れたりすることはできません。
最終的には、改めて正式な相続登記(名義変更)を申請して初めて、自分が法律上の所有者として認められることになります。その意味では 「猶予を確保するための仮の措置」 とも言えますので、「申告登記したからもう安心!」と放置せず、しかるべきタイミングで正式な登記に進みましょう。
この相続人申告登記制度のおかげで、「時間内に相続人全員の話し合いがまとまらない…」という場合でも、とりあえず過料だけは回避しつつ義務を果たしたことにできるようになりました。
私も相談者の方には「まず申告登記だけでも出しておきましょう。そうすれば過料の心配はなくなります」とアドバイスしています。その上で、じっくり遺産分割協議や正式登記の準備を進めればいいわけですね。
相続人申告登記のメリット – 登録することで得られる安心と効果

相続人申告登記を行うことには、先述のように「義務違反による過料を免れる」という直接的なメリットがありますが、それ以外にもさまざまな利点があります。新制度の目的でもあるそれらのメリットを確認してみましょう。
●行政から見たメリット(固定資産税の徴収・空き家対策): 不動産の相続人が法務局に申告登記をすると、登記簿にその人の氏名・住所が載ります
これは自治体にとって固定資産税の納税者を把握できることを意味します。今までは名義がずっと亡くなった親のままだと役所も相続人を正確に掴めず、税金の通知や空き家の管理に関する連絡が難しい場合がありました。申告登記のおかげで「この不動産は○○さんが相続人なんだな」と行政が把握できるので、適切に税金を課税・徴収したり、空き家の管理について注意喚起したりといった対策がとりやすくなります
ひいては自治体の財政確保や空き家対策推進にもつながるため、社会全体にとってプラスになる制度と言えます。
●所有者が明確になる安心感: 相続人申告登記によって少なくとも「この土地建物には今こういう相続人がいる」という情報が公の登記に記録されます
所有者が全く不明な状態に比べれば、たとえ相続人全員ではなくても誰かの名前が載っているだけで、近隣住民や利害関係者にとっては安心材料となります。万一その不動産で何か問題(例えば敷地の境界トラブルや建物の老朽化問題など)が起きた場合でも、登記簿を見れば連絡すべき相手が分かるので、対応がスムーズになります。「登記名義人はもう亡くなっていて誰に言えばいいか分からない…」という状態を避けられるのは、大きなメリットでしょう。
●将来のトラブル防止: 相続人申告登記をしておけば、「相続人の一人が勝手に持ち主不明のまま土地を占有して他人に売ってしまった」なんてことも防ぎやすくなります。登記簿に相続人の名前が出ていれば、少なくとも第三者が「この不動産には相続人がいるんだな」と認識できますし、相続人間でも自分たちの誰かが申告したことが分かれば、お互いに無断処分などの変な動きは抑制されます。また、いざ正式に相続登記しようとするときにも、申告登記をしていた相続人であれば手続きがスムーズに進む場合があります。義務違反の過料を避けられるだけでなく、不動産の権利関係を早めに公示しておくこと自体が将来の紛争予防につながるのです
●心理的な区切りになる: これは制度の直接の効果ではありませんが、「申告登記を出す」という行為が相続人にとって一つの区切りになる面もあります。というのも、相続登記をずっと放置している方の中には、「いつかやらなきゃと気に病んでいるけど重い腰が上がらない…」という心理状態の方も多いんですね。そうした方が申告登記だけでも済ませれば、「まず第一段階クリア!」と精神的な安心感を得られます。あとは時間の猶予ができたわけですから、専門家に依頼するなり関係者とゆっくり話し合うなり、冷静に次のステップに進めるでしょう。義務化によって「やらなきゃ」というプレッシャーは高まりましたが、この申告登記制度があるおかげでプレッシャーを前向きな行動に変えることができると私は感じています。
まとめ:早めの相談・早めの手続きで安心の相続を
最後に、本記事の内容を簡単にまとめます。
●相続登記は2024年4月から法律で義務化されました。不動産を相続したら取得を知った日から3年以内に名義変更の登記申請が必要です。
●正当な理由なく怠ると最大で10万円の過料(行政罰)が科される可能性があります
相続登記を長期間放置すると、相続人が増えて権利関係が複雑化し、当事者にとっても社会にとっても様々な弊害が生じます。所有者不明土地の増加や空き家問題の深刻化など、社会的な問題の原因にもなっていました。
新制度「相続人申告登記」が導入され、事情があってすぐに正式な相続登記ができない場合でも、「自分が相続人である」ことを法務局に申告すれば義務を果たしたとみなされるようになりました。
申告登記は相続人の一人から単独ででき、提出書類も最低限でOK、登録免許税も不要という手軽さです。
ただしこれは仮の措置であり、後日正式な名義変更登記が必要な点は注意しましょう。
相続人申告登記を行うメリットとして、過料のペナルティを回避できるのはもちろん、自治体が固定資産税の徴収先を把握できたり、所有者不明状態を解消してトラブルを防止できたりといった効果があります。
相続人自身にとっても心理的負担を減らし、安心して次の手続きを進めるための区切りとなります。
弁護士や専門家への相談の重要性: 相続登記の義務化によって、「やらなければ」というプレッシャーを感じている方もいるかもしれません。しかし、焦って一人で抱え込む必要はありません。 相続人の調査や書類集め、他の親族との調整などは専門家に任せることで格段にスムーズに進みます。司法書士は登記手続きのプロですし、紛争がある場合には私たち弁護士が法的な解決も含めてサポートできます。
特に今回の義務化対象となる過去の未了分の相続登記は厄介な案件も多いですが、「早めに相談・早めに対応」が何よりの解決策です。
私自身、相続に関するご相談を日々受けていますが、「もっと早く相談してもらえればこんなに悩まなくて済んだのに…」と感じるケースが少なくありません。
相続登記の義務化は一見ハードルが上がったように思えるかもしれませんが、視点を変えれば「相続問題を先送りせず早めに片付けて、次世代に悩みを残さないチャンス」とも言えます。
今回ご紹介した制度を上手に活用しつつ、専門家の力も借りながら、円満で安心な相続手続きを進めていきましょう。 もし現在相続登記でお困りのことがあれば、どうぞお気軽に当事務所までご相談ください。 私・平野潤が親身になってお話を伺い、最善の解決策をご提案いたします。一緒に悩みを解消して、皆さんの大切な財産とご家族の未来を守るお手伝いができれば幸いです。
参考資料:
●法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」 (法務省)
●大阪市公式サイト「令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました」 (大阪市)
●朝日新聞社 相続会議「相続登記の義務化とは 罰則から過去の相続分の扱いまでわかりやすく解説」 (相続会議)

2004年の弁護士登録以降、個人・法人問わず幅広い事件を担当し、クライアントにとっての重大事には誠実かつ丁寧に寄り添う。命運に配慮し、最善策を模索。豊富な実績と十分なコミュニケーションで、敷居の高さを感じさせない弁護士像を追求してきた。1978年大阪府出身、京都大学法学部卒業。2011年に独立。不動産・労務・商事・民事・破産・家事など多様な分野を扱い、2024年6月に蒼生法律事務所へ合流。相続・遺言