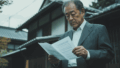相続人間に争いがなければ、相続手続は簡単に終わる――そう思っていませんか?
実際には、戸籍や財産の調査、書類作成、金融機関や法務局とのやり取り、そして相続税の申告まで、やるべきことは多岐にわたります。
手続きを誤ると、思わぬトラブルや追加の税負担につながるリスクも…。
本記事では、相続手続(遺産整理)の具体的な流れや注意点を解説し、必要に応じて専門家に相談すべきタイミングについてもお伝えします。
相続手続(遺産整理)

被相続人が遺言書を作成していない場合、相続人の調査、相続財産の調査ができれば、相続人全員で遺産分割協議を行うことになります。
遺産分割の条件などについて、相続人間で意見や希望が食い違うようであれば、弁護士に依頼して、調停や審判といった裁判手続をとることも考えなければいけません。
では、相続人間で争いがなければ、直ぐに相続財産の全部または一部を受け取って、相続手続を終えることができるでしょうか。残念ながら、そう簡単にはいかないかもしれません。
相続関係を特定できる書類を揃えて、金融機関や証券会社、法務局などで各種の手続をとらなければならず、相当な手間暇がかかることもあります。また、相続財産が大きければ、期限内に相続税の申告・納付を行う必要があります。
そのため、相続人間で争いがない場合であっても、相続に関する手続を全部まとめてお願いしたい、という依頼も少なくありません(相続人調査・相続財産調査などを含めて「遺産整理手続」と呼ぶこともあります)。
以下、相続手続(遺産整理)について、ご説明します。
1) 相続人・相続財産調査の実施
相続手続(遺産整理)は、相続人や相続財産の調査から始まり、遺産分割協議書の作成、預貯金や不動産の名義変更、相続税の申告など多くの手続が必要になります。
相続人間で争いがなくても、手続は煩雑かつ専門的で、期限や書類の不備がトラブルの原因となることも。
相続人・相続財産調査については、相続手続の全体像や具体的な流れ、専門家に依頼するメリットについてわかりやすく別記事で解説しています。
ぜひご一読ください。

2) 遺言書の確認

被相続人が遺言書を作成していた場合は、遺言書の内容を確認する必要があります。
自筆証書遺言が見つかった場合には、家庭裁判所で遺言書の検認手続をとる必要があります。
遺言書がない場合は、法定相続に基づいて分配されます。
3)(必要に応じて)相続放棄の手続
相続財産を調査した結果、被相続人の債務・負債が相続財産を超過することが明らかになった場合には、相続放棄の手続をとる必要があるか、検討します。
ご要望に応じて、相続放棄の申述書を作成し、家庭裁判所での手続をとります。

4) 相続手続の代行

遺産分割の条件について相続人間で争いがない場合は、遺産分割協議書を作成したうえで、下記のように、預貯金の払戻し、株式の売却、不動産の名義変更など様々な手続を代行します。
-
A) 相続情報一覧図の作成、申出
被相続人と相続人の関係性を証明するべく、「相続情報一覧図」を作成し、法務局に申出します。
大量の戸籍・除籍を何通も取り寄せる必要がなくなるため、費用を抑えることができ、手続をスムースに進めることができるようになります。
-
B) 相続財産目録の作成
相続財産の調査結果を踏まえて、相続財産目録を作成します。
未公開株式や不動産の評価が難しい場合には、税理士・公認会計士や不動産鑑定士などに協力を依頼します。
被相続人の債務・負債についても、明確にしておく必要があります。
-
C)遺産分割協議書の作成
相続財産の全体像が明らかになれば、誰がどの財産を承継するのか、条件について協議・調整を行います。当事務所では、相続の専門家として、遺産分割の条件などについてアドバイスを行います。
相続人全員が合意できれば、「遺産分割協議書」を作成し、各自に署名・押印をしてもらいます。

-
D)不動産の名義変更、売却など
相続財産である不動産の名義を、被相続人から承継相続人の名義に変更します(移転登記手続)。登記手続に関しては、当事務所が連携している司法書士をご紹介します。
不動産の売却を希望される場合には、当事務所が連携している不動産会社をご紹介します。借地上建物や共有不動産の場合には、地主や他の共有者との協議が必要となるため、ご要望に応じて、関係者との協議・交渉を行います。
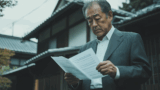
-
E) 銀行・信金の預貯金の名義変更
各種金融機関(銀行、信用金庫、信用組合など)での預貯金の解約・払戻手続を代行します。相続税の申告手続きに必要な残高証明書なども取得します。
-
F)証券口座・有価証券の名義変更
株式や社債、投資信託、ゴルフ会員権やリゾート会員権などの名義を、被相続人から承継する相続人の名義に変更します。
-
G) 貴金属・美術品などの売却
相続財産である宝飾品や高級時計、絵画や陶器などを売却する場合には、ご要望に応じて、当事務所と連携する美術商などをご紹介します。
-
H) 債務・負債の返済など
被相続人が負っていた債務・負債について、必要に応じて、債権者と協議・交渉します。債務・負債の存否や残額に争いがある場合には、裁判手続を見据えた対応が必要となります。
-
I) 相続税の申告・納付
相続税の申告・納付が必要な場合には、当事務所が連携する相続に強い税理士をご紹介します。当事務所として、税理士に対する相続財産の関する資料提供、情報提供などのサポートを行います。

2004年の弁護士登録以降、個人・法人問わず幅広い事件を担当し、クライアントにとっての重大事には誠実かつ丁寧に寄り添う。命運に配慮し、最善策を模索。豊富な実績と十分なコミュニケーションで、敷居の高さを感じさせない弁護士像を追求してきた。1978年大阪府出身、京都大学法学部卒業。2011年に独立。不動産・労務・商事・民事・破産・家事など多様な分野を扱い、2024年6月に蒼生法律事務所へ合流。相続・遺言